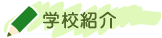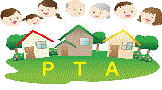�ߘa�V�N�x�@�ɂ��͂炫�炫����L�@�P�w��
�V���Q�W���i���j�������Ղ�
�@�u�������Ղ�v�̊J��ɎQ�����Ă܂���܂����B�������ҏ��ł������A���N���n��̊F����̔M���v�����W�܂�A�܂�̋�C�͊��C�ɖ����Ă��܂����B�c�O�Ȃ���A�q�ǂ������̎p�����邱�Ƃ͊����܂���ł������A����ł��A���̂����炱����ɏ���ꂽ���̂�A�s��20���N�̎v���A�А��̗ǂ��������A�`���������p���S���肽���̎p��ڂɂ��Ȃ���A�u���̒n��ɍ�����������Ƃ͉����v�����߂čl����ЂƂƂ��ƂȂ�܂����B
�@�n��̊F���S�����߂ď�������Ă������Ƃ��悭�`����Ă��āA�u�Ղ�v�Ƃ����ꂪ�A�l�Ɛl�Ƃ��Ȃ��A������z���āu�ւ�v�����L�����ȋ@��ł���Ɗ����܂����B
�@����͂��ЁA�q�ǂ������ƈꏏ�ɂ܂�̓��킢��̌��������Ǝv���܂��B
 �@
�@

�@�u�������Ղ�v�̊J��ɎQ�����Ă܂���܂����B�������ҏ��ł������A���N���n��̊F����̔M���v�����W�܂�A�܂�̋�C�͊��C�ɖ����Ă��܂����B�c�O�Ȃ���A�q�ǂ������̎p�����邱�Ƃ͊����܂���ł������A����ł��A���̂����炱����ɏ���ꂽ���̂�A�s��20���N�̎v���A�А��̗ǂ��������A�`���������p���S���肽���̎p��ڂɂ��Ȃ���A�u���̒n��ɍ�����������Ƃ͉����v�����߂čl����ЂƂƂ��ƂȂ�܂����B
�@�n��̊F���S�����߂ď�������Ă������Ƃ��悭�`����Ă��āA�u�Ղ�v�Ƃ����ꂪ�A�l�Ɛl�Ƃ��Ȃ��A������z���āu�ւ�v�����L�����ȋ@��ł���Ɗ����܂����B
�@����͂��ЁA�q�ǂ������ƈꏏ�ɂ܂�̓��킢��̌��������Ǝv���܂��B
�V���Q�T���i���j�T�}�[�X�N�[���Q���ځE���C�R����
�@�T�}�[�X�N�[���Q���ڂł��B��������T�}�[�X�N�[���ɎQ������q�A��������w�K�̌��������鐶�k�A�w���A�n��̕��X����������Ⴂ�܂����B������痈�Ă���q�������́A�������蒆�w���A���Z���A��w���A�n��̕��X�Ɋ���Ă��܂��B
�@�U�N���́A�u���N���w���ɂȂ�����A�T�}�[�X�N�[���ɋ����鑤�Ƃ��ĎQ�����܂��v�Ƙb���Ă���܂����B���w���A���Z���������A�u���N�����܂��I�v�ƌ����Ă���܂����B
�@�����͑�䒆�̊w�Z�^�c���c����A���@�ɂ��炵�Ă��������܂����B
�@�{�Z����ɂ��Ă���u�Ȃ���̋���v�́A���������F����̂��������Ȏx���̂��ƂɈ�܂�Ă��܂��B�Q���ԂƂ����Z�����Ԃł������A�q�������̐S�Ɏc��L���ȑ̌����Ƃ��ɖa���Ă����������F����ɁA�d�˂Ă���\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�@���C�R���ځB���E���́A�l�������C�ɂ���ʌ�����o�Ă���u�l�����o�琬�v���O�����v�̎��{�A���ʊ�����C�́A�w����̊J�������ꂩ�璚�J�ɓ`���A�E�����q���Ƃ��āA�͋[�w��������{�������C���s���܂����B
�@�����Q�w�������肽���Ȃ�悤�ȓ��e����ł����B�E���ō��ߍ������C���ł������Ƃ͑傫�ȍ��Y�ƂȂ�܂��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�T�}�[�X�N�[���Q���ڂł��B��������T�}�[�X�N�[���ɎQ������q�A��������w�K�̌��������鐶�k�A�w���A�n��̕��X����������Ⴂ�܂����B������痈�Ă���q�������́A�������蒆�w���A���Z���A��w���A�n��̕��X�Ɋ���Ă��܂��B
�@�U�N���́A�u���N���w���ɂȂ�����A�T�}�[�X�N�[���ɋ����鑤�Ƃ��ĎQ�����܂��v�Ƙb���Ă���܂����B���w���A���Z���������A�u���N�����܂��I�v�ƌ����Ă���܂����B
�@�����͑�䒆�̊w�Z�^�c���c����A���@�ɂ��炵�Ă��������܂����B
�@�{�Z����ɂ��Ă���u�Ȃ���̋���v�́A���������F����̂��������Ȏx���̂��ƂɈ�܂�Ă��܂��B�Q���ԂƂ����Z�����Ԃł������A�q�������̐S�Ɏc��L���ȑ̌����Ƃ��ɖa���Ă����������F����ɁA�d�˂Ă���\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�@���C�R���ځB���E���́A�l�������C�ɂ���ʌ�����o�Ă���u�l�����o�琬�v���O�����v�̎��{�A���ʊ�����C�́A�w����̊J�������ꂩ�璚�J�ɓ`���A�E�����q���Ƃ��āA�͋[�w��������{�������C���s���܂����B
�@�����Q�w�������肽���Ȃ�悤�ȓ��e����ł����B�E���ō��ߍ������C���ł������Ƃ͑傫�ȍ��Y�ƂȂ�܂��B
�V���Q�S���i�j�T�}�[�X�N�[���P���ځE���C2����
�@���N���A�n�悮��݂ŏ��w���̊w�т��x����T�}�[�X�N�[���P���ڂ��n�܂�܂����B��䐼���A��䒆�A�ӂ��ݖ썂�Z�̐��k����A���Ɛ��̍��Z���A�����w�@��w�̑�w���A�����Ė����ψ��E���������ψ��̊F���܁A����ɂ͒n��̕��X�܂�…��������̉����Ȃ܂Ȃ������W�܂�܂����B
�@�q�ǂ������́A�قȂ鐢��Ƃ̂ӂꂠ���̒��ŐV���ȋC�Â�����A�w�т̊y�����ɏo������肵�Ă��܂��B�Ⴂ��y�����Ƃ̌𗬂͎h���ɖ����A�n��̑�l�����̌���肩��͈��S���Ɨ�܂�������Ă���l�q�ł��B���w���Ƒ�w�������������ŁA�q�������ɐڂ���l�q�͂ƂĂ��قق��܂����v���܂����B
�@�ӂ��ݖ�s����ψ���̒��q���璷�l�͂��߂S���̕��X�A�ӂ��ݖ썂���w�Z�A��䐼���w�Z�A��䒆�w�Z�̍Z���搶�������@�ɖK��Ă��������܂����B
�@���E���́A�E�����Ō��C�ł��B�����̋��ލ쐬�A����u�X�N�[���^�N�g�̊��p�̎d���v�A���ʎx������ɂ��āA�E��������i��Ŏ��g��ł��܂����B








�@���N���A�n�悮��݂ŏ��w���̊w�т��x����T�}�[�X�N�[���P���ڂ��n�܂�܂����B��䐼���A��䒆�A�ӂ��ݖ썂�Z�̐��k����A���Ɛ��̍��Z���A�����w�@��w�̑�w���A�����Ė����ψ��E���������ψ��̊F���܁A����ɂ͒n��̕��X�܂�…��������̉����Ȃ܂Ȃ������W�܂�܂����B
�@�q�ǂ������́A�قȂ鐢��Ƃ̂ӂꂠ���̒��ŐV���ȋC�Â�����A�w�т̊y�����ɏo������肵�Ă��܂��B�Ⴂ��y�����Ƃ̌𗬂͎h���ɖ����A�n��̑�l�����̌���肩��͈��S���Ɨ�܂�������Ă���l�q�ł��B���w���Ƒ�w�������������ŁA�q�������ɐڂ���l�q�͂ƂĂ��قق��܂����v���܂����B
�@�ӂ��ݖ�s����ψ���̒��q���璷�l�͂��߂S���̕��X�A�ӂ��ݖ썂���w�Z�A��䐼���w�Z�A��䒆�w�Z�̍Z���搶�������@�ɖK��Ă��������܂����B
�@���E���́A�E�����Ō��C�ł��B�����̋��ލ쐬�A����u�X�N�[���^�N�g�̊��p�̎d���v�A���ʎx������ɂ��āA�E��������i��Ŏ��g��ł��܂����B
�V���Q�R���i���j���i����
�@�E���ŋ��͂��čZ���̔��i�������s���܂����B��������ʋ����A�q�ɂȂǂɂ��鋳�ނ�p�����ЂƂm�F���A�g������́E�C�����K�v�Ȃ��́E�p��������̂ɕ����Đ������܂����B���N�g���Ă������ނɂ́A�q�ǂ������̊w�т̗��j���������A�搶�����v���o�b�������Ȃ��璚�J�ɍ�Ƃ�i�߂Ă��܂����B
�@���ɐ}�H���◝�Ȏ��ł́A�ׂ����ޗ���������A���ނ���[�̍H�v�����߂��܂��B�搶���́A�g���₷������S�����l���Ȃ���A�I�̔z�u�Ȃǂ�b�������A�����K�Ȋw�K���Â���ɓw�߂Ă��܂����B
�@�̈�فA�̈珬���������̒��ɂ��A�搶����������č�Ƃ����Ă��܂����B
 �@
�@
 �@
�@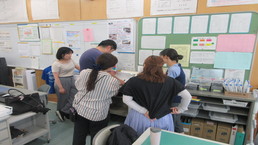
�@�E���ŋ��͂��čZ���̔��i�������s���܂����B��������ʋ����A�q�ɂȂǂɂ��鋳�ނ�p�����ЂƂm�F���A�g������́E�C�����K�v�Ȃ��́E�p��������̂ɕ����Đ������܂����B���N�g���Ă������ނɂ́A�q�ǂ������̊w�т̗��j���������A�搶�����v���o�b�������Ȃ��璚�J�ɍ�Ƃ�i�߂Ă��܂����B
�@���ɐ}�H���◝�Ȏ��ł́A�ׂ����ޗ���������A���ނ���[�̍H�v�����߂��܂��B�搶���́A�g���₷������S�����l���Ȃ���A�I�̔z�u�Ȃǂ�b�������A�����K�Ȋw�K���Â���ɓw�߂Ă��܂����B
�@�̈�فA�̈珬���������̒��ɂ��A�搶����������č�Ƃ����Ă��܂����B
�V���Q�Q���i�j�@���C�P���ځE�l�ʒk�i�`�Q�T���j
�@�q�ǂ������̂��Ȃ��Â��ȍZ�ɂ̒��ŁA�搶�������̊w���Ɍ����Ă��܂��܂ȏ����⌤�C�Ɏ��g��ł��܂��B
�@�����́A�}�H�̍�i�W�Ɍ����������Ƃ��āA�搶���������̍�i�̒�����o�i����I�肷���Ƃ��s���܂����B�}�H��C�����S�ƂȂ�A�w���̈Ӑ}���i�����鎋�_�̐���������܂����B��i��ЂƂɍ��߂�ꂽ�v����H�v�J�Ɍ��āA�ǂ̍�i���W����ŋP������b�������Ȃ���I�т܂����B�q�ǂ������̑n���̖͂L�����ɉ��߂Ċ������܂����B
�@�̈�̎��ƂɌ��������C�Ƃ��āA�̈��C�����S�ƂȂ�A�u�}�b�g�^���v�̕⏕���@�ɂ��Ă̎��Z���C�����{���܂����B���S�ɔz�����Ȃ���A���������S���Ē���ł���悤�A�⏕�̃^�C�~���O������̍H�v�Ȃǂ����ۂɑ̂����Ȃ���m�F���܂����B�搶���m�ňӌ����������A���悢�w�����@���w�э����M�d�Ȏ��ԂƂȂ�܂����B
�@�P�w���̎q�ǂ������̗l�q�ɂ��āA�ی�҂̕��X�ɂ��b�����Ă��������l�ʒk���n�܂�܂����B���T�����ς����{����܂��B






�@�q�ǂ������̂��Ȃ��Â��ȍZ�ɂ̒��ŁA�搶�������̊w���Ɍ����Ă��܂��܂ȏ����⌤�C�Ɏ��g��ł��܂��B
�@�����́A�}�H�̍�i�W�Ɍ����������Ƃ��āA�搶���������̍�i�̒�����o�i����I�肷���Ƃ��s���܂����B�}�H��C�����S�ƂȂ�A�w���̈Ӑ}���i�����鎋�_�̐���������܂����B��i��ЂƂɍ��߂�ꂽ�v����H�v�J�Ɍ��āA�ǂ̍�i���W����ŋP������b�������Ȃ���I�т܂����B�q�ǂ������̑n���̖͂L�����ɉ��߂Ċ������܂����B
�@�̈�̎��ƂɌ��������C�Ƃ��āA�̈��C�����S�ƂȂ�A�u�}�b�g�^���v�̕⏕���@�ɂ��Ă̎��Z���C�����{���܂����B���S�ɔz�����Ȃ���A���������S���Ē���ł���悤�A�⏕�̃^�C�~���O������̍H�v�Ȃǂ����ۂɑ̂����Ȃ���m�F���܂����B�搶���m�ňӌ����������A���悢�w�����@���w�э����M�d�Ȏ��ԂƂȂ�܂����B
�@�P�w���̎q�ǂ������̗l�q�ɂ��āA�ی�҂̕��X�ɂ��b�����Ă��������l�ʒk���n�܂�܂����B���T�����ς����{����܂��B
�V���P�W���i���j�P�w���I�Ǝ�
�@�����琰��n������̉��A�q�ǂ������͌��C�ɓo�Z���Ă��܂����B�����ɓ���ƁA���ɂ͒S�C�̐搶����̐S���܂郁�b�Z�[�W���B�F�Ƃ�ǂ�̃`���[�N�ŕ`���ꂽ�C���X�g�ƂƂ��ɁA�搶�̎v�����`����Ă��܂��B�q�ǂ������͂��̃��b�Z�[�W�����āA���R�ƏΊ�ɂȂ��Ă��܂����B
�@�I�Ǝ��ł́A������\�̂R�N���ƂU�N�������h�Ȍ��t���q�ׂĂ���܂����B�u���J�ɏ������Ƃ�������čd�M�̑�\�ɑI��܂����B�v�u�F�B�Ƃ����Ȃ��A���ǂ��߂����܂����B�Q�w���͐[���F�B�Ƃ����������ł��B�v���X�Ƃ����p�ɁA���̎������搶�������S���A���肪�苿���܂����B
�@�I�Ǝ���́A�d�M�W�œ��܂����q�ǂ������ւ̏�`�B������܂����B��\�̂U�N���̕Ԏ����ƂĂ����炵�������ł��B
�@�����ɖ߂�ƁA���悢��ʒm�\�̎��ԁB�搶�����l�ЂƂ�Ɏ�n�����ʒm�\���A�ْ������ʎ����Ŏ��q�A���������ɏΊ��������q�A�����ƒ��g���̂����q…�B���̎p����A�P�w���̓w�͂�����������A�����M���Ȃ�܂����B
�@��������͉ċx�݁B���̂₯���Ȃ��A���C�ɉ߂����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B�Q�w���A�܂����萬�������q�ǂ������ɉ��̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B
�@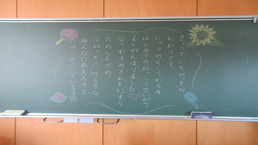 �@
�@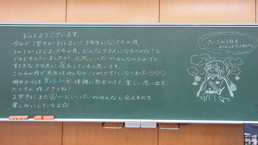
 �@
�@
 �@
�@
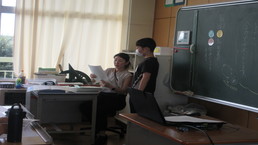 �@
�@
�@�����琰��n������̉��A�q�ǂ������͌��C�ɓo�Z���Ă��܂����B�����ɓ���ƁA���ɂ͒S�C�̐搶����̐S���܂郁�b�Z�[�W���B�F�Ƃ�ǂ�̃`���[�N�ŕ`���ꂽ�C���X�g�ƂƂ��ɁA�搶�̎v�����`����Ă��܂��B�q�ǂ������͂��̃��b�Z�[�W�����āA���R�ƏΊ�ɂȂ��Ă��܂����B
�@�I�Ǝ��ł́A������\�̂R�N���ƂU�N�������h�Ȍ��t���q�ׂĂ���܂����B�u���J�ɏ������Ƃ�������čd�M�̑�\�ɑI��܂����B�v�u�F�B�Ƃ����Ȃ��A���ǂ��߂����܂����B�Q�w���͐[���F�B�Ƃ����������ł��B�v���X�Ƃ����p�ɁA���̎������搶�������S���A���肪�苿���܂����B
�@�I�Ǝ���́A�d�M�W�œ��܂����q�ǂ������ւ̏�`�B������܂����B��\�̂U�N���̕Ԏ����ƂĂ����炵�������ł��B
�@�����ɖ߂�ƁA���悢��ʒm�\�̎��ԁB�搶�����l�ЂƂ�Ɏ�n�����ʒm�\���A�ْ������ʎ����Ŏ��q�A���������ɏΊ��������q�A�����ƒ��g���̂����q…�B���̎p����A�P�w���̓w�͂�����������A�����M���Ȃ�܂����B
�@��������͉ċx�݁B���̂₯���Ȃ��A���C�ɉ߂����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B�Q�w���A�܂����萬�������q�ǂ������ɉ��̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B
�@
�V���P�V���i�j���y���݉�E��|���E�e�X�g
�@�ߑO���̋����ł́A�Ō�̊m�F�e�X�g�ɐ^���ȕ\��Ō��������q�ǂ������̎p�B�����������M�̉��A���Ȃ����Ȃ���̌������A���ꂼ�ꂪ���̂P�w���̊w�т������Ȃ�ɐU��Ԃ��Ă��܂����B
�@��|�������Ă���N���X������܂����B���b�J�[������̋r�A���~���̌C���܂ŁA���i���߂��������ȏꏊ�ɂ��ڂ������Ȃ���A���͂��ăS�V�S�V�B�G�Ђɐ����܂܂������ɂ��A�����̐Ղ������܂����B�u�P�w�����肪�Ƃ��I�v�Ƃ����C���������߂āA�݂�ȂŊw�Z���s�J�s�J�ɂ��܂����B
�@�����āA���y���݉�I�e�N���X���ƂɍH�v���Â炵����悪�ڔ������ł��B�}�W�b�N����A����Q�[������A�N�C�Y����܂ŁB�F�B�Ɖ߂������ʂȎ��ԂɁA�q�ǂ������̊��������Ȑ����Z�ɒ��ɋ����܂����B
�@�Q�N���̋����ł̃}�W�b�N�́A�ƂĂ��N�I���e�B�������A���˂��������킩��Ȃ��قǂł����B���炵�������ł��B
�@�����̏I�Ǝ��ł́A�P�w���̐������������A���̈���ւ̃G�[���𑗂肽���Ǝv���܂��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�ߑO���̋����ł́A�Ō�̊m�F�e�X�g�ɐ^���ȕ\��Ō��������q�ǂ������̎p�B�����������M�̉��A���Ȃ����Ȃ���̌������A���ꂼ�ꂪ���̂P�w���̊w�т������Ȃ�ɐU��Ԃ��Ă��܂����B
�@��|�������Ă���N���X������܂����B���b�J�[������̋r�A���~���̌C���܂ŁA���i���߂��������ȏꏊ�ɂ��ڂ������Ȃ���A���͂��ăS�V�S�V�B�G�Ђɐ����܂܂������ɂ��A�����̐Ղ������܂����B�u�P�w�����肪�Ƃ��I�v�Ƃ����C���������߂āA�݂�ȂŊw�Z���s�J�s�J�ɂ��܂����B
�@�����āA���y���݉�I�e�N���X���ƂɍH�v���Â炵����悪�ڔ������ł��B�}�W�b�N����A����Q�[������A�N�C�Y����܂ŁB�F�B�Ɖ߂������ʂȎ��ԂɁA�q�ǂ������̊��������Ȑ����Z�ɒ��ɋ����܂����B
�@�Q�N���̋����ł̃}�W�b�N�́A�ƂĂ��N�I���e�B�������A���˂��������킩��Ȃ��قǂł����B���炵�������ł��B
�@�����̏I�Ǝ��ł́A�P�w���̐������������A���̈���ւ̃G�[���𑗂肽���Ǝv���܂��B
�V���P�U���i���j�\�t�g�o���[�{�[���E��i�ӏ�
�@�S�N���������ő̈�̎��Ƃ��s���܂����B��ڂ́u�\�t�g�o���[�{�[���v�B�_�炩���{�[�����g���āA�݂�ȂŊy�����������܂����B�ŏ��̓��[�����m�F���Ȃ���A�`�[���Ńp�X���K�����Ă��܂����B�{�[������邽�тɁu�i�C�X�I�v�Ɛ������������p���ƂĂ���ۓI�ł����B
�@�T�N���̐}�H�ł́A�F�B�̍�i���ӏ܂��鎞�Ԃ�����܂����B�G�i���ʁj�Ɨ��̍�i�ł��B�G�́u�G�߂������āv���̂́u�r�[�ʑ�`���v�ł��B���ʂ��猩����A�߂��猩����Ƃ��ꂼ�ꂪ�v���v���̐��E��\��������i�����т܂����B�Â��ɂ��܂��Ċӏ܂��A�F�B�̂悢�Ƃ�����L�����Ă��܂����B�L���E�����͂܂�ŏ����Ȕ��p�ق̂悤�ł����B�����Ƃ͈Ⴄ���_�┭�z�ɐG��邱�ƂŁA�q�ǂ������̊���������ɖL���ɂȂ��Ă����̂������܂����B���ꂩ����A�n������y�����ƁA�ӏ܂���ʔ����̗������ɂ��Ă��������ł��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�S�N���������ő̈�̎��Ƃ��s���܂����B��ڂ́u�\�t�g�o���[�{�[���v�B�_�炩���{�[�����g���āA�݂�ȂŊy�����������܂����B�ŏ��̓��[�����m�F���Ȃ���A�`�[���Ńp�X���K�����Ă��܂����B�{�[������邽�тɁu�i�C�X�I�v�Ɛ������������p���ƂĂ���ۓI�ł����B
�@�T�N���̐}�H�ł́A�F�B�̍�i���ӏ܂��鎞�Ԃ�����܂����B�G�i���ʁj�Ɨ��̍�i�ł��B�G�́u�G�߂������āv���̂́u�r�[�ʑ�`���v�ł��B���ʂ��猩����A�߂��猩����Ƃ��ꂼ�ꂪ�v���v���̐��E��\��������i�����т܂����B�Â��ɂ��܂��Ċӏ܂��A�F�B�̂悢�Ƃ�����L�����Ă��܂����B�L���E�����͂܂�ŏ����Ȕ��p�ق̂悤�ł����B�����Ƃ͈Ⴄ���_�┭�z�ɐG��邱�ƂŁA�q�ǂ������̊���������ɖL���ɂȂ��Ă����̂������܂����B���ꂩ����A�n������y�����ƁA�ӏ܂���ʔ����̗������ɂ��Ă��������ł��B
�V���P�T���i�j�{�Œm�������Ƃ��N�C�Y�ɂ��悤�E�����W
�@�R�N�Q�g�̋�������A�y�������ȏ����肪�������Ă��܂����B�̂����Ă݂�ƍ���̊w�K�u�{�Œm�������Ƃ��N�C�Y�ɂ��悤�v�̃N�C�Y�������Ă���Ƃ���ł����B
�@�q�ǂ������͎����Ŗ{��ǂ��e�����ƂɍH�v�����炵���N�C�Y���o�肵�Ă��܂��B�o��҂̕\��͂ǂ����ւ炵���ł��B���\�������Ď�������Ă����������Ă���q�ǂ��������������܂����B�u�t���~���S�̑̂͂Ȃ��s���N�F�Ȃ́H�v�ł́A�s���N�F�̐H�ו���H�ׂĂ��邩�炾�����ł��B���߂Ēm��܂����B�{����w�m���������̌��t�œ`���邱�ƂŁA�Ǐ����[�܂��Ă���悤�ł��B
�@�ƊԂ̋x�ݎ��ԁA�Q�g����L����ʂ�߂���Ƃ���ɁA�R�N�P�g����u�Z���搶�����ɗ��Ă��������I�������W�����Ƃ���ł��v�Ǝq�ǂ������ɗU���܂����B�C�X�̏�̂�������ɁA�����W�̃����o�[�������A�Ȃɍ��킹�ĐU�t�����Ă��܂��B���̃L���̂��铮���A���߃|�[�Y�A�ڐ��ƕ\����炵���A�唚�ł����B�I���ƁA�u�������A�������I�v�̎q�ǂ������̃A���R�[�����R��������܂����B
�@�w�т��V�т��S�͂Ŋy���ޑ��R�N���ł����B
 �@
�@
 �@
�@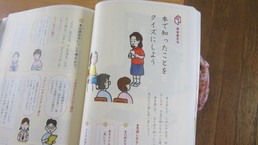
 �@
�@
�@�R�N�Q�g�̋�������A�y�������ȏ����肪�������Ă��܂����B�̂����Ă݂�ƍ���̊w�K�u�{�Œm�������Ƃ��N�C�Y�ɂ��悤�v�̃N�C�Y�������Ă���Ƃ���ł����B
�@�q�ǂ������͎����Ŗ{��ǂ��e�����ƂɍH�v�����炵���N�C�Y���o�肵�Ă��܂��B�o��҂̕\��͂ǂ����ւ炵���ł��B���\�������Ď�������Ă����������Ă���q�ǂ��������������܂����B�u�t���~���S�̑̂͂Ȃ��s���N�F�Ȃ́H�v�ł́A�s���N�F�̐H�ו���H�ׂĂ��邩�炾�����ł��B���߂Ēm��܂����B�{����w�m���������̌��t�œ`���邱�ƂŁA�Ǐ����[�܂��Ă���悤�ł��B
�@�ƊԂ̋x�ݎ��ԁA�Q�g����L����ʂ�߂���Ƃ���ɁA�R�N�P�g����u�Z���搶�����ɗ��Ă��������I�������W�����Ƃ���ł��v�Ǝq�ǂ������ɗU���܂����B�C�X�̏�̂�������ɁA�����W�̃����o�[�������A�Ȃɍ��킹�ĐU�t�����Ă��܂��B���̃L���̂��铮���A���߃|�[�Y�A�ڐ��ƕ\����炵���A�唚�ł����B�I���ƁA�u�������A�������I�v�̎q�ǂ������̃A���R�[�����R��������܂����B
�@�w�т��V�т��S�͂Ŋy���ޑ��R�N���ł����B
�V���P�S���i���j�@�������܂����I�E�Ԃ����S�[���E�}�b�g�V��
�@���̏T���ŁA�c�o���̃q�i�������������܂����B�����������Ă����̂ŁA���ꂵ���悤�Ȃ��т����悤�ȁA���т����悤�Ȃ��ꂵ���悤�ȕ��G�ȋC�����ł͂���܂����A�����ɑ����������Ƃ͊�тł��B���C�ɗ��N�܂������ɖ߂��Ă��Ăق����Ɗ肢�܂��B
�@�Z�����O�ɂ́A�̃J�[�e���Ƃ��āA�S�[�����͔|���Ă��܂��B��N�́A�̃J�[�e�������ɂł����̂ŁA�ӂ��ݖ�s����\������܂����B���N���͔|���Ă���̂ł����A���߂Ď����Ȃ�܂����B�傫���͂��������T�Z���`�قǂ̂��킢���S�[���̎��̐Ԃ����ł��B���ꂩ��ǂ�ǂ�����Ȃ�̂��y���݂ł��B
�@�P�N���̑̈�B�P�C�Q�g�����Ŏ��{���Ă��܂��B�O���낪��A��낱�낪��A��l�g�ł̊ۑ����낪��A�ǂ̂ڂ�t�����A���������A���������сA�A���e�i�A������̑������A�쒵�ѓ��A�}�b�g�����h������Ă�������^�����ł��܂����B��̂����ɋC��t���Ȃ���A���݂��ɐ��������Ă��܂����B
 �@
�@
 �@
�@ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
 �@
�@
 �@
�@
�@���̏T���ŁA�c�o���̃q�i�������������܂����B�����������Ă����̂ŁA���ꂵ���悤�Ȃ��т����悤�ȁA���т����悤�Ȃ��ꂵ���悤�ȕ��G�ȋC�����ł͂���܂����A�����ɑ����������Ƃ͊�тł��B���C�ɗ��N�܂������ɖ߂��Ă��Ăق����Ɗ肢�܂��B
�@�Z�����O�ɂ́A�̃J�[�e���Ƃ��āA�S�[�����͔|���Ă��܂��B��N�́A�̃J�[�e�������ɂł����̂ŁA�ӂ��ݖ�s����\������܂����B���N���͔|���Ă���̂ł����A���߂Ď����Ȃ�܂����B�傫���͂��������T�Z���`�قǂ̂��킢���S�[���̎��̐Ԃ����ł��B���ꂩ��ǂ�ǂ�����Ȃ�̂��y���݂ł��B
�@�P�N���̑̈�B�P�C�Q�g�����Ŏ��{���Ă��܂��B�O���낪��A��낱�낪��A��l�g�ł̊ۑ����낪��A�ǂ̂ڂ�t�����A���������A���������сA�A���e�i�A������̑������A�쒵�ѓ��A�}�b�g�����h������Ă�������^�����ł��܂����B��̂����ɋC��t���Ȃ���A���݂��ɐ��������Ă��܂����B
�V���P�P���i���j�@�����q�ǂ��܂�
�@���N�x�́u�����q�ǂ��܂�v�ł́A���̎��݂Ƃ��āA�c����ǂ��Ƃ̂��X���o�i���܂����B�w�N�����يw�N�𗬂̒��ŁA�q�ǂ������͗͂����킹�Ċ��E�����E�^�c�Ɏ��g�݂܂����B
�@�u�o�C�L���}�������Ă�I���傭�ς�܂�V���[�e�B���O�v�u���҂��݂�̂킭�킭��Ȃ��v�u�s�N�~������s�N�~���t�B�b�V���O�v�u�M���M���Ŏ~�߂납�`�L���[�X�v�u�o�C�L���}���ɏ��āA��Q�������[�v�u�ԃs�N�~���������v…�ǂ̂��X�ɂ����ꂼ��̔ǂ́u�A�C�f�B�A�v�Ɓu�H�v�v���l�܂��Ă��āA���ꂵ�����q������Ί炢���ς��ł����B�u�X�y�V�����V���b�v�r�搶�v�́A�R�O�b�Ԃłǂꂾ���J�E���^�[�������邩�Ƃ����搶���ŏ��o�X�ł��B���X�����Ȃ���A�Í��X�^���v�����[������A�y�����{���ł����B
�@��w�N�̎q�ǂ���������t���s���A���w�N�̎q�ǂ������͐�`�̌Ăэ��݂��撣��܂����B���w�N�̎q�ǂ��������₳�������������Ȃ���i�s�����[�h����p�́A�S�������������Ȃ�܂����B�݂�Ȃł��X�����y�����A��萋����B�����𖡂키���Ƃ��ł��܂����B
�@�ی�҂̕��X�������Q�����Ă�������A�q�ǂ������̗�݂ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B�@












�@���N�x�́u�����q�ǂ��܂�v�ł́A���̎��݂Ƃ��āA�c����ǂ��Ƃ̂��X���o�i���܂����B�w�N�����يw�N�𗬂̒��ŁA�q�ǂ������͗͂����킹�Ċ��E�����E�^�c�Ɏ��g�݂܂����B
�@�u�o�C�L���}�������Ă�I���傭�ς�܂�V���[�e�B���O�v�u���҂��݂�̂킭�킭��Ȃ��v�u�s�N�~������s�N�~���t�B�b�V���O�v�u�M���M���Ŏ~�߂납�`�L���[�X�v�u�o�C�L���}���ɏ��āA��Q�������[�v�u�ԃs�N�~���������v…�ǂ̂��X�ɂ����ꂼ��̔ǂ́u�A�C�f�B�A�v�Ɓu�H�v�v���l�܂��Ă��āA���ꂵ�����q������Ί炢���ς��ł����B�u�X�y�V�����V���b�v�r�搶�v�́A�R�O�b�Ԃłǂꂾ���J�E���^�[�������邩�Ƃ����搶���ŏ��o�X�ł��B���X�����Ȃ���A�Í��X�^���v�����[������A�y�����{���ł����B
�@��w�N�̎q�ǂ���������t���s���A���w�N�̎q�ǂ������͐�`�̌Ăэ��݂��撣��܂����B���w�N�̎q�ǂ��������₳�������������Ȃ���i�s�����[�h����p�́A�S�������������Ȃ�܂����B�݂�Ȃł��X�����y�����A��萋����B�����𖡂키���Ƃ��ł��܂����B
�@�ی�҂̕��X�������Q�����Ă�������A�q�ǂ������̗�݂ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B�@
�V���P�O���i�j�������̓��E�������ǂ��܂�̏���
�@����O�ɂ́A�����ȏ�ɓ��₩�Ȑ��������n���Ă��܂����B�����P�O���́u�������̓��v�ł��B�����͑�䐼���w�Z�̐��k����A�����āA�����ψ�����ƈꏏ�ɁA�S�Z�Łu�������^���v���s���܂����B���C�ȁu���͂悤�������܂��v�̐��ɓo�Z���Ă�����q�������̕\������R�Ɩ��邭�Ȃ�܂��B���w���̊F�����悵�Đ��������Ă����p�ɁA���w������������̂܂Ȃ����������Ă��܂����B�n��̕��X�Ǝq�����������킷�Ί�́A�܂��Ɂu�S�̂Ȃ���v��������ЂƂƂ��ł����B�A��ۂɁA�������̑��Ɛ�����u�T�}�[�X�N�[���Q���ԂƂ��s���܂��I�v�Ƙb���Ă���܂����B�����������Ɛ��ł����B
�@���x�݂���T���Ԗڂɂ����āA�����J�Â���u�����q�ǂ��܂�v�̏������s���܂����B���N�x����c���芈���̂��X���o���܂��B�������S��������A���n�[�T����������ƁA�O���[�v���Ƃɂ��ꂼ����g�݂܂����B�U�N���̃��[�_�[�V�b�v�������Ă��܂����B�����͕ی�҂̕��X�ɂ����J�ł��̂��A���Ђ��z�����������܂��悤�A���肢���܂��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@����O�ɂ́A�����ȏ�ɓ��₩�Ȑ��������n���Ă��܂����B�����P�O���́u�������̓��v�ł��B�����͑�䐼���w�Z�̐��k����A�����āA�����ψ�����ƈꏏ�ɁA�S�Z�Łu�������^���v���s���܂����B���C�ȁu���͂悤�������܂��v�̐��ɓo�Z���Ă�����q�������̕\������R�Ɩ��邭�Ȃ�܂��B���w���̊F�����悵�Đ��������Ă����p�ɁA���w������������̂܂Ȃ����������Ă��܂����B�n��̕��X�Ǝq�����������킷�Ί�́A�܂��Ɂu�S�̂Ȃ���v��������ЂƂƂ��ł����B�A��ۂɁA�������̑��Ɛ�����u�T�}�[�X�N�[���Q���ԂƂ��s���܂��I�v�Ƙb���Ă���܂����B�����������Ɛ��ł����B
�@���x�݂���T���Ԗڂɂ����āA�����J�Â���u�����q�ǂ��܂�v�̏������s���܂����B���N�x����c���芈���̂��X���o���܂��B�������S��������A���n�[�T����������ƁA�O���[�v���Ƃɂ��ꂼ����g�݂܂����B�U�N���̃��[�_�[�V�b�v�������Ă��܂����B�����͕ی�҂̕��X�ɂ����J�ł��̂��A���Ђ��z�����������܂��悤�A���肢���܂��B
�V���X���i���j�S�����悤�A���������Ȏ��ԁ@�`�x���Ќ𗬁`
�@�����͎x���Ќ𗬂̈�Ƃ��āA����������ʎx���w�Z�ɒʂ��Ă���Q�N���̎q���������A�{�Z�̂Q�N���̎q�������ƌ𗬂��܂����B��N�x���𗬂��Ă���̂ŁA�q�������́A�u�Z�Z���I�v�Ɗo���Ă��܂����B�{�[���̓������������Ă�������A�ꏏ�ɍ����l������A�h�b�W�{�[���ł́A�Z�Z����A�������[����݂�����ƁA�y���������ł��郋�[�����m�F���܂����B�����ƈꏏ�Ɏ���Ȃ��Ŋ��Y���Ă������Ă����Ă����p�A�{�[���������Ɠn���Ă�����p�A�q�����������̈�N�Œz���Ă����W���ƐS�̐��������������邱�Ƃ��ł��܂����B�A��ۂɂ́A�u�܂����Ăˁv�ƕʂ��ɂ��݁A�ĉ��������Ă��܂����B
�@�x���Ќ𗬂́A�q�������ɂƂ��āu�������𗝉����A�Ƃ��ɉ߂�����сv���w�ԑ�Ȏ��Ԃł��B���ꂩ����݂��Ɋw�э����A�炿�������������ȂȂ�����ɂ������ł��B�Q�w�����x���Ќ𗬂͑����܂��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�����͎x���Ќ𗬂̈�Ƃ��āA����������ʎx���w�Z�ɒʂ��Ă���Q�N���̎q���������A�{�Z�̂Q�N���̎q�������ƌ𗬂��܂����B��N�x���𗬂��Ă���̂ŁA�q�������́A�u�Z�Z���I�v�Ɗo���Ă��܂����B�{�[���̓������������Ă�������A�ꏏ�ɍ����l������A�h�b�W�{�[���ł́A�Z�Z����A�������[����݂�����ƁA�y���������ł��郋�[�����m�F���܂����B�����ƈꏏ�Ɏ���Ȃ��Ŋ��Y���Ă������Ă����Ă����p�A�{�[���������Ɠn���Ă�����p�A�q�����������̈�N�Œz���Ă����W���ƐS�̐��������������邱�Ƃ��ł��܂����B�A��ۂɂ́A�u�܂����Ăˁv�ƕʂ��ɂ��݁A�ĉ��������Ă��܂����B
�@�x���Ќ𗬂́A�q�������ɂƂ��āu�������𗝉����A�Ƃ��ɉ߂�����сv���w�ԑ�Ȏ��Ԃł��B���ꂩ����݂��Ɋw�э����A�炿�������������ȂȂ�����ɂ������ł��B�Q�w�����x���Ќ𗬂͑����܂��B
�V���W���i�j�@���V��
�@�P�N���̐����Ȃ̊w�K�Ő��V�т��y���݂܂����B�y�b�g�{�g���ŃA�T�K�I�ɐ�����������A���S�C�ŗV��A�S�_�ɂ邵������̓I�ɐ��S�C�Ő��Ă���ƁA�q�ǂ������͐��ɔG��Ȃ�����y���������Ɏ��g��ł��܂����B�A�T�K�I�̉Ԃ��i���ĐF��������āA�u�Z���搶�A���ā`�I�v�����ꂢ�ȐF���������Ă���܂����B���̗₽���⊴�G�A���z�̌��ɂ���߂��l�q�ȂǁA�܊���ʂ��Ċy���݂܂����B�u�������܂Ŕ��ł����`�v�u���������`�v�Ɗ����������Ȃ���A�F�B�Ƌ��͂�����V�肷��p����́A�w�тƗV�т���̂ƂȂ����L���Ȏ��Ԃ��������܂����B�ĂȂ�ł͂̊w�т��ɂ������ł��B






�@�P�N���̐����Ȃ̊w�K�Ő��V�т��y���݂܂����B�y�b�g�{�g���ŃA�T�K�I�ɐ�����������A���S�C�ŗV��A�S�_�ɂ邵������̓I�ɐ��S�C�Ő��Ă���ƁA�q�ǂ������͐��ɔG��Ȃ�����y���������Ɏ��g��ł��܂����B�A�T�K�I�̉Ԃ��i���ĐF��������āA�u�Z���搶�A���ā`�I�v�����ꂢ�ȐF���������Ă���܂����B���̗₽���⊴�G�A���z�̌��ɂ���߂��l�q�ȂǁA�܊���ʂ��Ċy���݂܂����B�u�������܂Ŕ��ł����`�v�u���������`�v�Ɗ����������Ȃ���A�F�B�Ƌ��͂�����V�肷��p����́A�w�тƗV�т���̂ƂȂ����L���Ȏ��Ԃ��������܂����B�ĂȂ�ł͂̊w�т��ɂ������ł��B
�V���V���i���j�ɂ���łЂ낪����̂�����E���_�J�̐Ԃ����E�Z�����C
�@�R�N�P�g�̐}�H�ł��B���̂ɂ��݂������\�������Ɏ��g�݂܂����B�����N�������ŕ`�������̒��ɁA�����܂܂����M�Ő����܂�����A�����ɐF���̂��Ă����܂��B�F���ɂ��݁A�v�������Ȃ��`��F�̂Ђ낪�肪���܂�܂��B�q�ǂ������́A���R�ł����͗l���y���݁A�F�Ƃ�ǂ�̂��Ă��ȍ�i�Ɏd�グ�Ă��܂����B
�@�T�N���͗��Ȃ̊w�K�Łu���_�J�v����ĂĂ��܂��B��������̐Ԃ�����܂�A�傫�����Ƃ̐����ɕ����Ď����Ă��܂��B�x�ݎ��Ԃ��C�ɂȂ�A�����b�����Ă���Ă��܂��B
�@���́A�Q�N�O�̂T�N�����炢�����������_�J���P�C�����Ă��܂��B���N�̂T�N������T�C���������������������ƂɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��B
�@�Z�����C�ł́u����v���������Ă��܂��B��N�x�Ɉ��������A�����w�@��w���C�����̋g�c�搶���w���҂Ƃ��ď��ق��A�u�����v�w���ɂ��āA���u�`�����������܂����B�u�����͂͏������Ƃɂ���Ă����g�ɂ��Ȃ��v�Ƃ�����̓I�Ȏ��H��������������Ă��������܂����B�s���ς̎w���厖�̐搶�����̗l�q�������ɂȂ��Ă��܂����B�{�Z�̐E���̑O�����Ȋw�Ԏp���ɋg�c�搶�A�w���厖�̐搶�����J�߂Ă��������܂����B�q�ǂ������ɂƂ��āA���悢�����ڎw���āA������l��l���w�ё�����p�����ɂ��Ă����܂��B�g�c�搶�ɂ͂Q�w���ɂ��������Ƃ̂��w���ł����b�ɂȂ�܂��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�R�N�P�g�̐}�H�ł��B���̂ɂ��݂������\�������Ɏ��g�݂܂����B�����N�������ŕ`�������̒��ɁA�����܂܂����M�Ő����܂�����A�����ɐF���̂��Ă����܂��B�F���ɂ��݁A�v�������Ȃ��`��F�̂Ђ낪�肪���܂�܂��B�q�ǂ������́A���R�ł����͗l���y���݁A�F�Ƃ�ǂ�̂��Ă��ȍ�i�Ɏd�グ�Ă��܂����B
�@�T�N���͗��Ȃ̊w�K�Łu���_�J�v����ĂĂ��܂��B��������̐Ԃ�����܂�A�傫�����Ƃ̐����ɕ����Ď����Ă��܂��B�x�ݎ��Ԃ��C�ɂȂ�A�����b�����Ă���Ă��܂��B
�@���́A�Q�N�O�̂T�N�����炢�����������_�J���P�C�����Ă��܂��B���N�̂T�N������T�C���������������������ƂɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��B
�@�Z�����C�ł́u����v���������Ă��܂��B��N�x�Ɉ��������A�����w�@��w���C�����̋g�c�搶���w���҂Ƃ��ď��ق��A�u�����v�w���ɂ��āA���u�`�����������܂����B�u�����͂͏������Ƃɂ���Ă����g�ɂ��Ȃ��v�Ƃ�����̓I�Ȏ��H��������������Ă��������܂����B�s���ς̎w���厖�̐搶�����̗l�q�������ɂȂ��Ă��܂����B�{�Z�̐E���̑O�����Ȋw�Ԏp���ɋg�c�搶�A�w���厖�̐搶�����J�߂Ă��������܂����B�q�ǂ������ɂƂ��āA���悢�����ڎw���āA������l��l���w�ё�����p�����ɂ��Ă����܂��B�g�c�搶�ɂ͂Q�w���ɂ��������Ƃ̂��w���ł����b�ɂȂ�܂��B
�V���S���i���j�@�}�b�g�^���E�v���O���~���O�w�K�i�S��ځj�E��������̐�
�@�P�N���̑̈�u�}�b�g���������^���V�сv�ł��B�w�����܂�߂đ̂���炷�u��肩���v�A��̂Ђ���}�b�g�ɂ��ĂāA�s���Ƒ����̂��u�A���e�i�v�A�ܐ��L���đ̂��܂������ɂ��Ă܂��u�ۑ����낪��v���A���̂������K���Ă��܂����B�u���ɂł��Ă�̂ŁA�ʐ^�B���Ă��������I�v�Ƃ��낢��ȃO���[�v���烊�N�G�X�g������܂����B�݂�Ȋ撣���Ă��܂��B
�@�R�N���̃v���O���~���O�w�K�́A�S��ڂɂȂ�܂����B���H�������Ƃ�����Ă��܂����A�����ԑ���ɂȂ�Ă��܂����B���T�͂��悢��ŏI��ɂȂ�܂��B�������A�s���ς̉|�{�搶�A�k���搶�A�{�����e�B�A�̊F����ɂ����b�ɂȂ�܂����B�ǂ�ȃR�[�X�̖��H���������邩�y���݂ł��B
�@�S�N�Q�g�ɋ����ɂ���z���C�g�{�[�h�ɂ́A�u�������ʼn̂��邩��A�T���Ԗڂ̉��y���y���݁v�Ə�����Ă��܂����B�����������̉̐����ɍs���ƁA�m���ɓ������̂���̐��������Ă��܂����B���Ă��ł����B
 �@
�@
 �@
�@
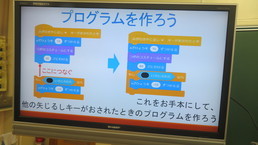 �@
�@
 �@
�@
�@�P�N���̑̈�u�}�b�g���������^���V�сv�ł��B�w�����܂�߂đ̂���炷�u��肩���v�A��̂Ђ���}�b�g�ɂ��ĂāA�s���Ƒ����̂��u�A���e�i�v�A�ܐ��L���đ̂��܂������ɂ��Ă܂��u�ۑ����낪��v���A���̂������K���Ă��܂����B�u���ɂł��Ă�̂ŁA�ʐ^�B���Ă��������I�v�Ƃ��낢��ȃO���[�v���烊�N�G�X�g������܂����B�݂�Ȋ撣���Ă��܂��B
�@�R�N���̃v���O���~���O�w�K�́A�S��ڂɂȂ�܂����B���H�������Ƃ�����Ă��܂����A�����ԑ���ɂȂ�Ă��܂����B���T�͂��悢��ŏI��ɂȂ�܂��B�������A�s���ς̉|�{�搶�A�k���搶�A�{�����e�B�A�̊F����ɂ����b�ɂȂ�܂����B�ǂ�ȃR�[�X�̖��H���������邩�y���݂ł��B
�@�S�N�Q�g�ɋ����ɂ���z���C�g�{�[�h�ɂ́A�u�������ʼn̂��邩��A�T���Ԗڂ̉��y���y���݁v�Ə�����Ă��܂����B�����������̉̐����ɍs���ƁA�m���ɓ������̂���̐��������Ă��܂����B���Ă��ł����B
�V���R���i�j�N�������A�p�X�ł�����h�ECan you�`�H�E�Z�O�w�K�i���Z���^�[�j
�@�Q�N���̐}�H�ł��B�N���������y�[�p�[�ŎC���Ăڂ�������A�ܗk�}�ō������Ɨl�X�ȕ��@�ŕ\�����܂����B�g������ς��邱�ƂŁA���͋C���K�����ƕς�邱�Ƃ��킩��܂��B�F���ӂ���ƍL����ƁA�u�����`�I�v�Ɓu�������낢�I�v�ȂǁA�ƂĂ��y�������Ɋ������邱�Ƃ��ł��܂����B�G�ɐ[�݂�����������i������Ă��܂����B
�@�T�N���̊O����ł��BI can�`. Can you�`�H�̉p��\�����g���ėF�B��g�߂Ȑl�ɂł��邱�ƁA�ł��Ȃ����Ƃ�q�ˁA���e���������A���݂��̂ł��邱�ƁA�ł��Ȃ����Ƃ�`���������肵�Ă��܂����B�������Ԃɓ���Ă��炢�A�q�ǂ������ƈꏏ�ɉp��ʼn�b���܂����B���̒��ŁA�����K���Ă�����A�_���X���K���Ă�����ƐV���Ȉ�ʂ��������A��b���L����܂����B
�@�S�N���͎Љ�Ȃ̊w�K�̈�Ƃ��āA���Z���^�[�����w���܂����B�����������X�o���S�~���ǂ̂悤�ɏ�������A���T�C�N������Ă���ɂ������ۂɌ��邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A�S�~���W�Ԃ̂����݂����ۂɌ����Ă��炢�܂����B�^�ꂽ�S�~������ȃN���[���ł͎����グ����Ƃ���A�ċp�F�̔M�𗘗p���Ĕ��d���Ă���d�g�݂ɖڂ��P�����Ă��܂����B�E���̕��X����́A�u�S�~�����炷���߂ɂł��邱�Ɓv�u���ʂ̑���v�u������邽�߂̍H�v�v�ɂ��āA�킩��₷�������Ă��������܂����B�q�ǂ������������������̎��₪����A�q�ǂ������Ȃ�̋C�Â���ӗ~���������܂�܂����B���w��A�S�~���o���O�ɂ�����x�l���邱�ƁA���T�C�N���ɂ��Ď��H����q�ǂ������ł����Ăق����Ǝv���܂����B���Z���^�[�̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�Q�N���̐}�H�ł��B�N���������y�[�p�[�ŎC���Ăڂ�������A�ܗk�}�ō������Ɨl�X�ȕ��@�ŕ\�����܂����B�g������ς��邱�ƂŁA���͋C���K�����ƕς�邱�Ƃ��킩��܂��B�F���ӂ���ƍL����ƁA�u�����`�I�v�Ɓu�������낢�I�v�ȂǁA�ƂĂ��y�������Ɋ������邱�Ƃ��ł��܂����B�G�ɐ[�݂�����������i������Ă��܂����B
�@�T�N���̊O����ł��BI can�`. Can you�`�H�̉p��\�����g���ėF�B��g�߂Ȑl�ɂł��邱�ƁA�ł��Ȃ����Ƃ�q�ˁA���e���������A���݂��̂ł��邱�ƁA�ł��Ȃ����Ƃ�`���������肵�Ă��܂����B�������Ԃɓ���Ă��炢�A�q�ǂ������ƈꏏ�ɉp��ʼn�b���܂����B���̒��ŁA�����K���Ă�����A�_���X���K���Ă�����ƐV���Ȉ�ʂ��������A��b���L����܂����B
�@�S�N���͎Љ�Ȃ̊w�K�̈�Ƃ��āA���Z���^�[�����w���܂����B�����������X�o���S�~���ǂ̂悤�ɏ�������A���T�C�N������Ă���ɂ������ۂɌ��邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A�S�~���W�Ԃ̂����݂����ۂɌ����Ă��炢�܂����B�^�ꂽ�S�~������ȃN���[���ł͎����グ����Ƃ���A�ċp�F�̔M�𗘗p���Ĕ��d���Ă���d�g�݂ɖڂ��P�����Ă��܂����B�E���̕��X����́A�u�S�~�����炷���߂ɂł��邱�Ɓv�u���ʂ̑���v�u������邽�߂̍H�v�v�ɂ��āA�킩��₷�������Ă��������܂����B�q�ǂ������������������̎��₪����A�q�ǂ������Ȃ�̋C�Â���ӗ~���������܂�܂����B���w��A�S�~���o���O�ɂ�����x�l���邱�ƁA���T�C�N���ɂ��Ď��H����q�ǂ������ł����Ăق����Ǝv���܂����B���Z���^�[�̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B
�V���Q���i���j�q�i�̎p�E�^�u���b�g�ɏW���E���[������
�@�c�o���̃q�i���p�������܂����B�����Ă݂�ƂT�H���܂��B�q�ǂ������́u�V�H����`�v�ƌ����Ă��܂����A�ق�Ƃ��ǂ����肩�ł͂���܂���B�e��������Ɣ�������傫���J���āA�������˂���l�q�͂Ȃ�Ƃ����킢���ł��B�����ɑ����悤�ɖ���������Ă��܂��B
�@��������Ȃ��Ǝv���قǁA�Q�N���̋����ł́A�^�u���b�g�[����e���C�u�����ɏW�����Ď��g��ł��܂����B�g�����Ɋ���Ă���̂ŁA�ǂ�ǂ�i��ł��܂��B
�@���w���ł́A���[�Ɍ����Ă��ꂼ�ꂪ����������܂����B�����͂���������s���܂����B����P�ƂЂ����̂��킢�炵������̍�i���������܂����B
 �@
�@
 �@
�@

�@�c�o���̃q�i���p�������܂����B�����Ă݂�ƂT�H���܂��B�q�ǂ������́u�V�H����`�v�ƌ����Ă��܂����A�ق�Ƃ��ǂ����肩�ł͂���܂���B�e��������Ɣ�������傫���J���āA�������˂���l�q�͂Ȃ�Ƃ����킢���ł��B�����ɑ����悤�ɖ���������Ă��܂��B
�@��������Ȃ��Ǝv���قǁA�Q�N���̋����ł́A�^�u���b�g�[����e���C�u�����ɏW�����Ď��g��ł��܂����B�g�����Ɋ���Ă���̂ŁA�ǂ�ǂ�i��ł��܂��B
�@���w���ł́A���[�Ɍ����Ă��ꂼ�ꂪ����������܂����B�����͂���������s���܂����B����P�ƂЂ����̂��킢�炵������̍�i���������܂����B
�V���P���i�j�C�w���s�@�Q����
�@�Q���ڂ̒��A�S�����C�Ō}���܂����B�����͂�A������������q�����������܂��B���炵���H�~�ł��B�h���{�݂̑�����A�����߂��ɃV�J�������т�H�ׂĂ��܂����B
�@�Q���Ԃ����b�ɂȂ����h���{�݂̕��ɁA���s�ψ�����̃X���[�Y�Ȏi��ɑ����āA���ӂ̋C���������߂Ĉ��A�����܂����B�ǂ̕������������A�ŏI�`�F�b�N�͈ꔭ���i�ł��B
�@���Ƌ{�ɓ�������ƁA�v�������ό��q�⑼�Z�����Ȃ������̂ŁA�����ɓ��ꂪ�ł��܂����B�����āA�z������o�b�N�Ɏʐ^�B�e���ł��܂����B�O���[�v���Ƃ̍s���ǂɕ�����Ă̊ό��ł��B�ƍN�̕�܂ł̊K�i�̐����A�N�C�Y�ɓ����Ȃ���A���w�����܂����B�r���A�`���b�N�|�C���g�ɂ͐E�������āA�T�C�������炢�܂����B�q�a�ł́A�喼�ɂȂ�������ŁA���Q��������Ă��������܂����B
�@�v�������A�Z�����Ԃł��ׂĉ�邱�Ƃ��ł������Ƃ���A�\��ύX�ŁA���H�̑O�ɕx�m���ό��Z���^�[�Ŕ����������܂����B�v��I�ɂ��y�Y�����̂�������ɋL�����Ă���q�����܂����B�R�O�O�O�~�҂�����̔��������Ă���q�����ċ����܂����B
�@���̂Q���ԁA�q�������́A�u���Ԃ����v�u�W�c�ōs������v�u���ӂ̋C���������v�Ƃ������A�w�Z�ő�ɂ��Ă��邱�Ƃ���������Ǝ��H���Ă���܂����B�o�X�̒��ł̉߂������A�h�̕��ւ̈��A�A�搶���ւ̋C�z�蓙�A�v�����̎p�������Ɍ����A���������q�������𗊂������v���܂����B
�@�ی�҂̊F�l�ɂ�����܂��ẮA������̒��Ǘ����A�����̂����͂����肪�Ƃ��������܂����B�x���Ă�������F����̂������ŁA�q�������͑傫�Ȍo���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@���̂Q���ԁA�S�������C�ŃP�K�⎖�̂��Ȃ��߂��Ă��Ă��ꂽ���ƁA����肤�ꂵ���������Ƃł��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�Q���ڂ̒��A�S�����C�Ō}���܂����B�����͂�A������������q�����������܂��B���炵���H�~�ł��B�h���{�݂̑�����A�����߂��ɃV�J�������т�H�ׂĂ��܂����B
�@�Q���Ԃ����b�ɂȂ����h���{�݂̕��ɁA���s�ψ�����̃X���[�Y�Ȏi��ɑ����āA���ӂ̋C���������߂Ĉ��A�����܂����B�ǂ̕������������A�ŏI�`�F�b�N�͈ꔭ���i�ł��B
�@���Ƌ{�ɓ�������ƁA�v�������ό��q�⑼�Z�����Ȃ������̂ŁA�����ɓ��ꂪ�ł��܂����B�����āA�z������o�b�N�Ɏʐ^�B�e���ł��܂����B�O���[�v���Ƃ̍s���ǂɕ�����Ă̊ό��ł��B�ƍN�̕�܂ł̊K�i�̐����A�N�C�Y�ɓ����Ȃ���A���w�����܂����B�r���A�`���b�N�|�C���g�ɂ͐E�������āA�T�C�������炢�܂����B�q�a�ł́A�喼�ɂȂ�������ŁA���Q��������Ă��������܂����B
�@�v�������A�Z�����Ԃł��ׂĉ�邱�Ƃ��ł������Ƃ���A�\��ύX�ŁA���H�̑O�ɕx�m���ό��Z���^�[�Ŕ����������܂����B�v��I�ɂ��y�Y�����̂�������ɋL�����Ă���q�����܂����B�R�O�O�O�~�҂�����̔��������Ă���q�����ċ����܂����B
�@���̂Q���ԁA�q�������́A�u���Ԃ����v�u�W�c�ōs������v�u���ӂ̋C���������v�Ƃ������A�w�Z�ő�ɂ��Ă��邱�Ƃ���������Ǝ��H���Ă���܂����B�o�X�̒��ł̉߂������A�h�̕��ւ̈��A�A�搶���ւ̋C�z�蓙�A�v�����̎p�������Ɍ����A���������q�������𗊂������v���܂����B
�@�ی�҂̊F�l�ɂ�����܂��ẮA������̒��Ǘ����A�����̂����͂����肪�Ƃ��������܂����B�x���Ă�������F����̂������ŁA�q�������͑傫�Ȍo���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@���̂Q���ԁA�S�������C�ŃP�K�⎖�̂��Ȃ��߂��Ă��Ă��ꂽ���ƁA����肤�ꂵ���������Ƃł��B
�U���R�O���i���j�C�w���s�@�P����
�@�U�N�����҂��ɑ҂����C�w���s�ɑS���Q���ŏo�����܂����B�s��́A���j�Ǝ��R�����a����Ȗ،������ł��B���������Ƃ��ĎQ�������Ă��������܂����B�o�X���N�̎q�ǂ��������A���������Ă����o�����ŁA�����͂������Ƃ����ԂɌ��n�ɒ����܂����B�̒��s�ǂɂȂ�q�͂��܂���B
�@�P���ڂ͉،��̑�ƒ��P����K��A���R�̔��͂ɖڂ�D���܂����B�O���̉J�̉e���ł��傤���A�،��̑�̐��ʂ𑽂��ɋ����܂����B�����Ԃ����A���w�̂Ƃ낱�܂���������łł��܂����B�����̉��ł́A�J���[�̐H�ו���ɁA�قƂ�ǂ̎q�������������������܂����B
�@�j�̎R��w�i�ɐ�ꃖ���̃n�C�L���O���s���܂����B�O���[�v���Ƃɏo���ł��B����܂ł́A�Q���Ԃ����ĕ����܂����B�o���ʂ̕��X�ɂ́u����ɂ��́`�v�ƈ��A�����킵�܂����B�r���A�T���ɂ��o��܂����B���ꂩ��́A�S���œ��̌̎��������A����܂ŕ����܂����B����ł͂P�O�~�ʂ����A�����̗͂ł݂�݂�F���ς��܂����B����ɃV�J�ɂ��������A�q�������͑勻���B���َ����ς܂��A�������ƂɃJ�[�h�Q�[�����Ő���オ��܂����B�u�ꏏ�ɂ��܂��傤�v�Ǝq����������U���A�y�����Q�[���̎Q�����܂����B�[�H�������������������A�ЂÂ����������ł��B�̒��s�ǂ��Ȃ��A�P���ڂ��I���܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�U�N�����҂��ɑ҂����C�w���s�ɑS���Q���ŏo�����܂����B�s��́A���j�Ǝ��R�����a����Ȗ،������ł��B���������Ƃ��ĎQ�������Ă��������܂����B�o�X���N�̎q�ǂ��������A���������Ă����o�����ŁA�����͂������Ƃ����ԂɌ��n�ɒ����܂����B�̒��s�ǂɂȂ�q�͂��܂���B
�@�P���ڂ͉،��̑�ƒ��P����K��A���R�̔��͂ɖڂ�D���܂����B�O���̉J�̉e���ł��傤���A�،��̑�̐��ʂ𑽂��ɋ����܂����B�����Ԃ����A���w�̂Ƃ낱�܂���������łł��܂����B�����̉��ł́A�J���[�̐H�ו���ɁA�قƂ�ǂ̎q�������������������܂����B
�@�j�̎R��w�i�ɐ�ꃖ���̃n�C�L���O���s���܂����B�O���[�v���Ƃɏo���ł��B����܂ł́A�Q���Ԃ����ĕ����܂����B�o���ʂ̕��X�ɂ́u����ɂ��́`�v�ƈ��A�����킵�܂����B�r���A�T���ɂ��o��܂����B���ꂩ��́A�S���œ��̌̎��������A����܂ŕ����܂����B����ł͂P�O�~�ʂ����A�����̗͂ł݂�݂�F���ς��܂����B����ɃV�J�ɂ��������A�q�������͑勻���B���َ����ς܂��A�������ƂɃJ�[�h�Q�[�����Ő���オ��܂����B�u�ꏏ�ɂ��܂��傤�v�Ǝq����������U���A�y�����Q�[���̎Q�����܂����B�[�H�������������������A�ЂÂ����������ł��B�̒��s�ǂ��Ȃ��A�P���ڂ��I���܂����B
�U���Q�V���i���j �w�Z�w���K��
�@���E�s����ψ���̕��X���ۂP���K�₳��܂����B���̖K��́A����̎��̌����ړI�Ƃ��āA�w�Z�̋��犈���S�ʂ�_���A��������2�N��1��̑�ȋ@��ł��B�K��ł́A���E�s���ςƍZ���A�����Ɗw�Z�o�c�̘b�������A���E���̎w���̐��⋳���ł̎��Ƃ̗l�q��A�q�ǂ����������̊������������������܂����B���Ƃł́A�S�w�N�^�u���b�g�[�����g�p�������e��W�J���Ă��܂����B����ψ���̕��X����́A���������̐ϋɓI�Ȋw�т̎p����A���t�̔M�S�Ȏw���ɑ��ĕ]�������������܂����B�܂��A�w�Z�̎{�݂���ɂ��Ă��A�����Ő�������Ă���Ƃ̂��J�߂̌��t�����������܂����B
�@�����ɂ͖{�s���璷�@���q�F�l���A6�N���ƈꏏ�ɋ��H�������オ��܂����B�q�ǂ������ɂƂ��ċ��璷�l�ƐG�ꍇ�������Ƃ͂����Ƃ悢�v���o�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B
�@����̖K���ʂ��āA�{�Z�̋��犈�����q�ϓI�ɐU��Ԃ�M�d�ȋ@��ƂȂ�܂����B������q�ǂ�������l��l���u�ЂƂ݂����₭���������Ȋw�Z�v��ڎw���āA���E���ꓯ�w�߂Ă܂���܂��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@���E�s����ψ���̕��X���ۂP���K�₳��܂����B���̖K��́A����̎��̌����ړI�Ƃ��āA�w�Z�̋��犈���S�ʂ�_���A��������2�N��1��̑�ȋ@��ł��B�K��ł́A���E�s���ςƍZ���A�����Ɗw�Z�o�c�̘b�������A���E���̎w���̐��⋳���ł̎��Ƃ̗l�q��A�q�ǂ����������̊������������������܂����B���Ƃł́A�S�w�N�^�u���b�g�[�����g�p�������e��W�J���Ă��܂����B����ψ���̕��X����́A���������̐ϋɓI�Ȋw�т̎p����A���t�̔M�S�Ȏw���ɑ��ĕ]�������������܂����B�܂��A�w�Z�̎{�݂���ɂ��Ă��A�����Ő�������Ă���Ƃ̂��J�߂̌��t�����������܂����B
�@�����ɂ͖{�s���璷�@���q�F�l���A6�N���ƈꏏ�ɋ��H�������オ��܂����B�q�ǂ������ɂƂ��ċ��璷�l�ƐG�ꍇ�������Ƃ͂����Ƃ悢�v���o�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B
�@����̖K���ʂ��āA�{�Z�̋��犈�����q�ϓI�ɐU��Ԃ�M�d�ȋ@��ƂȂ�܂����B������q�ǂ�������l��l���u�ЂƂ݂����₭���������Ȋw�Z�v��ڎw���āA���E���ꓯ�w�߂Ă܂���܂��B
�U���Q�U���i�j�@�F�Ƃ�ǂ�̃A�T�K�I�E�����A����
�@�P�N������Ɉ�ĂĂ���u�A�T�K�I�v�ł����A����͂T�̂��Ԃ��炢�Ă����̂ł����A�����͂�������炢�Ă��܂����B�Q�g�̎q�ǂ������́A�����Ȃ̎��ԂɃ^�u���b�g�ŎB�e���āA�ώ@�J�[�h�ɋL�^���邽�߂ɃX�N�[���^�N�g�ɃA�b�v���[�h���Ă��܂����B�u�B��܂����v�ƌ����Ă��ꂽK����B����ƁA�u�����v�u�ڂ����v�ƌ����ɗ��Ă���܂����B
�@�{�Z�ƎO�p���̐搶������䐼���w�Z�֖K�₵�A���k�����̎��Ƃ����w���܂����B���w�Z�̎��Ƃ̐i�ߕ���k�����̊w�K�ԓx�ڌ��邱�ƂŁA���w�Z�ł̎w���Ɋ�������M�d�Ȍo���ƂȂ�܂����B�܂��A���Ɛ��̐��������邱�Ƃ��ł��A���������v���܂����B���ƎQ�ό�́A�w�͌���A���k�w���A���瑊�k�A���ʎx������A�{��̂T�̕���ɕ�����āA�e�w�Z�̌���Ɖۑ�A�A�g���ׂ����e��b�������܂����B���N�x���T�}�[�X�N�[���A�������^���A������k��̃I�����C���𗬓��A�A�g�����Ă����܂��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�P�N������Ɉ�ĂĂ���u�A�T�K�I�v�ł����A����͂T�̂��Ԃ��炢�Ă����̂ł����A�����͂�������炢�Ă��܂����B�Q�g�̎q�ǂ������́A�����Ȃ̎��ԂɃ^�u���b�g�ŎB�e���āA�ώ@�J�[�h�ɋL�^���邽�߂ɃX�N�[���^�N�g�ɃA�b�v���[�h���Ă��܂����B�u�B��܂����v�ƌ����Ă��ꂽK����B����ƁA�u�����v�u�ڂ����v�ƌ����ɗ��Ă���܂����B
�@�{�Z�ƎO�p���̐搶������䐼���w�Z�֖K�₵�A���k�����̎��Ƃ����w���܂����B���w�Z�̎��Ƃ̐i�ߕ���k�����̊w�K�ԓx�ڌ��邱�ƂŁA���w�Z�ł̎w���Ɋ�������M�d�Ȍo���ƂȂ�܂����B�܂��A���Ɛ��̐��������邱�Ƃ��ł��A���������v���܂����B���ƎQ�ό�́A�w�͌���A���k�w���A���瑊�k�A���ʎx������A�{��̂T�̕���ɕ�����āA�e�w�Z�̌���Ɖۑ�A�A�g���ׂ����e��b�������܂����B���N�x���T�}�[�X�N�[���A�������^���A������k��̃I�����C���𗬓��A�A�g�����Ă����܂��B
�U���Q�T���i���j�A�T�K�I�������܂����E���ƎQ�ρi���w�N�j�E�q�i���a��
�@�u�Z�����`�I�A�T�K�I�������܂����`�I�v�ƁA�o�Z����1�N���������Ă���܂����B�u�ǂ�ǂ�H�v�ƃA�T�K�I�ɋ߂Â��ƐF�Ƃ�ǂ�̃A�T�K�I���炢�Ă��܂����B�u�Ԃ��Ȃ��Ă��邩��A�����炭����…�v�ƁA�ڂ݂������āA���ꂩ��炭�A�T�K�I���y���݂ɂ��Ă���P�N���̎q�������ł��B�J�̗\��ł����A�����ƍ炢�Ăق����Ƃ����v���ŁA�ꐶ�������������Ă��܂����B
�@�R�N���̂׃����ő��������Ă���c�o���ɁA�Ăуq�i�̒a��������܂����B���x�͑����痎���Ȃ��悤�ɂƋF�����ł��B��������y���݂��܂������܂����B
�@���ƎQ�ρi���w�N�j������܂����B�R�N���Q�g�͑̈�Ńv�����{�[�����s���܂����B�o�E���h����{�[�����ǂ��ɂƂԂ̂����킩��Ȃ��̂ŁA�\�z���Ȃ��瓮���Ă��܂����B���ԂƂƂ��Ɋw�э����p���������������Ă��邱�Ƃ��������܂����B���Ȃł́A�u���̗͂œ����ԁv�ǂ���������Ɖ����܂ŎԂ������̂����s���낵�Ă��܂����B�S�N���̎Z���ł́A�R�̃O���[�v�ɕ����āA�O�D�O�P��菬���Ȑ����ǂ��悤�ɂ�����悢���Ƃ����ۑ�Ɏ��g�݂܂����B����܂Ŋw��ł����m�����g���A�P�O�����ɕ����čl����悳�ɋC�Â��܂����B���Ƃ̕����Q�����Ă���N���X������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�u�Z�����`�I�A�T�K�I�������܂����`�I�v�ƁA�o�Z����1�N���������Ă���܂����B�u�ǂ�ǂ�H�v�ƃA�T�K�I�ɋ߂Â��ƐF�Ƃ�ǂ�̃A�T�K�I���炢�Ă��܂����B�u�Ԃ��Ȃ��Ă��邩��A�����炭����…�v�ƁA�ڂ݂������āA���ꂩ��炭�A�T�K�I���y���݂ɂ��Ă���P�N���̎q�������ł��B�J�̗\��ł����A�����ƍ炢�Ăق����Ƃ����v���ŁA�ꐶ�������������Ă��܂����B
�@�R�N���̂׃����ő��������Ă���c�o���ɁA�Ăуq�i�̒a��������܂����B���x�͑����痎���Ȃ��悤�ɂƋF�����ł��B��������y���݂��܂������܂����B
�@���ƎQ�ρi���w�N�j������܂����B�R�N���Q�g�͑̈�Ńv�����{�[�����s���܂����B�o�E���h����{�[�����ǂ��ɂƂԂ̂����킩��Ȃ��̂ŁA�\�z���Ȃ��瓮���Ă��܂����B���ԂƂƂ��Ɋw�э����p���������������Ă��邱�Ƃ��������܂����B���Ȃł́A�u���̗͂œ����ԁv�ǂ���������Ɖ����܂ŎԂ������̂����s���낵�Ă��܂����B�S�N���̎Z���ł́A�R�̃O���[�v�ɕ����āA�O�D�O�P��菬���Ȑ����ǂ��悤�ɂ�����悢���Ƃ����ۑ�Ɏ��g�݂܂����B����܂Ŋw��ł����m�����g���A�P�O�����ɕ����čl����悳�ɋC�Â��܂����B���Ƃ̕����Q�����Ă���N���X������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�U���Q�S���i�j���y����E���̂����E���ƎQ�ρi���w�N�j
�@�̂������Ƃ��܂��Ȃ邽�߂ɁA�܂䂰�������A�ڂ��ς�����A�قق��グ�āA�̂����Ƃ��|�C���g�ł��邱�Ƃ����y�S����H�搶����|�C���g�������Ă���܂����B�����������邽�߂ɁA�^�Ő��X�J�[�t�̒��ɐ�������悤�ɂ�������ӎ����Ă��܂����B�q�������̐������������������Ŋ����邱�Ƃ��ł��Ă��܂����B���̉��y����͂��Ă��ȉ̐��ɕ�܂�܂����B
�@�Q�N���̎Z���u���̂����v�ł��B1dl�̗ʂ͂ǂꂭ�炢�Ȃ̂��A���ۂɐ����g���đ̌����Ȃ���w�т܂����B�q�������́A�v�ʃJ�b�v�ɂP�����̐���������ƁA�v������菬�����Ƌ����ÁX�B����ɖ������H�ň���ł��鋍���͉������Ȃ̂��A�\�z�𗧂Ă܂����B�Q�C�R�A�T���k�ł��B���ۂɐ����g���ċ����p�b�N�ɐ��������}�X�Ŋm���߂�ƂQ�����ł��B�Q�����Ɨ\�z����2�N���͂�������đ��т��Ă��܂����B�A�g�̉��̂��낢��ȏ�ʂŁA�����̊w�K����������Ă������Ƃ����҂��Ă��܂��B
�@�T�C�U�N����ΏۂɁu�q�ǂ������u���v���s���܂����B�C���^�[�l�b�g��r�m�r���g�߂Ȏ���ł��B�q�����������S�A���S�̎g�������ł��܂��悤�A��ʌ����N�ۂ���l�b�g�A�h�o�C�U�[�ł���}���搶�ɂ��z�����������A�킩��₷�����H�I�Ȃ��b�����������܂����B����͕ی�҂̊F�l�ɂ����ƂɎQ�����Ă��������A�ƒ�Ɗw�Z���A�g���Ďq���������x���Ă�����������߂Ċ�����@��ƂȂ�܂����B���Ƃł́u�l�b�g�ɂ������ʐ^�⌾�t�͂ǂ��Ȃ�̂��v�u�Q�[����r�m�r�̏��Ȃ����������v�u�l���v���A�q������������I�ɒ�������e�[�}�����Ƃɍl����[�߁A���[�N�V�[�g�ɋL�q���Ȃ�����Ƃ��i�݂܂����B����̎��Ƃ́A�ċx�ݑO�ł����邱�ƁA��N�x�̊w�Z�ی��ψ���ŁA���N�x�̍��w�N�̏A�Q�������x�����ƁA�Q�[����X�}�z�����Ă��鎞�Ԃ��{�Z�͒����Ƃ����������ʂ���A����̎��ƂɎ���܂����B�e�ƒ�Řb�������A�b��ɂ��Ă��������A���������P�ł��邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@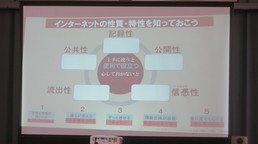
 �@
�@
�@�̂������Ƃ��܂��Ȃ邽�߂ɁA�܂䂰�������A�ڂ��ς�����A�قق��グ�āA�̂����Ƃ��|�C���g�ł��邱�Ƃ����y�S����H�搶����|�C���g�������Ă���܂����B�����������邽�߂ɁA�^�Ő��X�J�[�t�̒��ɐ�������悤�ɂ�������ӎ����Ă��܂����B�q�������̐������������������Ŋ����邱�Ƃ��ł��Ă��܂����B���̉��y����͂��Ă��ȉ̐��ɕ�܂�܂����B
�@�Q�N���̎Z���u���̂����v�ł��B1dl�̗ʂ͂ǂꂭ�炢�Ȃ̂��A���ۂɐ����g���đ̌����Ȃ���w�т܂����B�q�������́A�v�ʃJ�b�v�ɂP�����̐���������ƁA�v������菬�����Ƌ����ÁX�B����ɖ������H�ň���ł��鋍���͉������Ȃ̂��A�\�z�𗧂Ă܂����B�Q�C�R�A�T���k�ł��B���ۂɐ����g���ċ����p�b�N�ɐ��������}�X�Ŋm���߂�ƂQ�����ł��B�Q�����Ɨ\�z����2�N���͂�������đ��т��Ă��܂����B�A�g�̉��̂��낢��ȏ�ʂŁA�����̊w�K����������Ă������Ƃ����҂��Ă��܂��B
�@�T�C�U�N����ΏۂɁu�q�ǂ������u���v���s���܂����B�C���^�[�l�b�g��r�m�r���g�߂Ȏ���ł��B�q�����������S�A���S�̎g�������ł��܂��悤�A��ʌ����N�ۂ���l�b�g�A�h�o�C�U�[�ł���}���搶�ɂ��z�����������A�킩��₷�����H�I�Ȃ��b�����������܂����B����͕ی�҂̊F�l�ɂ����ƂɎQ�����Ă��������A�ƒ�Ɗw�Z���A�g���Ďq���������x���Ă�����������߂Ċ�����@��ƂȂ�܂����B���Ƃł́u�l�b�g�ɂ������ʐ^�⌾�t�͂ǂ��Ȃ�̂��v�u�Q�[����r�m�r�̏��Ȃ����������v�u�l���v���A�q������������I�ɒ�������e�[�}�����Ƃɍl����[�߁A���[�N�V�[�g�ɋL�q���Ȃ�����Ƃ��i�݂܂����B����̎��Ƃ́A�ċx�ݑO�ł����邱�ƁA��N�x�̊w�Z�ی��ψ���ŁA���N�x�̍��w�N�̏A�Q�������x�����ƁA�Q�[����X�}�z�����Ă��鎞�Ԃ��{�Z�͒����Ƃ����������ʂ���A����̎��ƂɎ���܂����B�e�ƒ�Řb�������A�b��ɂ��Ă��������A���������P�ł��邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�U���Q�R���i���j�Ă̂��ԂɃo�g���^�b�`�`�T�N���Ɗw�Z�����c�݂̂Ȃ���ƈꏏ�Ɂ`
�@�~�J�̐���Ԃ������Ă��܂��B�Ԓd�ł́A�S�������������Ȃ���i���L�����Ă��܂����B�����́A�T�N���ƒn��̕��X���͂����킹�āA�Ă̂��Ԃւ̐A���ւ���Ƃ��s���܂����B
�@����A�t�ɍ炫�ق����Ă����r�I�����u���肪�Ƃ��v�̋C���������߂Ĕ������A�y���x�߂Ă��܂����B�����́A�܂����Ԃ�A����O�ɓy���_�炩�����A�������܂����B���ԉ������F�Ƃ�ǂ�̃}���[�S�[���h�A�T���r�A�A�u���[�T���r�A�A�W�j�A�A�R���E�X���A�Ă����C�ɍʂ�ԁX��͂��Ă��������܂����B���ԉ�����A�����������Ă��������܂����B�A����O�ɂ́A�y���@��A�����ɐ��������Ղ����邻���ł��B���R�͏ォ�琅�������Ă����܂Ő����s���n��Ȃ����炾�����ł��B�������̕����ɂȂ�Ƃ���J�ɐ������Ă���A�A���܂����B�q����������̂Ђ�ł₳�����y���������āA�₳�����C�����ŐA���Ă���܂����B��T�Ԃ������Ƌ����Ă��������܂����B�������荪�����t���܂ŁA����肵�܂��B
�@�Ō�͐��������āA���ꂢ�ɍ炭�Ƃ����˂ƉԒd�������p�ɁA�S�������������Ȃ�܂����B
�@�����c�̊F�l�A�M�d�Ȏ��ԁA�����ĉ��������������肪�Ƃ��������܂����B






�@
�@�~�J�̐���Ԃ������Ă��܂��B�Ԓd�ł́A�S�������������Ȃ���i���L�����Ă��܂����B�����́A�T�N���ƒn��̕��X���͂����킹�āA�Ă̂��Ԃւ̐A���ւ���Ƃ��s���܂����B
�@����A�t�ɍ炫�ق����Ă����r�I�����u���肪�Ƃ��v�̋C���������߂Ĕ������A�y���x�߂Ă��܂����B�����́A�܂����Ԃ�A����O�ɓy���_�炩�����A�������܂����B���ԉ������F�Ƃ�ǂ�̃}���[�S�[���h�A�T���r�A�A�u���[�T���r�A�A�W�j�A�A�R���E�X���A�Ă����C�ɍʂ�ԁX��͂��Ă��������܂����B���ԉ�����A�����������Ă��������܂����B�A����O�ɂ́A�y���@��A�����ɐ��������Ղ����邻���ł��B���R�͏ォ�琅�������Ă����܂Ő����s���n��Ȃ����炾�����ł��B�������̕����ɂȂ�Ƃ���J�ɐ������Ă���A�A���܂����B�q����������̂Ђ�ł₳�����y���������āA�₳�����C�����ŐA���Ă���܂����B��T�Ԃ������Ƌ����Ă��������܂����B�������荪�����t���܂ŁA����肵�܂��B
�@�Ō�͐��������āA���ꂢ�ɍ炭�Ƃ����˂ƉԒd�������p�ɁA�S�������������Ȃ�܂����B
�@�����c�̊F�l�A�M�d�Ȏ��ԁA�����ĉ��������������肪�Ƃ��������܂����B
�@
�U���Q�Q���i���j�w������X�|�[�c�t�F�X�e�B�o��
�@�n��s���̈�ł���A�w������̃X�|�[�c�t�F�X�e�B�o�����A�{�Z�̑̈�قŊJ�Â���܂����B���Z�́u�{�b�`���v�ł��B�ӂ��ݖ�s�X�|�[�c���i���̕��X�����Z���A�u�{�b�`���v�̂�����������Ă��������܂����B�n��̕��X�̑��A�{�Z�����̂P�N���Q�����Q�����Ă��܂����B���یケ�ǂ������ł�������Ƃ�����悤�ŁA���[���͗������Ă��܂��B�P�N���̍ŏ��̓����ł́A�����Ȃ蔒���{�[���̋߂��ɐԃ{�[�����邷�炵�������ɋ����܂����B�N��ɊW�Ȃ��A�y�������S�ɃQ�[�����ł��܂����B
 �@
�@
 �@
�@
�@�n��s���̈�ł���A�w������̃X�|�[�c�t�F�X�e�B�o�����A�{�Z�̑̈�قŊJ�Â���܂����B���Z�́u�{�b�`���v�ł��B�ӂ��ݖ�s�X�|�[�c���i���̕��X�����Z���A�u�{�b�`���v�̂�����������Ă��������܂����B�n��̕��X�̑��A�{�Z�����̂P�N���Q�����Q�����Ă��܂����B���یケ�ǂ������ł�������Ƃ�����悤�ŁA���[���͗������Ă��܂��B�P�N���̍ŏ��̓����ł́A�����Ȃ蔒���{�[���̋߂��ɐԃ{�[�����邷�炵�������ɋ����܂����B�N��ɊW�Ȃ��A�y�������S�ɃQ�[�����ł��܂����B
�U���Q�O���i���j�v���O���~���O�w�K�E���ƎQ�ρi���w���j�E�������Ɋ���
�@3�N���̃v���O���~���O�w�K�́A�����łR��ڂł��B�X�N���b�`���g���āA���H�Q�[���̐���Ɏ��g�݂܂����B�}�E�X�̑���ɋ�J���܂������A����Ă��܂����B�L�����N�^�[�̃l�R��������A�ǂɂԂ���Ȃ��悤�ɋ���������ƁA��l��l�����s������d�˂Ȃ���A�v���O������g�ݗ��ĂĂ����܂����B�������A�s���ς�GiGA�X�N�[���劲�|�{�搶���A�{�����e�B�A�̕��X�ɂ����b�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�@���ƎQ�ςł́A���[�Ɍ����āu���Ȃ���������낤�v�Ƃ����������s���܂����B�S�C�ɘb���������蕷���A���ꂼ��̌�������f�G�ȏ�����d�グ�Ă����܂����B�肢�����t�ɂ��邱�ƁA���̌P���ƏW���͂̌���A�����Ƌ�������Ă鎞�ԁA�G�ߊ��╶���ւ̐e���ݓ��A������𐧍삷��[���Ӗ��̂��銈���ɂȂ�܂����B
�@�{�Z�ł́A�n��̊F�l�̂����͂̂��ƁA�w�тɊ������L���ɂȂ��Ă��܂��B�����́A�j���w�`�}�̕c�����C�Ɉ�悤�A�c������ɔ������߂̖Ԃ�ݒu���Ă��������܂����B���z�Ɍ������ăO���O���ƐL�тĂ������Ƃł��傤�B�܂��A�Z��ł͂g���A�Z��̑������s���Ă��������܂����B�������ł̍�Ƃɂ�������炸�A���J�ɋ��X�܂Ő����Ă�������A�q�ǂ����������S�ɗV�ׂ���������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
 �@
�@
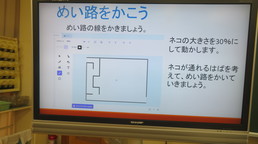
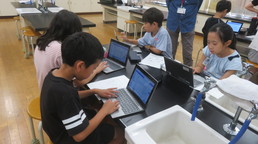




�@3�N���̃v���O���~���O�w�K�́A�����łR��ڂł��B�X�N���b�`���g���āA���H�Q�[���̐���Ɏ��g�݂܂����B�}�E�X�̑���ɋ�J���܂������A����Ă��܂����B�L�����N�^�[�̃l�R��������A�ǂɂԂ���Ȃ��悤�ɋ���������ƁA��l��l�����s������d�˂Ȃ���A�v���O������g�ݗ��ĂĂ����܂����B�������A�s���ς�GiGA�X�N�[���劲�|�{�搶���A�{�����e�B�A�̕��X�ɂ����b�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�@���ƎQ�ςł́A���[�Ɍ����āu���Ȃ���������낤�v�Ƃ����������s���܂����B�S�C�ɘb���������蕷���A���ꂼ��̌�������f�G�ȏ�����d�グ�Ă����܂����B�肢�����t�ɂ��邱�ƁA���̌P���ƏW���͂̌���A�����Ƌ�������Ă鎞�ԁA�G�ߊ��╶���ւ̐e���ݓ��A������𐧍삷��[���Ӗ��̂��銈���ɂȂ�܂����B
�@�{�Z�ł́A�n��̊F�l�̂����͂̂��ƁA�w�тɊ������L���ɂȂ��Ă��܂��B�����́A�j���w�`�}�̕c�����C�Ɉ�悤�A�c������ɔ������߂̖Ԃ�ݒu���Ă��������܂����B���z�Ɍ������ăO���O���ƐL�тĂ������Ƃł��傤�B�܂��A�Z��ł͂g���A�Z��̑������s���Ă��������܂����B�������ł̍�Ƃɂ�������炸�A���J�ɋ��X�܂Ő����Ă�������A�q�ǂ����������S�ɗV�ׂ���������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�U���P�X���i�j��̉ԁE���ƎQ��
�@4�N���̍���u��̉ԁv�̊w�K�ł��B�u��̉ԁv�́A�펞���̌��������ŁA�Ƒ��̈��ƁA���e�̐[���v�����@�ׂɕ`���ꂽ����ł��B�����́A�펞���Ɛ����r���A�ω���ǂݎ��܂����B��l���́u��݂��v�Ƃ���������A�H���A�R�X���X���̕\���̎d���ɂ��āA�O���[�v�Řb�������A���\���܂����B
�@�P�C�Q�N���̎��ƎQ�ς�����܂����B�Q�N���͓�N���X�Ƃ��A����u�������炢���ȁA����Ȃ��́v�ɂ��āA���\��ł����B���ԎԁA����{�^���������ƁA�H�ו����łĂ���Ƃ������̖B�q�������Ȃ�ł͂̔��z���������e�ł����B�P�N�P�g�͓����ł����B�u���݂��v�Ƃ������b�ł́A�q�������ɂƂ��Đg�߂ŁA�������I���f����Ă�̂ɂ҂�����̑�ނł����B�q�������ɂ́u���܂�̂��������v�ɂ��āA�l���A���Ƃ̐l�ɂ��Q�����Ȃ���̎��Ƃł����B�Q�g�͎Z���ŁA�W�|�T�́u�Ђ�����v�ł����B�u���b�N�̋�̕����g���āA���̊W��ڂɌ�����`�ő��������܂����B�܂��A�Ђ�����̎��ƊG���A���t�Ƃ����т��܂����B�q�������͒�����āA��������̔��\�����Ă��܂����B�ҏ��̒��A�����̂��Q�ς����肪�Ƃ��������܂����B�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@ �@
�@
�@4�N���̍���u��̉ԁv�̊w�K�ł��B�u��̉ԁv�́A�펞���̌��������ŁA�Ƒ��̈��ƁA���e�̐[���v�����@�ׂɕ`���ꂽ����ł��B�����́A�펞���Ɛ����r���A�ω���ǂݎ��܂����B��l���́u��݂��v�Ƃ���������A�H���A�R�X���X���̕\���̎d���ɂ��āA�O���[�v�Řb�������A���\���܂����B
�@�P�C�Q�N���̎��ƎQ�ς�����܂����B�Q�N���͓�N���X�Ƃ��A����u�������炢���ȁA����Ȃ��́v�ɂ��āA���\��ł����B���ԎԁA����{�^���������ƁA�H�ו����łĂ���Ƃ������̖B�q�������Ȃ�ł͂̔��z���������e�ł����B�P�N�P�g�͓����ł����B�u���݂��v�Ƃ������b�ł́A�q�������ɂƂ��Đg�߂ŁA�������I���f����Ă�̂ɂ҂�����̑�ނł����B�q�������ɂ́u���܂�̂��������v�ɂ��āA�l���A���Ƃ̐l�ɂ��Q�����Ȃ���̎��Ƃł����B�Q�g�͎Z���ŁA�W�|�T�́u�Ђ�����v�ł����B�u���b�N�̋�̕����g���āA���̊W��ڂɌ�����`�ő��������܂����B�܂��A�Ђ�����̎��ƊG���A���t�Ƃ����т��܂����B�q�������͒�����āA��������̔��\�����Ă��܂����B�ҏ��̒��A�����̂��Q�ς����肪�Ƃ��������܂����B�@
�U���P�W���i�j�@�Z�O�w�K�R�N���i�k�{���R�ώ@�����j
�@
�@�������ҏ��ɂȂ�܂������A�R�N���́A�k�{���R�ώ@�����ɍs���Ă��܂����B���̓��̂��߂ɁA�Ă�Ă�V����P�O�肢�����߂č��������������܂������A������ƓV�C���ǂ����܂��B
�@�k�{���R�ώ@�����́A��ʌ��́u���n���R�v�̎��R�����c���Ȃ���A�쐶�̐����������炵�₷���悤�A��������l���������R�ɐe���߂�悤������ꂽ�����ł��B
�@�͂��߂ɁA�W�̕�����k�{���R�ώ@�����̐��������������܂����B�쐶�̒���A�����������邱�Ƃ����ɐ������Ă��������܂����B����ł́A�̎}�ɋ[�Ԃ���i�i�t�V�ɏo��܂����B�i�i�t�V�̍ő�̓����́A�̎}�ɋ[�Ԃ��ĊO�G����g������Ă���Ƃ���ł��B�����U���͂�f�����^���\�͂������Ȃ�����ɁA�ׂ��̂�̎}��t���ς̂悤�Ɍ��������āA�G���\���Ă���̂ł��B�q�������̓i�i�t�V��r�ɂ̂�����A��������肷�邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�ҏ��̂��߁A���ٓ��͎����ł��������܂����B�ߌ�͍H���������A�~�j�V�A�^�[���ς���Ə[���������Ԃ��߂����܂����B���s�ψ��A�o�X���N����A������W����A�����܂ł̏������肪�Ƃ��������܂����B�����̉^�c�����炵�������ł��B�o���̏W���ŁA�Z�����b�����R�̂��u�������v�u����v�u�����������Ƃv���ӎ����Ď��g�߂��Ɠ����̏W���ŐU��Ԃ肪�ł��܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@
�@�������ҏ��ɂȂ�܂������A�R�N���́A�k�{���R�ώ@�����ɍs���Ă��܂����B���̓��̂��߂ɁA�Ă�Ă�V����P�O�肢�����߂č��������������܂������A������ƓV�C���ǂ����܂��B
�@�k�{���R�ώ@�����́A��ʌ��́u���n���R�v�̎��R�����c���Ȃ���A�쐶�̐����������炵�₷���悤�A��������l���������R�ɐe���߂�悤������ꂽ�����ł��B
�@�͂��߂ɁA�W�̕�����k�{���R�ώ@�����̐��������������܂����B�쐶�̒���A�����������邱�Ƃ����ɐ������Ă��������܂����B����ł́A�̎}�ɋ[�Ԃ���i�i�t�V�ɏo��܂����B�i�i�t�V�̍ő�̓����́A�̎}�ɋ[�Ԃ��ĊO�G����g������Ă���Ƃ���ł��B�����U���͂�f�����^���\�͂������Ȃ�����ɁA�ׂ��̂�̎}��t���ς̂悤�Ɍ��������āA�G���\���Ă���̂ł��B�q�������̓i�i�t�V��r�ɂ̂�����A��������肷�邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�ҏ��̂��߁A���ٓ��͎����ł��������܂����B�ߌ�͍H���������A�~�j�V�A�^�[���ς���Ə[���������Ԃ��߂����܂����B���s�ψ��A�o�X���N����A������W����A�����܂ł̏������肪�Ƃ��������܂����B�����̉^�c�����炵�������ł��B�o���̏W���ŁA�Z�����b�����R�̂��u�������v�u����v�u�����������Ƃv���ӎ����Ď��g�߂��Ɠ����̏W���ŐU��Ԃ肪�ł��܂����B
�U���P�V���i�j�x�����āE���_�J�̐S���E�����������͂��낤
�@�P�N���̐����Ȃł̓A�T�K�I����ĂĂ��܂��B�����o�Z����ƁA�����̂����b�����Ă��܂��B�{�t���T�A�U���ɂȂ�A�邪�̂тĂ��܂����B�����͂P���ԖڂɎx���𗧂ĂĂ��܂����B�����̎x���𗧂Ă�ꂽ��A�F�B�̂Ƃ���ւ���`���ɍs���Ă��܂����B�قق��܂������i�ł��B�Ԃ��炭�̂��y���݂ɂ��Ă���q�������ł����B
�@�T�N���̗��Ȃł́A�u���_�J�̂��傤�v���w�K���Ă��܂��B�����ł��x�����_�Ń��_�J�Q�O�C�����炵�Ă��܂��B�����ɂ悤�ɗ����Y��ł���̂ŁA�ǂ�ǂ�Ԃ���a�����Ă��܂��B�����́A���_�J�̗����������ł̂����Ă݂܂����B���̒��ɂ́A�ڂ�������́A�����ۂ��łĂ������ȗ�������܂����B���ȒS���̋�����C���u���_�J�̐S�����������v�Ɛ���������ƁA�x�ݎ��Ԃɂ�������炸�A�q�������͗���Ȃ��Ă��̐S���̓������m���߂܂����B���������̂����Ă݂�ƁA�m���ɓ����Ă��܂��B�����ȏ����Ȗ��ł��B���߂Č��܂����B�ƂĂ����Ƃ������v���܂����B�q�������������v���ł��B
�@�R�N���̎Z���ł́A�u�����������͂��낤�v�̊w�K�����Ă��܂����B�q�������������Ă݂����ꏊ��F�B�Ƙb�������܂����B���̌�A�����ڂ��g���Ē������̂̒����𑪂�܂����B�����ڂ��߂ɂȂ��Ă��܂�����A����݂��Ȃ��悤�ɂ�����A�H�v���Đ}��܂����B�Q�N���̊w�K�Ŏg�������̂����Ƃ͈Ⴂ�A�Ȗʏ�̒���������ł��邱�Ƃɋ���������܂����B���̂����Ɗ����ڂ̂��ꂼ��̂悳���������܂����B�����̒����A���A�L�����A�O���[�v�Ŋy���݂Ȃ���A�����Ă��܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�P�N���̐����Ȃł̓A�T�K�I����ĂĂ��܂��B�����o�Z����ƁA�����̂����b�����Ă��܂��B�{�t���T�A�U���ɂȂ�A�邪�̂тĂ��܂����B�����͂P���ԖڂɎx���𗧂ĂĂ��܂����B�����̎x���𗧂Ă�ꂽ��A�F�B�̂Ƃ���ւ���`���ɍs���Ă��܂����B�قق��܂������i�ł��B�Ԃ��炭�̂��y���݂ɂ��Ă���q�������ł����B
�@�T�N���̗��Ȃł́A�u���_�J�̂��傤�v���w�K���Ă��܂��B�����ł��x�����_�Ń��_�J�Q�O�C�����炵�Ă��܂��B�����ɂ悤�ɗ����Y��ł���̂ŁA�ǂ�ǂ�Ԃ���a�����Ă��܂��B�����́A���_�J�̗����������ł̂����Ă݂܂����B���̒��ɂ́A�ڂ�������́A�����ۂ��łĂ������ȗ�������܂����B���ȒS���̋�����C���u���_�J�̐S�����������v�Ɛ���������ƁA�x�ݎ��Ԃɂ�������炸�A�q�������͗���Ȃ��Ă��̐S���̓������m���߂܂����B���������̂����Ă݂�ƁA�m���ɓ����Ă��܂��B�����ȏ����Ȗ��ł��B���߂Č��܂����B�ƂĂ����Ƃ������v���܂����B�q�������������v���ł��B
�@�R�N���̎Z���ł́A�u�����������͂��낤�v�̊w�K�����Ă��܂����B�q�������������Ă݂����ꏊ��F�B�Ƙb�������܂����B���̌�A�����ڂ��g���Ē������̂̒����𑪂�܂����B�����ڂ��߂ɂȂ��Ă��܂�����A����݂��Ȃ��悤�ɂ�����A�H�v���Đ}��܂����B�Q�N���̊w�K�Ŏg�������̂����Ƃ͈Ⴂ�A�Ȗʏ�̒���������ł��邱�Ƃɋ���������܂����B���̂����Ɗ����ڂ̂��ꂼ��̂悳���������܂����B�����̒����A���A�L�����A�O���[�v�Ŋy���݂Ȃ���A�����Ă��܂����B
�U���P�U���i���j�������̐����������E����܂��悤��…
�@3�N�P�g�̃x�����_�̏�ɁA�����̓c�o���̑��Ƀc�o���������Ƃ��Ă��܂����B�q�i������̂��ǂ����܂������킩��܂���B�J�����ڐ��𑗂��Ă���܂����B
�@�����́u���߂����v�ł��B�S���̂��ׂĂ̑��������Ƃ��āA�E�͂��Ă��܂����B���������i�ł��B���������Â��Ƒ����������߂Ă��܂��܂����B�u���߂����v�������̂�…�Ǝv���܂����B
�@�T�N���̗��Ȃł́u���_�J�̒a���v�ɂ��Ċw�K���Ă��܂��B�T�N�P�g�̃x�����_�ɂ́A�Q�O�C�قǂ̃��_�J�����炳��Ă��܂��B�����Ȗ��̑��������L���A���R�ɐe���ސS���u���_�J�v�𗑂����ĂĂ݂����v�Ƃ����������̎��犈���ւ̈ӗ~�����߂Ă��܂��B���łɂ�������̗����Y��ł��܂��B�������������邩�ǂ����AH�����ׂĂ��܂����B
�@�P�W���i���j�́A�R�N���̍Z�O�w�K�ł��B�R�N�P�g�̋����ɂ́A��������̎���u�Ă�Ă�V��v�������Ă��܂����B�q�������̊肢�͂����Ɗ����܂��B�i�������ł���…�j
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@3�N�P�g�̃x�����_�̏�ɁA�����̓c�o���̑��Ƀc�o���������Ƃ��Ă��܂����B�q�i������̂��ǂ����܂������킩��܂���B�J�����ڐ��𑗂��Ă���܂����B
�@�����́u���߂����v�ł��B�S���̂��ׂĂ̑��������Ƃ��āA�E�͂��Ă��܂����B���������i�ł��B���������Â��Ƒ����������߂Ă��܂��܂����B�u���߂����v�������̂�…�Ǝv���܂����B
�@�T�N���̗��Ȃł́u���_�J�̒a���v�ɂ��Ċw�K���Ă��܂��B�T�N�P�g�̃x�����_�ɂ́A�Q�O�C�قǂ̃��_�J�����炳��Ă��܂��B�����Ȗ��̑��������L���A���R�ɐe���ސS���u���_�J�v�𗑂����ĂĂ݂����v�Ƃ����������̎��犈���ւ̈ӗ~�����߂Ă��܂��B���łɂ�������̗����Y��ł��܂��B�������������邩�ǂ����AH�����ׂĂ��܂����B
�@�P�W���i���j�́A�R�N���̍Z�O�w�K�ł��B�R�N�P�g�̋����ɂ́A��������̎���u�Ă�Ă�V��v�������Ă��܂����B�q�������̊肢�͂����Ɗ����܂��B�i�������ł���…�j
 �@
�@�U���P�R���i���j�Z�O�w�K�S�N�i����a���̗��E��̔����فj
�@�����ňꏏ�ɏo�����܂����B�܂��́u����a���̗��v�ł��B�E�l����A�a���̗��j������������Ă��������܂����B�b���������肫���Ă��ė��h�ł����B���ۂɎ������̌��ɂ��`�������W���܂����B�v�������A�킭���d�������悤�ł��B�͂��߂́A�W�̕����x���Ă���܂������A�r�������l�ł��܂����B�c�ɉ��ɔg�ł悤�ɗh�炵�܂����B�����̎�ł������a�����u�ł�������̂��y���݁I�v�ƂЂƂ݂��P�����Ă��܂����B�W�����ł́A�a������铹��␢�E������Y�ɓo�^���ꂽ�א�a���������w���܂����B�W������Ă���ԁX�����ׂĘa���łł��Ă���̂����āA�����܂����B
�@�u��̔����فv�ł́A��̂͂��炫�␅�̑���ɂ��āA�r����������瓌���p�܂ōČ������f��Ϗ܁A���̗͂œ������ԁA�S�TK�������鐅���^�Ԃ��߂̉������̌��R�[�i�[�ł́A�̂̐l�X������������グ�邾���łȂ��A�^��ł������Ƃ��w�сA���̋�J�̈�������Ă��܂����B�S�C���������ɍČ�����A�����̎������ς܂����B�����ƂƂ��ɁA�����Ԃ��������āA��C�ɗ����l�q�͔��͂�����܂����B
�@���s�ψ��A�o�X���N�S���̎q�������́A���̓��̂��߂ɂ������������Ă���܂����B�W�c�Ƃ��Ă̐����������܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�����ňꏏ�ɏo�����܂����B�܂��́u����a���̗��v�ł��B�E�l����A�a���̗��j������������Ă��������܂����B�b���������肫���Ă��ė��h�ł����B���ۂɎ������̌��ɂ��`�������W���܂����B�v�������A�킭���d�������悤�ł��B�͂��߂́A�W�̕����x���Ă���܂������A�r�������l�ł��܂����B�c�ɉ��ɔg�ł悤�ɗh�炵�܂����B�����̎�ł������a�����u�ł�������̂��y���݁I�v�ƂЂƂ݂��P�����Ă��܂����B�W�����ł́A�a������铹��␢�E������Y�ɓo�^���ꂽ�א�a���������w���܂����B�W������Ă���ԁX�����ׂĘa���łł��Ă���̂����āA�����܂����B
�@�u��̔����فv�ł́A��̂͂��炫�␅�̑���ɂ��āA�r����������瓌���p�܂ōČ������f��Ϗ܁A���̗͂œ������ԁA�S�TK�������鐅���^�Ԃ��߂̉������̌��R�[�i�[�ł́A�̂̐l�X������������グ�邾���łȂ��A�^��ł������Ƃ��w�сA���̋�J�̈�������Ă��܂����B�S�C���������ɍČ�����A�����̎������ς܂����B�����ƂƂ��ɁA�����Ԃ��������āA��C�ɗ����l�q�͔��͂�����܂����B
�@���s�ψ��A�o�X���N�S���̎q�������́A���̓��̂��߂ɂ������������Ă���܂����B�W�c�Ƃ��Ă̐����������܂����B
�U���P�Q���i�j�|���̎��ԁE�N���u����
�@5�N���̋����O�̘L���́A���Ȃ艘�ꂪ�ڗ����܂��B�㗚���̃S���̐Ղ���������Ȃ��قǂ���܂��B�����Łu����������v�̗͂���āA�q���������ꐶ���������܂����B���̑|���ꏊ���I������q����������`���Ă���܂����B���肪�Ƃ��B�܂��܂�����͂���܂����A�����������A���ꂢ�ɂ��Ă��������ł��B
�@�N���u�����ł́A�Ȋw�N���u���ׂ��b���Â�������Ă��܂����B�����Ɛ����悭�������킹�A�A���~�z�C���ɗ�������܂��B�����āA�z�b�g�v���[�g�ŏł��Ȃ��悤�ɉ��M���܂��B�E�����܂ō����������������ȍ��肪���܂����B
 �@
�@
 �@
�@
�@5�N���̋����O�̘L���́A���Ȃ艘�ꂪ�ڗ����܂��B�㗚���̃S���̐Ղ���������Ȃ��قǂ���܂��B�����Łu����������v�̗͂���āA�q���������ꐶ���������܂����B���̑|���ꏊ���I������q����������`���Ă���܂����B���肪�Ƃ��B�܂��܂�����͂���܂����A�����������A���ꂢ�ɂ��Ă��������ł��B
�@�N���u�����ł́A�Ȋw�N���u���ׂ��b���Â�������Ă��܂����B�����Ɛ����悭�������킹�A�A���~�z�C���ɗ�������܂��B�����āA�z�b�g�v���[�g�ŏł��Ȃ��悤�ɉ��M���܂��B�E�����܂ō����������������ȍ��肪���܂����B
�U���P�P���i���j�������ǂ��܂菀���E���y�ӏ܋���
�@���N�x�̐������ǂ��܂�́A�N���X���Ƃ̏o�����ł͂Ȃ��A�c����ǁi�P�N������U�N���̍\���j�ł�
���X���o���܂��B���ɔz�������o���������ꂼ��̔ǂōl���Ă��܂��B�e�ǂ̎q�������́A������������̂��U�N�������S�ƂȂ��Đ��������Ă��܂����B���������ł��B
�@���M���y��w�ŁA���y�ӏ܋���������܂����B���N�U�N�����Q�����܂��B���߂Č���y�������܂����B����ɃN�����l�b�g�Ƃ����Ă��A���̍��Ⴊ����o�X�N�����l�b�g�Ƃ����y�������܂����B���y���x����ቷ�y������y�ɉԂ�Y���Ă��܂��B
�@�w���ґ̌��ł́AM������Ă���܂����B�n�܂�O����ƂĂ��s���ȗl�q�ł������A����Ă݂�ƒ��J�ɂ������Ɠ��X�Ɛ��t�y�����[�h���܂����B���炵���w���ł����B�I����Ă���̑傫�Ȕ���Ɉ��g�������ƂƎv���܂��B�I����Ă���u�y���������ł��v�̌��t�͂ƂĂ���ۂɎc��܂����B�A���R�[���ł́A�݂�Ȏ蔏�q�ʼn��t�ɍ��킹�ăm���m���ł����B���̉��t���ӏ܂���̌��́A�S��h���Ԃ��܂����B�q�������ɂƂ��āA�ꐶ�̎v���o�ɂȂ������Ƃł��傤�B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@���N�x�̐������ǂ��܂�́A�N���X���Ƃ̏o�����ł͂Ȃ��A�c����ǁi�P�N������U�N���̍\���j�ł�
���X���o���܂��B���ɔz�������o���������ꂼ��̔ǂōl���Ă��܂��B�e�ǂ̎q�������́A������������̂��U�N�������S�ƂȂ��Đ��������Ă��܂����B���������ł��B
�@���M���y��w�ŁA���y�ӏ܋���������܂����B���N�U�N�����Q�����܂��B���߂Č���y�������܂����B����ɃN�����l�b�g�Ƃ����Ă��A���̍��Ⴊ����o�X�N�����l�b�g�Ƃ����y�������܂����B���y���x����ቷ�y������y�ɉԂ�Y���Ă��܂��B
�@�w���ґ̌��ł́AM������Ă���܂����B�n�܂�O����ƂĂ��s���ȗl�q�ł������A����Ă݂�ƒ��J�ɂ������Ɠ��X�Ɛ��t�y�����[�h���܂����B���炵���w���ł����B�I����Ă���̑傫�Ȕ���Ɉ��g�������ƂƎv���܂��B�I����Ă���u�y���������ł��v�̌��t�͂ƂĂ���ۂɎc��܂����B�A���R�[���ł́A�݂�Ȏ蔏�q�ʼn��t�ɍ��킹�ăm���m���ł����B���̉��t���ӏ܂���̌��́A�S��h���Ԃ��܂����B�q�������ɂƂ��āA�ꐶ�̎v���o�ɂȂ������Ƃł��傤�B
�U���P�O���i�j�������̓��E���j�w�K�ŏI��
�@���������ψ�����������Ⴂ��u�������^���v�ł��B�����͍~�J�ł������A�J�ɕ����Ȃ��ł������������������ł��傤���A�r������J����݂܂����B�����͂T�N���������������^���ɎQ�����Ă���܂����B���肪�Ƃ��B
�@���j�w�K�̍ŏI���ł��B�S����{��������3��͍~�J�ɂȂ��Ă��܂��܂������A�q�������ɂ͊W����܂���B�v�[���ɓ���̂��y���݂ɂ��Ă���Ă��܂����B��������w�N�ƈꏏ�Ƀo�X�ɏ��܂����B�����1�N���̃o�X�ł��B�����u����Ƃ�v�u����͂Ȃɂł��傤�Q�[���v�i�Ȃ�ׂ����Ȃ��q���g�ƌ����Ă��Ă�Q�[���ł��j�����܂����B����Ƃ�́A�ƂĂ����������ł��B���ǎ{�݂ɓ������Ă������͂����A1�N�����킴�Ɓu��v�������t�������ďI���ɂ��܂����B�����Ƃ����Ԃ̓����ł����B
�@�ӂ���������A���̂сA��������ɂ��ăy�A�ŃR�[�X�����w�K�����܂����B���w���ł́A�����O�̕����A�E�͂��đ̂�����������A�r�[�g���g�p���ăo�^���������肵�܂����B
�@���w�N�͌ߌ�ł��B������ɍs���ƁA�q����������������Ί�������Ă���A���U���Ă��ꂽ�q�����܂����B�����Ă������`���I
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@

�@���������ψ�����������Ⴂ��u�������^���v�ł��B�����͍~�J�ł������A�J�ɕ����Ȃ��ł������������������ł��傤���A�r������J����݂܂����B�����͂T�N���������������^���ɎQ�����Ă���܂����B���肪�Ƃ��B
�@���j�w�K�̍ŏI���ł��B�S����{��������3��͍~�J�ɂȂ��Ă��܂��܂������A�q�������ɂ͊W����܂���B�v�[���ɓ���̂��y���݂ɂ��Ă���Ă��܂����B��������w�N�ƈꏏ�Ƀo�X�ɏ��܂����B�����1�N���̃o�X�ł��B�����u����Ƃ�v�u����͂Ȃɂł��傤�Q�[���v�i�Ȃ�ׂ����Ȃ��q���g�ƌ����Ă��Ă�Q�[���ł��j�����܂����B����Ƃ�́A�ƂĂ����������ł��B���ǎ{�݂ɓ������Ă������͂����A1�N�����킴�Ɓu��v�������t�������ďI���ɂ��܂����B�����Ƃ����Ԃ̓����ł����B
�@�ӂ���������A���̂сA��������ɂ��ăy�A�ŃR�[�X�����w�K�����܂����B���w���ł́A�����O�̕����A�E�͂��đ̂�����������A�r�[�g���g�p���ăo�^���������肵�܂����B
�@���w�N�͌ߌ�ł��B������ɍs���ƁA�q����������������Ί�������Ă���A���U���Ă��ꂽ�q�����܂����B�����Ă������`���I
�U���X���i���j�w����E��������
�@�U�N���̊w����ł��B�u�N���X�̃L�����N�^�[���l���悤�v�Ƃ����c��ł����B�߂��Ắu�U�|�P�炵�������̂킭�L�����N�^�[���l���悤�v�ł����B���P�ł́A�u�ǂ�Ȃ��̂����`�[�t�v�ɂ��邩�ł����B�����i�˂��A����A���b�T�[�p���_�A�����j�A�w�N�X�q�̈ӌ����o����܂����B���ꂼ��̍l���ɂ��Ĕ��\������A�^���ӌ���S�z�Ȉӌ���b�������܂����B���Ԃ�����Ȃ��Ȃ�A���Q�Ɉڂ�܂����B���Q�ł́A�ǂ�ɂȂ��Ă������悤�ȁA�u���܂������`�[�t�̓����v���l���܂����B�ӌ��̒��Łu�������̃o�b�W�v���o��ƁA�u�����`�v�Ɣ[������悤�Ȑ���������������o�܂����B�q���������i�߂��悢���̂����낤�Ƃ��Ă���p�A�ӌ���ے肷��̂ł͂Ȃ��A�F�B�̈ӌ����ɂ��Ȃ���̈ӌ��ɁA�q�������̐����������܂����B
�@���������ł́A�T�����l�̏ꏊ�ŐL�тĂ����������������܂����B���ꂩ��ǂ�ǂ��̂тĂ��鎞���ɂ��ꂢ�ɂł��A�������肵�܂����B�Ԓd�����ꂩ��ėp�̂��ԂɐA���ւ��ł��B���ݑ܂͂P�O�܂ɂ��Ȃ�܂����B���肪�Ƃ��I
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�U�N���̊w����ł��B�u�N���X�̃L�����N�^�[���l���悤�v�Ƃ����c��ł����B�߂��Ắu�U�|�P�炵�������̂킭�L�����N�^�[���l���悤�v�ł����B���P�ł́A�u�ǂ�Ȃ��̂����`�[�t�v�ɂ��邩�ł����B�����i�˂��A����A���b�T�[�p���_�A�����j�A�w�N�X�q�̈ӌ����o����܂����B���ꂼ��̍l���ɂ��Ĕ��\������A�^���ӌ���S�z�Ȉӌ���b�������܂����B���Ԃ�����Ȃ��Ȃ�A���Q�Ɉڂ�܂����B���Q�ł́A�ǂ�ɂȂ��Ă������悤�ȁA�u���܂������`�[�t�̓����v���l���܂����B�ӌ��̒��Łu�������̃o�b�W�v���o��ƁA�u�����`�v�Ɣ[������悤�Ȑ���������������o�܂����B�q���������i�߂��悢���̂����낤�Ƃ��Ă���p�A�ӌ���ے肷��̂ł͂Ȃ��A�F�B�̈ӌ����ɂ��Ȃ���̈ӌ��ɁA�q�������̐����������܂����B
�@���������ł́A�T�����l�̏ꏊ�ŐL�тĂ����������������܂����B���ꂩ��ǂ�ǂ��̂тĂ��鎞���ɂ��ꂢ�ɂł��A�������肵�܂����B�Ԓd�����ꂩ��ėp�̂��ԂɐA���ւ��ł��B���ݑ܂͂P�O�܂ɂ��Ȃ�܂����B���肪�Ƃ��I
�U���V���i�y�j�O�p���w�Z�^����
�@��䐼���w�Z��̏����A�g�����Ă���O�p���w�Z�̉^����ɍs���܂����B�L����f���炵���V�C�ɂȂ�܂����B�O�p���w�Z�Ƀe���g���Q�͂�݂��܂������A�P�͎����ȁA������͖{���ȂɎg�p���Ă��������Ă��܂����B�{�Z�T�O���N�L�O�ło�s�`�̊F�l�ɍw�����Ă����������e���g�̉��Ŋϐ킳���Ă��������܂����B�R�F�i�ԁA���A�j�ɕ�����ĉ�������A���Z�ɐ����o������A��������ƑS�͂̎p�Ɋ������܂����B
�@�F�B�̉����ɗ��Ă����P�N���ɉ�܂����B���������Ă���Ă��肪�Ƃ��I
 �@
�@
�@��䐼���w�Z��̏����A�g�����Ă���O�p���w�Z�̉^����ɍs���܂����B�L����f���炵���V�C�ɂȂ�܂����B�O�p���w�Z�Ƀe���g���Q�͂�݂��܂������A�P�͎����ȁA������͖{���ȂɎg�p���Ă��������Ă��܂����B�{�Z�T�O���N�L�O�ło�s�`�̊F�l�ɍw�����Ă����������e���g�̉��Ŋϐ킳���Ă��������܂����B�R�F�i�ԁA���A�j�ɕ�����ĉ�������A���Z�ɐ����o������A��������ƑS�͂̎p�Ɋ������܂����B
�@�F�B�̉����ɗ��Ă����P�N���ɉ�܂����B���������Ă���Ă��肪�Ƃ��I
 �@
�@
�U���U���i���j �I���G���e�[�����O�E�v���O���~���O�w�K�E�������炢���Ȃ���Ȃ���
�@4�N���̊w�N�W��ł��B���T���j���Ɏ��{����Z�O�w�K�̃I���G���e�[�����O�����Ă��܂����B�S�C���u��̔����فv�Ɓu�a���̗��v�ɉ����ɍs�����Ƃ��̎ʐ^���f���o�����ƁA�q�������̖ڂ��P���܂����B�����ɗ����������A���ʂ����������܂����B�u�J���~������ʐ^�B�e�͂ǂ�����̂��v�ƋC�ɂȂ邱�Ƃ����₵�Ă��܂����B4�N���ƈꏏ�ɍZ�O�w�K�ɏo������̂Ŋy���݂ł��B
�@�R�N���̃v���O���~���O�w�K����������n�܂�܂����B�ӂ��ݖ�s����ψ���̉|�{�搶�ɂ��w�����������܂����B�q�������̎x�������Ă�������{�����e�B�A�̕��X���S�����炵�Ă��������܂����B�v���O���~���O�Ƃ͂Ȃɂ��Ƃ����Ƃ��납��A�������Ă��������܂����B�l�R�������v���O���~���O�w�K�c�[���́u�X�N���b�`�v���g�p���܂����B�˂����㉺���E�ɓ��������Ƃ���n�߂܂����B���T���p�����܂��B
�@�Q�N���̍���ł��B�����̒��Łu����ȂƂ��ɂ���Ȃ��̂��������炢���̂ɂȁv�Ɗ������o������A�֗��ȓ�����l���܂��B���������̓I�Ȍ`�ɂ��邽�߂ɁA����̘b�̓��e�𑨂��Ď��₵����A���z��`�����肷��͂���Ă܂��B�����͂��̈ꎞ�ԖڂŁA�q���������u�������炢���ȁv�u�ł����炢���ȁv�����l���܂����B�u�C�ɂ������ԁv�u���Ⴎ������W���[�X�v�u�����������Ƃ��ꂢ�Ȏ��ɂȂ邦��҂v���m�[�g�ɏ����Ă��܂����B���������̂��^�u���b�g�Ŏʐ^���Ƃ�A�X�N�[���^�N�g�ɃA�b�v���܂����B�q�������Ȃ�ł͂̃A�C�f�B�A����������o�Ă��܂����B


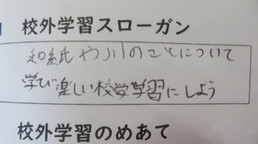




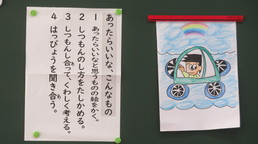
�@4�N���̊w�N�W��ł��B���T���j���Ɏ��{����Z�O�w�K�̃I���G���e�[�����O�����Ă��܂����B�S�C���u��̔����فv�Ɓu�a���̗��v�ɉ����ɍs�����Ƃ��̎ʐ^���f���o�����ƁA�q�������̖ڂ��P���܂����B�����ɗ����������A���ʂ����������܂����B�u�J���~������ʐ^�B�e�͂ǂ�����̂��v�ƋC�ɂȂ邱�Ƃ����₵�Ă��܂����B4�N���ƈꏏ�ɍZ�O�w�K�ɏo������̂Ŋy���݂ł��B
�@�R�N���̃v���O���~���O�w�K����������n�܂�܂����B�ӂ��ݖ�s����ψ���̉|�{�搶�ɂ��w�����������܂����B�q�������̎x�������Ă�������{�����e�B�A�̕��X���S�����炵�Ă��������܂����B�v���O���~���O�Ƃ͂Ȃɂ��Ƃ����Ƃ��납��A�������Ă��������܂����B�l�R�������v���O���~���O�w�K�c�[���́u�X�N���b�`�v���g�p���܂����B�˂����㉺���E�ɓ��������Ƃ���n�߂܂����B���T���p�����܂��B
�@�Q�N���̍���ł��B�����̒��Łu����ȂƂ��ɂ���Ȃ��̂��������炢���̂ɂȁv�Ɗ������o������A�֗��ȓ�����l���܂��B���������̓I�Ȍ`�ɂ��邽�߂ɁA����̘b�̓��e�𑨂��Ď��₵����A���z��`�����肷��͂���Ă܂��B�����͂��̈ꎞ�ԖڂŁA�q���������u�������炢���ȁv�u�ł����炢���ȁv�����l���܂����B�u�C�ɂ������ԁv�u���Ⴎ������W���[�X�v�u�����������Ƃ��ꂢ�Ȏ��ɂȂ邦��҂v���m�[�g�ɏ����Ă��܂����B���������̂��^�u���b�g�Ŏʐ^���Ƃ�A�X�N�[���^�N�g�ɃA�b�v���܂����B�q�������Ȃ�ł͂̃A�C�f�B�A����������o�Ă��܂����B
�U���T���i�j�@���̂������̂����E�u�����āA���Ȃ��̂��Ɓv�E�Z�O�w�K�P�A�Q�N
�@�R�N�P�g�̃x�����_�Ƀc�o�����H���x�߂Ă��܂����B��ɂ��鑃������Ƃ����P�H�̃c�o�������܂��B�������q�i���a�����Ă���Ƃ����ł��B
�@�o�Z�����T�N����H���u�Z���搶�A�ςȒ������邩�痈�Ă��������I�v�Ɛ��������܂����B�͗t�̂悤�Ȓ��ł��B�u�ʐ^���B���Ă��������������ł���v�Ǝq���������犩�߂��܂����B�������߂Ă݂钎�ł��B���ׂĂ݂��…�u�X�Y���K�v�Ƃ����u��v�ł����B�q�������̂������Ŏ����w�т܂����B�������͎��R�L���Ȋw�Z�Ȃ̂ł��B
�@�T�N���̍���ł��B�u�����āA���Ȃ��̂��Ɓv�Ƃ����P���ł́A�F�B�ƃC���^�r���[�������A�C���^�r���[�Œm�������Ƃ����Ƃɂ��āA���̗F�B���Љ��w�K���s���܂��B�����͂��̔��\�����Ă��܂����BI����́u�P�N������̑����K���Ă��邱�Ɓv�AM����́u�e�j�X���K���Ă��邱�Ɓv���A�V�������āA�F�B�̐V���Ȉ�ʂ�悳�������邱�Ƃ��ł��܂����B�Љ���q�������́A�����Ƃꂭ�������Ȋ����ł����B
�@�P�C�Q�N�������ŁA�Z�O�w�K�֏o�����܂����B2�N���́A���s�ψ��̎q���������i������Ă��܂����B�������������ł��B�T�v�ے��������ł��Q�N�����P�N�������[�h���āA�P�N�����y�����V�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B�u����܂�����v�u����܂���̈���v�u�����Q�[���v���A�݂�ȏΊ炪�͂����Ă��܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@




�@�R�N�P�g�̃x�����_�Ƀc�o�����H���x�߂Ă��܂����B��ɂ��鑃������Ƃ����P�H�̃c�o�������܂��B�������q�i���a�����Ă���Ƃ����ł��B
�@�o�Z�����T�N����H���u�Z���搶�A�ςȒ������邩�痈�Ă��������I�v�Ɛ��������܂����B�͗t�̂悤�Ȓ��ł��B�u�ʐ^���B���Ă��������������ł���v�Ǝq���������犩�߂��܂����B�������߂Ă݂钎�ł��B���ׂĂ݂��…�u�X�Y���K�v�Ƃ����u��v�ł����B�q�������̂������Ŏ����w�т܂����B�������͎��R�L���Ȋw�Z�Ȃ̂ł��B
�@�T�N���̍���ł��B�u�����āA���Ȃ��̂��Ɓv�Ƃ����P���ł́A�F�B�ƃC���^�r���[�������A�C���^�r���[�Œm�������Ƃ����Ƃɂ��āA���̗F�B���Љ��w�K���s���܂��B�����͂��̔��\�����Ă��܂����BI����́u�P�N������̑����K���Ă��邱�Ɓv�AM����́u�e�j�X���K���Ă��邱�Ɓv���A�V�������āA�F�B�̐V���Ȉ�ʂ�悳�������邱�Ƃ��ł��܂����B�Љ���q�������́A�����Ƃꂭ�������Ȋ����ł����B
�@�P�C�Q�N�������ŁA�Z�O�w�K�֏o�����܂����B2�N���́A���s�ψ��̎q���������i������Ă��܂����B�������������ł��B�T�v�ے��������ł��Q�N�����P�N�������[�h���āA�P�N�����y�����V�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B�u����܂�����v�u����܂���̈���v�u�����Q�[���v���A�݂�ȏΊ炪�͂����Ă��܂����B
�U���S���i���j�~�̎��E�z�E�Z���J�̒���…�E�{�[�������Q�[��
�@�����A�Z��������u��������Ȃ��قǂ̔~�̎�������܂��v�ƁA�����Ă��������܂����B�Z�����O�̔~�̖ɂ́A�����������Ȕ~���m���ɂ�����������Ă��܂����B�~�̎��͏����₷���̂ŁA�D�������J�ɁA�Z���������n���Ă��������܂����B��N�͏����ł����̂ŁA���N�͖L��ł��B
�@�u�z�E�Z���J�̓y�ɗc�������܂��I�v�ƂR�N�������������Ă���܂����B�u�ǂ�ǂ�…�v�Ƌ��鋰�錩��ƁA�m���ɗc�������܂����B�u�y�̋��S�n�������ˁv�Ƙb���܂����B�u�ʐ^���B��܂������H�v�Ƃx����B�z�E�Z���J�ƂƂ��ɁA�c���ւ̂₳�����v��������܂����B
�@�Q�N���̑̈�u�{�[�������Q�[���v�ł��B�|�[�g�{�[����̋t�ɂ��ă{�[�����S�u���Ă��܂����B�˂�����Ƃ���ɁA�{�[�����Ȃ�����A���肪�߂�₷���{�[���𓊂�����ł���悤�ɗ��K�����Ă���A�Q�[�������Ă��܂����B�q�������͖����ɂȂ��āA�Q�[���ɎQ���B���т������ɂȂ��āA�y����ł��܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�����A�Z��������u��������Ȃ��قǂ̔~�̎�������܂��v�ƁA�����Ă��������܂����B�Z�����O�̔~�̖ɂ́A�����������Ȕ~���m���ɂ�����������Ă��܂����B�~�̎��͏����₷���̂ŁA�D�������J�ɁA�Z���������n���Ă��������܂����B��N�͏����ł����̂ŁA���N�͖L��ł��B
�@�u�z�E�Z���J�̓y�ɗc�������܂��I�v�ƂR�N�������������Ă���܂����B�u�ǂ�ǂ�…�v�Ƌ��鋰�錩��ƁA�m���ɗc�������܂����B�u�y�̋��S�n�������ˁv�Ƙb���܂����B�u�ʐ^���B��܂������H�v�Ƃx����B�z�E�Z���J�ƂƂ��ɁA�c���ւ̂₳�����v��������܂����B
�@�Q�N���̑̈�u�{�[�������Q�[���v�ł��B�|�[�g�{�[����̋t�ɂ��ă{�[�����S�u���Ă��܂����B�˂�����Ƃ���ɁA�{�[�����Ȃ�����A���肪�߂�₷���{�[���𓊂�����ł���悤�ɗ��K�����Ă���A�Q�[�������Ă��܂����B�q�������͖����ɂȂ��āA�Q�[���ɎQ���B���т������ɂȂ��āA�y����ł��܂����B
 �@
�@
 �@
�@
�U���R���i�j�J�^�c�����E�N���[������E�d�M
�@���A�o�Z�����P�N����m���A�傫�ȃJ�^�c�����������܂����B�~�J����O�ł����A�����̉J�ƃJ�^�c�������ƂĂ��������܂��B�F�Â����A�W�T�C�̉Ԃ̏�ɁA�₳�����߂��Ă����܂����B���j�w�K���I�������ƂɃA�W�T�C�̂Ƃ����m����ƍs���܂������A���łɈړ����Ă��܂����B
�@�U�N���̉ƒ�Ȃł��B�Z���̗l�X�ȉ����ꏊ�ɂ������|���̎d�����H�v���Ď��H����Ƃ����w�K�ł��B�����́A����͂ǂ��ɂ���̂��}�H���A���Ȏ��A���y�����̓��ʋ����̑��A�K�i�̉���ׂ邽�߁A�^�u���b�g�����p���ʐ^�Ŏ��߂܂����B�ƒ�Ȏ��ɂ��ǂ��Ă��牘��̓��e�ɂ��ăX�N�[���^�N�g�ɒ�o���܂����B�B�ق���A���ȁA�ǂ�A�����ȃS�~�A�H�ׂ����A���̖ѓ�������܂����B�悲��ɂ���āA��ޕ��������Ă���A���H�ɓ���܂��B������ǂ�ȕ��@�ł��ꂢ�ɂ��Ă��邩���l���܂����B
�@�R�N���̍d�M�ł��B����{�Ƃ�������ɏ����悤�Ɉӎ����܂����B���`�𐮂��ď����A�q�������͏W�����Ď��g�݂܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@���A�o�Z�����P�N����m���A�傫�ȃJ�^�c�����������܂����B�~�J����O�ł����A�����̉J�ƃJ�^�c�������ƂĂ��������܂��B�F�Â����A�W�T�C�̉Ԃ̏�ɁA�₳�����߂��Ă����܂����B���j�w�K���I�������ƂɃA�W�T�C�̂Ƃ����m����ƍs���܂������A���łɈړ����Ă��܂����B
�@�U�N���̉ƒ�Ȃł��B�Z���̗l�X�ȉ����ꏊ�ɂ������|���̎d�����H�v���Ď��H����Ƃ����w�K�ł��B�����́A����͂ǂ��ɂ���̂��}�H���A���Ȏ��A���y�����̓��ʋ����̑��A�K�i�̉���ׂ邽�߁A�^�u���b�g�����p���ʐ^�Ŏ��߂܂����B�ƒ�Ȏ��ɂ��ǂ��Ă��牘��̓��e�ɂ��ăX�N�[���^�N�g�ɒ�o���܂����B�B�ق���A���ȁA�ǂ�A�����ȃS�~�A�H�ׂ����A���̖ѓ�������܂����B�悲��ɂ���āA��ޕ��������Ă���A���H�ɓ���܂��B������ǂ�ȕ��@�ł��ꂢ�ɂ��Ă��邩���l���܂����B
�@�R�N���̍d�M�ł��B����{�Ƃ�������ɏ����悤�Ɉӎ����܂����B���`�𐮂��ď����A�q�������͏W�����Ď��g�݂܂����B
 �@
�@
�U���Q���i���j�l������
�@�l���i��ψ��A�s�����܂߂U���̕������Z����u�l�������v�̎��Ƃ����Ă��������܂����B�l���i��ψ��̕��̒��ɂ́A�{�Z�P�P��Z���������ێR�搶���������ɂȂ�A���Ƃ̒��S�ƂȂ��Đi�߂Ă��������܂����B
�@�͂��߂ɁA�l���A�j�����ς܂����B����́A���w4�N���́u���₩�v���������́u�݂䂫�v�Ɏ���̎ʐ^���Ă��v���[���g����Ƃ��납��n�܂�܂��B�������A�u�݂䂫�v�͂��̃v���[���g���C�ɓ��炸�A�u���₩�v�ɂ��������n�߂܂��B����ɂ��A�N���X�S�̂��u���₩�v�𒇊ԊO��ɂ���悤�ɂȂ�܂��B���̃A�j���́A�����߂̖���ʂ��āA�����⑼�l�̐l���̑���ɋC�Â����邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B�����߂Ă���q�A�����߂��Ă���q�A�����߂����Ă���q�ɂ��āA�q�������͂��ꂼ��v�����Ƃ����������Ǝv���܂��B�w�Z���x��l���́u���₩�v�̋C������S�������\���܂����B����ɁA�����������߂�ꂽ��ǂ�����̂����A�������胏�[�N�V�[�g�ɋL�����Ă���A����ɂ��Ă��S�������\���܂����B�e�A�搶�ɑ��k����A�M�������l�ɑ��k����A�����߂Ă���q�Ɖ�b�����ĉ������铙�A�^���ɍl���܂����B�����̎q�������̉�b���ɁA�����߂̉�͂���܂��B�A���e�i�������A������������Ȃ����Ƃ����߂đ���ƍl���������܂����B
�@���ƌ�A���Z���������ێR�搶���A�Z�����Ɍf�z�����Ă���̂��m�F���ɁA�U�N�����������܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@ �@
�@
�@�l���i��ψ��A�s�����܂߂U���̕������Z����u�l�������v�̎��Ƃ����Ă��������܂����B�l���i��ψ��̕��̒��ɂ́A�{�Z�P�P��Z���������ێR�搶���������ɂȂ�A���Ƃ̒��S�ƂȂ��Đi�߂Ă��������܂����B
�@�͂��߂ɁA�l���A�j�����ς܂����B����́A���w4�N���́u���₩�v���������́u�݂䂫�v�Ɏ���̎ʐ^���Ă��v���[���g����Ƃ��납��n�܂�܂��B�������A�u�݂䂫�v�͂��̃v���[���g���C�ɓ��炸�A�u���₩�v�ɂ��������n�߂܂��B����ɂ��A�N���X�S�̂��u���₩�v�𒇊ԊO��ɂ���悤�ɂȂ�܂��B���̃A�j���́A�����߂̖���ʂ��āA�����⑼�l�̐l���̑���ɋC�Â����邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B�����߂Ă���q�A�����߂��Ă���q�A�����߂����Ă���q�ɂ��āA�q�������͂��ꂼ��v�����Ƃ����������Ǝv���܂��B�w�Z���x��l���́u���₩�v�̋C������S�������\���܂����B����ɁA�����������߂�ꂽ��ǂ�����̂����A�������胏�[�N�V�[�g�ɋL�����Ă���A����ɂ��Ă��S�������\���܂����B�e�A�搶�ɑ��k����A�M�������l�ɑ��k����A�����߂Ă���q�Ɖ�b�����ĉ������铙�A�^���ɍl���܂����B�����̎q�������̉�b���ɁA�����߂̉�͂���܂��B�A���e�i�������A������������Ȃ����Ƃ����߂đ���ƍl���������܂����B
�@���ƌ�A���Z���������ێR�搶���A�Z�����Ɍf�z�����Ă���̂��m�F���ɁA�U�N�����������܂����B
�T���R�O���i���j�͂��߂Ă�e���C�u�����E�u������胁���̍H�v�v���\��
�@�ӂ��ݖ�s����ψ���GIGA�X�N�[���劲�̉|�{�搶�����Z���A1�N���ɏ��߂�e���C�u�����̂����������Ă��������܂����Be���C�u�����́A�w�K�x���T�[�r�X�ł��B���w�Z�̋��ȏ��ɑΉ��������ނ��g��AI�^�h���������p���Ċw�K�ł���̂������ł��B�K�n�x�ɉ�������肪�����ō\������邽�߂Ɏ����ɍ������w�ѕ����ł��܂��B���܂Ŋw�K�����Z���́u�����Ƃ����v�ł́A�u���ق�v�u�Ђ傤�����v�u���傤����v�̂R�i�K����q�������������őI��Ŋw�K���܂����B�P�O�O�_���Ƃ��ƁAe���C�u�����̒��̐A�����傫���Ȃ�A��݂ɂȂ�܂��B�u�Ƃł����Ƃ�肽�`���I�v�ƈӗ~���X�ł����B�ی�҂̕��X�ւ̂��ւ�ƂƂ��ɁA�U�����玝���A��܂��B
�@�S�N���̍���u������胁���̍H�v�v�̔��\��ɏ��҂���܂����B�q�������̔��\�����Ă��������܂����B�u�q���̂��떲���ɂȂ����V�т͂Ȃɂ��v�u�搶�ɂȂ������R�͂Ȃɂ��v�u���w���̂Ƃ��̏K�����͂Ȃɂ��v�u���w���̂Ƃ��̍D���ȋ��H�̃��j���[�͉����v���A�q�������������������Ă�����e��搶����l��l�ɕ����ă����ɂƂ�A���\���܂����B���\�̎d���ɂ��āA�u�܂��v�u���Ɂv�u�Ō�Ɂv���ӎ����Ęb���悤�ɂ��܂����B���\�������e�̒��ɁA�u�V���N���i�C�Y�h�X�C�~���O�v���K���Ă����搶�������̂ɁA�q�����������������܂����B���\�����q�������̘b���m�[�g�ɂ������胁�������܂����B
 �@
�@
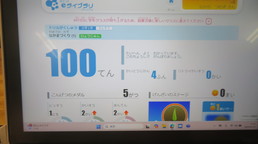 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�ӂ��ݖ�s����ψ���GIGA�X�N�[���劲�̉|�{�搶�����Z���A1�N���ɏ��߂�e���C�u�����̂����������Ă��������܂����Be���C�u�����́A�w�K�x���T�[�r�X�ł��B���w�Z�̋��ȏ��ɑΉ��������ނ��g��AI�^�h���������p���Ċw�K�ł���̂������ł��B�K�n�x�ɉ�������肪�����ō\������邽�߂Ɏ����ɍ������w�ѕ����ł��܂��B���܂Ŋw�K�����Z���́u�����Ƃ����v�ł́A�u���ق�v�u�Ђ傤�����v�u���傤����v�̂R�i�K����q�������������őI��Ŋw�K���܂����B�P�O�O�_���Ƃ��ƁAe���C�u�����̒��̐A�����傫���Ȃ�A��݂ɂȂ�܂��B�u�Ƃł����Ƃ�肽�`���I�v�ƈӗ~���X�ł����B�ی�҂̕��X�ւ̂��ւ�ƂƂ��ɁA�U�����玝���A��܂��B
�@�S�N���̍���u������胁���̍H�v�v�̔��\��ɏ��҂���܂����B�q�������̔��\�����Ă��������܂����B�u�q���̂��떲���ɂȂ����V�т͂Ȃɂ��v�u�搶�ɂȂ������R�͂Ȃɂ��v�u���w���̂Ƃ��̏K�����͂Ȃɂ��v�u���w���̂Ƃ��̍D���ȋ��H�̃��j���[�͉����v���A�q�������������������Ă�����e��搶����l��l�ɕ����ă����ɂƂ�A���\���܂����B���\�̎d���ɂ��āA�u�܂��v�u���Ɂv�u�Ō�Ɂv���ӎ����Ęb���悤�ɂ��܂����B���\�������e�̒��ɁA�u�V���N���i�C�Y�h�X�C�~���O�v���K���Ă����搶�������̂ɁA�q�����������������܂����B���\�����q�������̘b���m�[�g�ɂ������胁�������܂����B
�T���Q�X���i�j������E�|�[�g�{�[��
�@�Q�N���̐����ȁu������v������܂��B�����́A�w�Z��Ƃ̂܂��ɂ͂ǂ�Ȏ{�݂₨�X������̂��A�Z�O�w�K�ɏo�����܂����B�w����́u�R���f�B�C�C�_�v�u�_�Ƃ̂l����v�̂Ƃ���ɍs���܂����B���i�A�������ɍs���ꏊ�����߂Č��āA�����S�����������Ƃ����������܂����B��U�A�w�Z�ɖ߂��ċx�e�����Ă���A�l����̔��Ɍ������܂����B���イ��A�`���Q���������Ă���n�E�X�ɓ��点�Ă������������B�܂��A�g���N�^�[�������Ă��������܂����B�n�E�X�̒��̍앨�ł́A������������@�ɂ��āA���������̃~�j�g�}�g�Ɣ�r���Ȃ���w�т܂����B�Ō�Ƀ`���Q���̎����l��l�ɂ��������܂����B�����b�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�S�N���̑̈�u�|�[�g�{�[���v�ł��B�������n�܂�O�ɁA�{�[���p�X���Ȃ���悤�Ƀ`�[�����Ƃɗ��K�����Ă��܂����B�݂�ȃ`�[�����[�N�悭���K���Ă��܂��B�����ł́A�ォ��̃p�X�����łȂ��A�o�E���h�p�X�����āA���������Ȃ���S�[����ڎw���Ă��܂����B�{�[���������ĂR���ȏ�����Ă���q�������Ƃ������������ɐ������A���̂��Ƃɂ��đf���Ɏ���Ă���t�F�A�v���[������܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�Q�N���̐����ȁu������v������܂��B�����́A�w�Z��Ƃ̂܂��ɂ͂ǂ�Ȏ{�݂₨�X������̂��A�Z�O�w�K�ɏo�����܂����B�w����́u�R���f�B�C�C�_�v�u�_�Ƃ̂l����v�̂Ƃ���ɍs���܂����B���i�A�������ɍs���ꏊ�����߂Č��āA�����S�����������Ƃ����������܂����B��U�A�w�Z�ɖ߂��ċx�e�����Ă���A�l����̔��Ɍ������܂����B���イ��A�`���Q���������Ă���n�E�X�ɓ��点�Ă������������B�܂��A�g���N�^�[�������Ă��������܂����B�n�E�X�̒��̍앨�ł́A������������@�ɂ��āA���������̃~�j�g�}�g�Ɣ�r���Ȃ���w�т܂����B�Ō�Ƀ`���Q���̎����l��l�ɂ��������܂����B�����b�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�S�N���̑̈�u�|�[�g�{�[���v�ł��B�������n�܂�O�ɁA�{�[���p�X���Ȃ���悤�Ƀ`�[�����Ƃɗ��K�����Ă��܂����B�݂�ȃ`�[�����[�N�悭���K���Ă��܂��B�����ł́A�ォ��̃p�X�����łȂ��A�o�E���h�p�X�����āA���������Ȃ���S�[����ڎw���Ă��܂����B�{�[���������ĂR���ȏ�����Ă���q�������Ƃ������������ɐ������A���̂��Ƃɂ��đf���Ɏ���Ă���t�F�A�v���[������܂����B
�T���Q�W���i���j��䐼���̈�ՁE�n���h�x����…�E�J���t���˂��
�@�C���t���G���U���ɂ��w�����ʼn����ɂȂ�����䐼���w�Z�̑̈�Ղ��A�{���J�Â���܂����B���Ɛ��̐��k�����́A�݂Ȓ��w���̕\��ɂȂ�A�J��ɎQ������p�͂ƂĂ��z�X���������܂����B�����e���g�̒��ɂ��邱�Ƃ��������P�N���́A���U���Ă���܂����B�ƂĂ����ꂵ�������ł��B�܂��A�킴�킴�e���g�܂ň��A�ɂ����Ă��ꂽ���Ɛ������܂����B�������܂����B�������蒆�w�Z�̈���Ƃ��āA�ꐶ�����^�c�Ɍg����Ă��܂����B�搶����������w�����A���̒��ɋʂ�����u�ǂ������ʓ���v�A�Q�N���́u�䕗�̖ځv�܂Ō������Ă��������܂����B���ʂ��Ō�ɂȂ�ԐF�c�ɑ��āA�ق��̐c�A���F�c���������艞�����Ă���p���A���炵�������ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@���w���̉��y�ł��B�u�h���~�̉́v���n���h�x���ʼn��t���Ă��܂����B�����̓���^�C�~���O���W�����Ė炷���Ƃ��ł��܂����B�܂��A�����̒S�����鉹���ł��܂����B���Y�����w�Ԃ��Ƃ����łȂ��A�݂�ȂŃn���h�x���̉��t�̃N�I���e�B�����߂�悤�ɂ��܂����B
�@�R�N���̐}�H�f���ł��B�u�����ăJ���t���˂�ǁv�ł́A�ԁA���A�A�ԁv�̂S�F�����S�y���������킹�āA�悭���˂�ƁA�V�����F���ł��܂����B�悤�������킹����A���܂荬�����Ƀ}�[�u���͗l���y������ƂЂ���ɂQ�F���˂����Ă݂���ƁA���낢��ƍH�v�����Ă��܂����B��͎��i�˂��A�ƂĂ������������ł��B�c�Ύs�O�ł��B������͂��Ƃ̕��ւ̊��ӂ̃��b�Z�[�W������܂���
 �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@
�@�C���t���G���U���ɂ��w�����ʼn����ɂȂ�����䐼���w�Z�̑̈�Ղ��A�{���J�Â���܂����B���Ɛ��̐��k�����́A�݂Ȓ��w���̕\��ɂȂ�A�J��ɎQ������p�͂ƂĂ��z�X���������܂����B�����e���g�̒��ɂ��邱�Ƃ��������P�N���́A���U���Ă���܂����B�ƂĂ����ꂵ�������ł��B�܂��A�킴�킴�e���g�܂ň��A�ɂ����Ă��ꂽ���Ɛ������܂����B�������܂����B�������蒆�w�Z�̈���Ƃ��āA�ꐶ�����^�c�Ɍg����Ă��܂����B�搶����������w�����A���̒��ɋʂ�����u�ǂ������ʓ���v�A�Q�N���́u�䕗�̖ځv�܂Ō������Ă��������܂����B���ʂ��Ō�ɂȂ�ԐF�c�ɑ��āA�ق��̐c�A���F�c���������艞�����Ă���p���A���炵�������ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@���w���̉��y�ł��B�u�h���~�̉́v���n���h�x���ʼn��t���Ă��܂����B�����̓���^�C�~���O���W�����Ė炷���Ƃ��ł��܂����B�܂��A�����̒S�����鉹���ł��܂����B���Y�����w�Ԃ��Ƃ����łȂ��A�݂�ȂŃn���h�x���̉��t�̃N�I���e�B�����߂�悤�ɂ��܂����B
�@�R�N���̐}�H�f���ł��B�u�����ăJ���t���˂�ǁv�ł́A�ԁA���A�A�ԁv�̂S�F�����S�y���������킹�āA�悭���˂�ƁA�V�����F���ł��܂����B�悤�������킹����A���܂荬�����Ƀ}�[�u���͗l���y������ƂЂ���ɂQ�F���˂����Ă݂���ƁA���낢��ƍH�v�����Ă��܂����B��͎��i�˂��A�ƂĂ������������ł��B�c�Ύs�O�ł��B������͂��Ƃ̕��ւ̊��ӂ̃��b�Z�[�W������܂���
�T���Q�V���i�j�������K�i�U�N�j�E���j�w�K�i���w�N�j
�@�U�N���́A�����g�����������K�����܂����B�X�N�����u���G�b�O�ł��B�o�^�[��������ꂼ��I�����Ē������܂����B�Ή������厖�ł����A�ǂ�����ɂł��܂����B�o���オ�����ǂ���A�u�H�ׂĂ��������I�v�ƁA�\�z�����Ă��Ȃ����U��������܂����B�u�����́H�v�u�͂��I�v���肪�������������܂����B�����ڂǂ���A�ƂĂ��������������ł��B�����������܂ł����B�݂�Ȃŋ��͂��č�����X�N�����u���G�b�O�ł����B
�@���j�w�K�Q��ڂł��B�ߑO���A���w���A��w�N�A���w�N�͋������A�ߌ�A���w�N�͍Z�������������܂����B��T�͂��̋t�������̂ŁA���͍��w�N�̌��������܂����B�����ɖ��ʂ��Ȃ��A���������w�N�ł��B�w�Z�Ő��j�w�K�����Ă����Ƃ��́A���̗₽��������A�u�n���̃V�����[�v�Ǝq�������͕\�����Ă��܂����BY���A�u�����͓V���̃V�����[�ł��I�v�ƁA�����̂��肪�������������Ă��܂����B�R�̃O���[�v�ɕ�����āA���K���d�˂Ă��܂����B��������̖J�߃V�����[�𗁂тĂ���q�������́A���̐��j�w�K�ɂ��ӗ~�I�ł����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�U�N���́A�����g�����������K�����܂����B�X�N�����u���G�b�O�ł��B�o�^�[��������ꂼ��I�����Ē������܂����B�Ή������厖�ł����A�ǂ�����ɂł��܂����B�o���オ�����ǂ���A�u�H�ׂĂ��������I�v�ƁA�\�z�����Ă��Ȃ����U��������܂����B�u�����́H�v�u�͂��I�v���肪�������������܂����B�����ڂǂ���A�ƂĂ��������������ł��B�����������܂ł����B�݂�Ȃŋ��͂��č�����X�N�����u���G�b�O�ł����B
�@���j�w�K�Q��ڂł��B�ߑO���A���w���A��w�N�A���w�N�͋������A�ߌ�A���w�N�͍Z�������������܂����B��T�͂��̋t�������̂ŁA���͍��w�N�̌��������܂����B�����ɖ��ʂ��Ȃ��A���������w�N�ł��B�w�Z�Ő��j�w�K�����Ă����Ƃ��́A���̗₽��������A�u�n���̃V�����[�v�Ǝq�������͕\�����Ă��܂����BY���A�u�����͓V���̃V�����[�ł��I�v�ƁA�����̂��肪�������������Ă��܂����B�R�̃O���[�v�ɕ�����āA���K���d�˂Ă��܂����B��������̖J�߃V�����[�𗁂тĂ���q�������́A���̐��j�w�K�ɂ��ӗ~�I�ł����B
�T���Q�U���i���j���y����E��ʈ��S����
�@���N�x���߂Ẳ��y�������܂����B�Ȗڂ́u�Z�́v�ł��B����̏�ɂ́A�����ō������Ƃ��ĂU�N��������ł��܂��B���ꂢ�ȉ̐����I���A�w�������Ă���܂����B�߂��ẮA�u�w�Ȃ̎R�x���ӎ����ĉ̂����v�ł��B�u�l����`�ӂ��́`�v�̂Ƃ������Ɉӎ����ĉ̂��܂����B�P�N�����o�����Ắu�Z�́v�����ꂢ�ȉ̐��ʼn̂��Ă����㋉���̐��ɍ��킹�ĉ̂����Ƃ��ł��܂����B
�@�����Ԍx�@���A��ʎw��������A��ʈ��S����̕��X�A�s�����̕��X�����Z���A��ʈ��S���������{����܂����B��w�N�́A�M���̈Ӗ��A���f�̎d�����w�т܂����B���w�N�A���w�N�́A�_�����ڂƂ��āu�u�^�x���T�n���v�i�u���[�L�E�^�C���E�x���E�T�h���E�n���h���E���˔E���C�g�j�Ɗo���邱�ƂŁA�ԈႦ�邱�ƂȂ��_�����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��m�F���܂����B�_���̍ۂ́A�ڂŌ���A�����A�e���ɐG��邱�Ƃ���ł��邱�Ƃ������Ă��������܂����B���]�Ԃł́A�E���āA�����Ă̑��ɁA��������Ă̂������ڂ��lj��ł����B��ʎ��̂O���p�����Ă���{�Z�ł��B�T���͓��ɂP�N������ʎ��̂ɑ������Ƃ����������ł��B���ꂩ����A���̂��Ƃ��p���ł��܂��悤�A�ЂƂ�ЂƂ��ʃ��[��������Ăق����ł��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@���N�x���߂Ẳ��y�������܂����B�Ȗڂ́u�Z�́v�ł��B����̏�ɂ́A�����ō������Ƃ��ĂU�N��������ł��܂��B���ꂢ�ȉ̐����I���A�w�������Ă���܂����B�߂��ẮA�u�w�Ȃ̎R�x���ӎ����ĉ̂����v�ł��B�u�l����`�ӂ��́`�v�̂Ƃ������Ɉӎ����ĉ̂��܂����B�P�N�����o�����Ắu�Z�́v�����ꂢ�ȉ̐��ʼn̂��Ă����㋉���̐��ɍ��킹�ĉ̂����Ƃ��ł��܂����B
�@�����Ԍx�@���A��ʎw��������A��ʈ��S����̕��X�A�s�����̕��X�����Z���A��ʈ��S���������{����܂����B��w�N�́A�M���̈Ӗ��A���f�̎d�����w�т܂����B���w�N�A���w�N�́A�_�����ڂƂ��āu�u�^�x���T�n���v�i�u���[�L�E�^�C���E�x���E�T�h���E�n���h���E���˔E���C�g�j�Ɗo���邱�ƂŁA�ԈႦ�邱�ƂȂ��_�����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��m�F���܂����B�_���̍ۂ́A�ڂŌ���A�����A�e���ɐG��邱�Ƃ���ł��邱�Ƃ������Ă��������܂����B���]�Ԃł́A�E���āA�����Ă̑��ɁA��������Ă̂������ڂ��lj��ł����B��ʎ��̂O���p�����Ă���{�Z�ł��B�T���͓��ɂP�N������ʎ��̂ɑ������Ƃ����������ł��B���ꂩ����A���̂��Ƃ��p���ł��܂��悤�A�ЂƂ�ЂƂ��ʃ��[��������Ăق����ł��B
�T���Q�S���i�y�j��䒆�̈��
�@�{�Z�̑��Ɛ���������䒆�i�w���Ă��܂��B�����͑̈�Ղ�����܂����B�V�S�z����܂������A
�������������Ȃ��̈�Ղ�����ɂ͂��傤�ǂ悢�C���ł����B���k�����̎�ڂ͊�]���ł��B�u�`�F�b�R���ʓ���v�u�w���R�����[�v�u�A�X���`�b�N�����[�v���ɏo�ꂵ�Ă��܂����B���Ɛ����e���g�ɂ��鎄�̂Ƃ���܂ŁA���A�ɗ��Ă���܂����B�ƂĂ����ꂵ�������ł��B���ׂĒ��w�����������������ō��グ�Ă��銴��������܂����B���p���Ő��삵���̈�Ղ̃X���[�K���u�E��簐i�v���P���Ă��܂����B
 �@
�@

�@�{�Z�̑��Ɛ���������䒆�i�w���Ă��܂��B�����͑̈�Ղ�����܂����B�V�S�z����܂������A
�������������Ȃ��̈�Ղ�����ɂ͂��傤�ǂ悢�C���ł����B���k�����̎�ڂ͊�]���ł��B�u�`�F�b�R���ʓ���v�u�w���R�����[�v�u�A�X���`�b�N�����[�v���ɏo�ꂵ�Ă��܂����B���Ɛ����e���g�ɂ��鎄�̂Ƃ���܂ŁA���A�ɗ��Ă���܂����B�ƂĂ����ꂵ�������ł��B���ׂĒ��w�����������������ō��グ�Ă��銴��������܂����B���p���Ő��삵���̈�Ղ̃X���[�K���u�E��簐i�v���P���Ă��܂����B
 �@
�@

�T���Q�R���i���j�������K�EGIGA�X�N�[���K��
�@�T�N���̒������K�B�W���K�C����䥂ł܂����B���肱�Ԃ��ȏ�̑傫�ȃW���K�C���������Ă��Ă���q�����܂����B�܂��́A��̕������s�[���[�łƂ�A��Ő�܂��B�����邨����w���ۂ߂ăW���K�C�����������āA����Ƃ�����ŃW���K�C�����܂����B�S�����ɂ���̂ɁA���Ԃ�������܂����B��ł�Ƃ��ɂ́A�W���K�C���������邮�炢�ɐ�������悤�ɂ��A�q�������͐T�d�ɐ��̗ʂ��C�ɂ��Ă��܂����B�������Ă���A�W���K�C�������炩���Ȃ��Ă��邩�m�F���Ă���A���H���܂����B���������d�オ�����ǂ��قƂ�ǂł��B�����߂̃W���K�C�������炩���Ȃ��Ă����̂ň��S�����̂ł����A���H���Ă݂�ƁA�傫�ȃW���K�C���͏��������߂������悤�ł��B������w�т�����܂����B
�@�ӂ��ݖ�s����ψ����AGIGA�X�N�[���劲�ł���|�{�搶�����Z���A�{�Z�̃^�u���b�g�w�K�ɂ����Ƃ����w�����Ă��������܂����B�Q�N���͍���ȂŁu�X�C�~�[�v�̏����̊��z���m�[�g�ɏ��������̂��^�u���b�g�ŎB�e���A�X�N�[���^�N�g�ɒ�o���銈���A�R�N���͗��ȂŁu�z�E�Z���J�̊ώ@�v�ł����B�u�z�E�Z���J�v���B�e���A�C�Â������e���X�N�[���^�N�g�ɋL�q���Ă��܂����B�U�N���́A�u���v�̎��ԂƐS�̎��ԁv�̐��������ނɂ��āA�M�҂̎咣�Ǝ���𑨂��A�O���[�v�Řb�����������Ȃ���A�����̍l�����X�N�[���^�N�g�ɒ�o���銈�������Ă��܂����B�|�{�搶����A����I�Ƀ^�u���b�g�w�K���g�ɂ��Ă��邱�Ƃ�]�����Ă��������܂����B���Ƃ̖ڕW�ɔ��邽�߂̗L���Ȏ藧�ĂƂ��č�������p���Ăق����Ƃ��w�������������܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@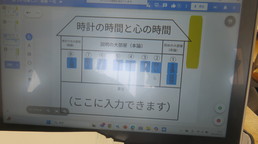
 �@
�@
�@�T�N���̒������K�B�W���K�C����䥂ł܂����B���肱�Ԃ��ȏ�̑傫�ȃW���K�C���������Ă��Ă���q�����܂����B�܂��́A��̕������s�[���[�łƂ�A��Ő�܂��B�����邨����w���ۂ߂ăW���K�C�����������āA����Ƃ�����ŃW���K�C�����܂����B�S�����ɂ���̂ɁA���Ԃ�������܂����B��ł�Ƃ��ɂ́A�W���K�C���������邮�炢�ɐ�������悤�ɂ��A�q�������͐T�d�ɐ��̗ʂ��C�ɂ��Ă��܂����B�������Ă���A�W���K�C�������炩���Ȃ��Ă��邩�m�F���Ă���A���H���܂����B���������d�オ�����ǂ��قƂ�ǂł��B�����߂̃W���K�C�������炩���Ȃ��Ă����̂ň��S�����̂ł����A���H���Ă݂�ƁA�傫�ȃW���K�C���͏��������߂������悤�ł��B������w�т�����܂����B
�@�ӂ��ݖ�s����ψ����AGIGA�X�N�[���劲�ł���|�{�搶�����Z���A�{�Z�̃^�u���b�g�w�K�ɂ����Ƃ����w�����Ă��������܂����B�Q�N���͍���ȂŁu�X�C�~�[�v�̏����̊��z���m�[�g�ɏ��������̂��^�u���b�g�ŎB�e���A�X�N�[���^�N�g�ɒ�o���銈���A�R�N���͗��ȂŁu�z�E�Z���J�̊ώ@�v�ł����B�u�z�E�Z���J�v���B�e���A�C�Â������e���X�N�[���^�N�g�ɋL�q���Ă��܂����B�U�N���́A�u���v�̎��ԂƐS�̎��ԁv�̐��������ނɂ��āA�M�҂̎咣�Ǝ���𑨂��A�O���[�v�Řb�����������Ȃ���A�����̍l�����X�N�[���^�N�g�ɒ�o���銈�������Ă��܂����B�|�{�搶����A����I�Ƀ^�u���b�g�w�K���g�ɂ��Ă��邱�Ƃ�]�����Ă��������܂����B���Ƃ̖ڕW�ɔ��邽�߂̗L���Ȏ藧�ĂƂ��č�������p���Ăق����Ƃ��w�������������܂����B
�T���Q�Q���i�j�Ƃ����э��E���߂Ẵ^�u���b�g
�@�x�ݎ��ԂɂP�N���̋����ɂ���ƁA�u���A�Ƃ����э��������I�v�ƁA�����Ă���܂����B�q�����������X�Ƒ��ۂɏW�܂�A�u�ق�Ƃ����I�v�u���������v�u�����肽���ȁv�ƃ��N���N���Ă��܂����B���̗l�q���A�Ƃ����э��̌W�̕��ɂ��`������ƁA�ƂĂ����Ă��܂����B
�@�{�̎���A�Ԃ����������Ă��������A�q�������͂��������Ƃ����э��̎���ɏW�܂�܂����B�Ƃ����э��̑��ɂ��A�S�̃N���A�P�[�X�ɓ����Ă��邽������̖{������܂����B�Ɗԋx�݂ɂ́A���w�N�̎q�ǂ��������W�܂�A�����̖{����Ă��܂����B
�@�P�N���́A���߂ă^�u���b�g���g�p���܂����B�����܂łɁA�x��������������A�J�E���g��\�߃Z�b�e�B���O���Ă��������܂����B�{�̂𗧂��グ�A�J�����A�v���ɍs���܂ł��A�������Ԃ�������܂������A�S�����A�T�K�I�̊ώ@�̂��߂ɁA�B�e�����܂����B�傫���Ȃ����o�t�A�o�t�̘e����o�Ă����{�t�̂�����̂�����܂����B�J�����@�\����r�f�I�ɂȂ��Ă��܂��ƁA�u���`���I�v�Ƃ����������琺���������܂��B���̂��тɁA��������`�������Ă��������܂����B�����ɎB�e�ł���ƁA�u���Č��āI�v�Ǝq�������������ɂ��Ă���܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�x�ݎ��ԂɂP�N���̋����ɂ���ƁA�u���A�Ƃ����э��������I�v�ƁA�����Ă���܂����B�q�����������X�Ƒ��ۂɏW�܂�A�u�ق�Ƃ����I�v�u���������v�u�����肽���ȁv�ƃ��N���N���Ă��܂����B���̗l�q���A�Ƃ����э��̌W�̕��ɂ��`������ƁA�ƂĂ����Ă��܂����B
�@�{�̎���A�Ԃ����������Ă��������A�q�������͂��������Ƃ����э��̎���ɏW�܂�܂����B�Ƃ����э��̑��ɂ��A�S�̃N���A�P�[�X�ɓ����Ă��邽������̖{������܂����B�Ɗԋx�݂ɂ́A���w�N�̎q�ǂ��������W�܂�A�����̖{����Ă��܂����B
�@�P�N���́A���߂ă^�u���b�g���g�p���܂����B�����܂łɁA�x��������������A�J�E���g��\�߃Z�b�e�B���O���Ă��������܂����B�{�̂𗧂��グ�A�J�����A�v���ɍs���܂ł��A�������Ԃ�������܂������A�S�����A�T�K�I�̊ώ@�̂��߂ɁA�B�e�����܂����B�傫���Ȃ����o�t�A�o�t�̘e����o�Ă����{�t�̂�����̂�����܂����B�J�����@�\����r�f�I�ɂȂ��Ă��܂��ƁA�u���`���I�v�Ƃ����������琺���������܂��B���̂��тɁA��������`�������Ă��������܂����B�����ɎB�e�ł���ƁA�u���Č��āI�v�Ǝq�������������ɂ��Ă���܂����B
�T���Q�P���i���j��������E���������сi�V�̗̓e�X�g�j�E�傫������ׁE�҂�����
�@�ی������ψ���̎q���������A�̉H�̕�����������Ă��܂����B����A�����ŕ�����Ăъ|���Ă����̂ŁA�Q�U�l�̎q����������������Ă���܂����B�o�Z���Ă����P�N���́A��ɂ��������肵�߂Ă��āA�u����…�v�Ƃǂ̂悤�ɕ�������炢�����A�킩�炸�ɖK�˂Ă��܂������A��������̎q����������������Ă���l�q�����āA����������������邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�Q�N���̑̈�ł́A�V�̗̓e�X�g�̗��������т����Ă��܂����B�j�q�����蒆�ŁA���q�͗��K�ł��B���̗l�q���ʐ^�Ɏ��߂�ƁA�Œ���ł���u�Ԃ��B�e�ł��āA�q���������u�����I�v�Ɗ������グ�Ă��܂����B
�@�P�N���̎Z���ł��B�u���̑傫������ׁv�����Ă��܂����B�q���������y�A�ɂȂ�A�u���[�́v�ŁA�����������Ă���J�[�h���o�������܂����B����ɁA�Z�ɐԐF���h���Ă��鐔�̃J�[�h�Ɛ����̃J�[�h���u���[�́v�ŏo�������u�傫������ׁv�����āA���̊T�O�̗�����[�߂܂����B
�@���Ȍ��f�̑҂�����…�R�N���̒j�q�́A�L���łȂ����C�s�m�̂悤�ɁA�݂�ȋF��̃|�[�Y�����Ă��܂����B�ƂĂ��Â��ɑ҂��Ƃ��ł��܂����B���h�ł����B�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�ی������ψ���̎q���������A�̉H�̕�����������Ă��܂����B����A�����ŕ�����Ăъ|���Ă����̂ŁA�Q�U�l�̎q����������������Ă���܂����B�o�Z���Ă����P�N���́A��ɂ��������肵�߂Ă��āA�u����…�v�Ƃǂ̂悤�ɕ�������炢�����A�킩�炸�ɖK�˂Ă��܂������A��������̎q����������������Ă���l�q�����āA����������������邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�Q�N���̑̈�ł́A�V�̗̓e�X�g�̗��������т����Ă��܂����B�j�q�����蒆�ŁA���q�͗��K�ł��B���̗l�q���ʐ^�Ɏ��߂�ƁA�Œ���ł���u�Ԃ��B�e�ł��āA�q���������u�����I�v�Ɗ������グ�Ă��܂����B
�@�P�N���̎Z���ł��B�u���̑傫������ׁv�����Ă��܂����B�q���������y�A�ɂȂ�A�u���[�́v�ŁA�����������Ă���J�[�h���o�������܂����B����ɁA�Z�ɐԐF���h���Ă��鐔�̃J�[�h�Ɛ����̃J�[�h���u���[�́v�ŏo�������u�傫������ׁv�����āA���̊T�O�̗�����[�߂܂����B
�@���Ȍ��f�̑҂�����…�R�N���̒j�q�́A�L���łȂ����C�s�m�̂悤�ɁA�݂�ȋF��̃|�[�Y�����Ă��܂����B�ƂĂ��Â��ɑ҂��Ƃ��ł��܂����B���h�ł����B�@
�T���Q�O���i�j���j�w�K
�@�ӂ��ݖ�s�ł́A��N�x���炷�ׂĂ̏����w�Z�ŁA�O���{�݂ł̐��j�w�K�����{���Ă��܂��B�{�Z�̉��́A�u���l�T���X�V����v�ł��B1�N���ɂƂ��ẮA���߂Ă̍Z�O�w�K�ɂȂ�܂��B�o�X�ɏ���ďo������̂ŁA�����烏�N���N�ł����B���w�҂����邱�Ƃ���A�w�Z�����c�̕ی�҂̕��X�Ɍ��������Ă��������܂����B�܂��A�o�X���~�肽�Ƃ��납��A�X�C�~���O�X�N�[���܂ł̈��S�w���A��w�N�̒��ւ�������`�������������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�X�C�~���O�X�N�[���́A�V�����[���������A�������R�O�D�T�x�ł����̂ŁA���K�Ȋ��̂��ƂŁA���Ƃ�i�߂��܂����B���l�T���X�V����̕����A���j�w�K�����Ă���ԁA�q��������������Ă��������܂����B���w���A��w�N�̎��Ƃ��I����Ă���A���l�T���X�V����̌W�̕��X���A�v�[���t���A���ړ����Ă�������A���w�N�p�A���w�N�p�ɗl�ς��ł��B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�o�f�B�A�n���h�T�C���̊m�F�A�w�N�ɂ���Ċw�K���e�͈Ⴂ�܂����A��w�N�́A����������Ă���A�����̃����O�E���A�����W�����P���A�搶�ւ݂̂������Q�[���A�����v�[�������s���܂����B�w�K���I�����q�������́u�y�����������I�v�Ƃ݂�Ȗ����C�ł����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�ӂ��ݖ�s�ł́A��N�x���炷�ׂĂ̏����w�Z�ŁA�O���{�݂ł̐��j�w�K�����{���Ă��܂��B�{�Z�̉��́A�u���l�T���X�V����v�ł��B1�N���ɂƂ��ẮA���߂Ă̍Z�O�w�K�ɂȂ�܂��B�o�X�ɏ���ďo������̂ŁA�����烏�N���N�ł����B���w�҂����邱�Ƃ���A�w�Z�����c�̕ی�҂̕��X�Ɍ��������Ă��������܂����B�܂��A�o�X���~�肽�Ƃ��납��A�X�C�~���O�X�N�[���܂ł̈��S�w���A��w�N�̒��ւ�������`�������������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�X�C�~���O�X�N�[���́A�V�����[���������A�������R�O�D�T�x�ł����̂ŁA���K�Ȋ��̂��ƂŁA���Ƃ�i�߂��܂����B���l�T���X�V����̕����A���j�w�K�����Ă���ԁA�q��������������Ă��������܂����B���w���A��w�N�̎��Ƃ��I����Ă���A���l�T���X�V����̌W�̕��X���A�v�[���t���A���ړ����Ă�������A���w�N�p�A���w�N�p�ɗl�ς��ł��B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�o�f�B�A�n���h�T�C���̊m�F�A�w�N�ɂ���Ċw�K���e�͈Ⴂ�܂����A��w�N�́A����������Ă���A�����̃����O�E���A�����W�����P���A�搶�ւ݂̂������Q�[���A�����v�[�������s���܂����B�w�K���I�����q�������́u�y�����������I�v�Ƃ݂�Ȗ����C�ł����B
�T���P�X���i���j�V���g�������E���������E������胁���̍H�v�A
�@�S�N�����V�̗̓e�X�g�̎�ڂ̈�ł���u�V���g�������v�����Ă��܂����B���̊Ԋu�ňꉹ���d�q������܂��B�d�q���i�h���~�t�@�\���V�h�j�����ɖ�܂łɂQ�O����̐��ɒB���A���������邩�A�G�ꂽ��A���̏�Ō�����ς��铮����J��Ԃ��܂��B�������邽�тɓd�q���������Ȃ�܂��B�q�������́A��N�̐���葽�����邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ă��܂��B�u���K�����������邱�Ƃ��ł����I�v�ƂƂĂ����ł��܂����B�l�������Ȃ��Ȃ�ƁA�q����������u�����`�I�v�̉����̐����傫���Ȃ�܂��B�S�N���łP�O�O�����o�܂����B�悭�����܂����B
�@���������ł́A�S�Z�������Z���A�����݂̂Ƃ���̎G�����Ƃ�܂����B�J�オ�肾�����̂ŁA��������̑�����邱�Ƃ��ł��܂����B���Ƃ̕��X�ɂ������͂��������A��Ϗ�����܂����B�܂��A�q�������̏������I��������ɁA�ی�҂̕��X�Ƀg�C���ɓ���Ƃ���̏������A�����|���������͂��������܂����B�㗚���オ�����Ȃ�A�ƂĂ����ꂢ�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�S�N���̍���Ŏ��g��ł���u������胁���̂��ӂ��v�ł́A�R�l�̎q�����������x�݂ɗ������܂����B�u���w���̂Ƃ����ӂ��������̂͂Ȃ�ł����v�u�搶�ɓ{��ꂽ���ƂŊo���Ă��邱�Ƃ͂���܂����v���A���Ԃ�����Ȃ��قǎ��₳��܂����B���������Ă݂�ƁA�ӏ������ɂ�����A���t�̂ݏ�������A�K�v�ȏ�����̑I�����āA�܂Ƃ߂邱�Ƃ����H���Ă��܂����B�u���\�̂Ƃ��Ɍ��ɍs���ˁv�Ɠ`����ƁA�u���Ă��������I�v�ƌ��C�ɓ����Ă���܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�S�N�����V�̗̓e�X�g�̎�ڂ̈�ł���u�V���g�������v�����Ă��܂����B���̊Ԋu�ňꉹ���d�q������܂��B�d�q���i�h���~�t�@�\���V�h�j�����ɖ�܂łɂQ�O����̐��ɒB���A���������邩�A�G�ꂽ��A���̏�Ō�����ς��铮����J��Ԃ��܂��B�������邽�тɓd�q���������Ȃ�܂��B�q�������́A��N�̐���葽�����邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ă��܂��B�u���K�����������邱�Ƃ��ł����I�v�ƂƂĂ����ł��܂����B�l�������Ȃ��Ȃ�ƁA�q����������u�����`�I�v�̉����̐����傫���Ȃ�܂��B�S�N���łP�O�O�����o�܂����B�悭�����܂����B
�@���������ł́A�S�Z�������Z���A�����݂̂Ƃ���̎G�����Ƃ�܂����B�J�オ�肾�����̂ŁA��������̑�����邱�Ƃ��ł��܂����B���Ƃ̕��X�ɂ������͂��������A��Ϗ�����܂����B�܂��A�q�������̏������I��������ɁA�ی�҂̕��X�Ƀg�C���ɓ���Ƃ���̏������A�����|���������͂��������܂����B�㗚���オ�����Ȃ�A�ƂĂ����ꂢ�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�S�N���̍���Ŏ��g��ł���u������胁���̂��ӂ��v�ł́A�R�l�̎q�����������x�݂ɗ������܂����B�u���w���̂Ƃ����ӂ��������̂͂Ȃ�ł����v�u�搶�ɓ{��ꂽ���ƂŊo���Ă��邱�Ƃ͂���܂����v���A���Ԃ�����Ȃ��قǎ��₳��܂����B���������Ă݂�ƁA�ӏ������ɂ�����A���t�̂ݏ�������A�K�v�ȏ�����̑I�����āA�܂Ƃ߂邱�Ƃ����H���Ă��܂����B�u���\�̂Ƃ��Ɍ��ɍs���ˁv�Ɠ`����ƁA�u���Ă��������I�v�ƌ��C�ɓ����Ă���܂����B
�T���P�T���i�j �A�T�K�I�̊ώ@�E�V�̗̓e�X�g�E�����^�C���E������胁���̂��ӂ��@
�@�u�t���ς��o�Ă�����B�v�u�ڂ��̂͂S���o�Ă�B�v�Ǝq���������܂����A�T�K�I�̎킩��A��������̑o�t������o���Ă��܂����B�����ȉ肪�y�̒�����͋�������ƐL�тĂ���l�q�ɁA�q�������͂ЂƂ݂��P�����Ȃ���ώ@���Ă��܂����B���ɂ́u�Ȃ�ł������͏o�ĂȂ��̂��ȁv�Ɖ肪�o�Ă��Ȃ����̂ɂ����Ɩڂ������Ă��l���Ă���q�����āA���R�Ƃ̊ւ��̒��Łu�C�Â��v��u�^��v�����͂�����Ă���Ɗ����܂����B
�@�S�N���́A�V�̗̓e�X�g�́u�\�t�g�{�[�������v�����Ă��܂����B�͂����ς��̂��g���ē����܂����BY���u�ڂ��͂P�W�������܂����v�u�����L�^���ˁv�Ƃ���������Ƃ��^����ƁA�u�l����͂R�T���������Ă��v�ƗF�B�̋L�^���ق߂������Ă��܂����B�����̎��Ă�͂�t�������邱�ƁA�q�������݂͂�Ȋ撣���Ă��܂��B
�@���N�x���߂Ắu�����^�C���v�ł��B�{�Z�ł́A�P�N������U�N���܂ł���̔ǂɂȂ�u�c���芈���v�Ɏ��g��ł��܂��B�V�т�𗬊�����ʂ��āA�w�N���z�����ւ����ɂ��Ă��܂��B�����́A�����̐i�ߕ���������A�Ō�ɋL�O�ʐ^���B��܂����B���������ōl���A��������Ȃ��瓮���p���ƂĂ���ۓI�ł����B
�@�S�N���̍���ł́A�u�厖�Ȃ��Ƃ𗎂Ƃ����ɕ������v�Ƃ����P������A�E�����̐搶���փC���^�r���[�����Ă��܂����B�u�Ȃ��A���w�Z�̐搶�ɂȂ����̂ł����v�u���̎d�������Ă��Ă��ꂵ���Ǝv�������Ƃ͂Ȃ�ł����v���A����ǂ����₪��������p�ӂ���Ă��܂����B�������j���ɃC���^�r���[����܂��B








�@�u�t���ς��o�Ă�����B�v�u�ڂ��̂͂S���o�Ă�B�v�Ǝq���������܂����A�T�K�I�̎킩��A��������̑o�t������o���Ă��܂����B�����ȉ肪�y�̒�����͋�������ƐL�тĂ���l�q�ɁA�q�������͂ЂƂ݂��P�����Ȃ���ώ@���Ă��܂����B���ɂ́u�Ȃ�ł������͏o�ĂȂ��̂��ȁv�Ɖ肪�o�Ă��Ȃ����̂ɂ����Ɩڂ������Ă��l���Ă���q�����āA���R�Ƃ̊ւ��̒��Łu�C�Â��v��u�^��v�����͂�����Ă���Ɗ����܂����B
�@�S�N���́A�V�̗̓e�X�g�́u�\�t�g�{�[�������v�����Ă��܂����B�͂����ς��̂��g���ē����܂����BY���u�ڂ��͂P�W�������܂����v�u�����L�^���ˁv�Ƃ���������Ƃ��^����ƁA�u�l����͂R�T���������Ă��v�ƗF�B�̋L�^���ق߂������Ă��܂����B�����̎��Ă�͂�t�������邱�ƁA�q�������݂͂�Ȋ撣���Ă��܂��B
�@���N�x���߂Ắu�����^�C���v�ł��B�{�Z�ł́A�P�N������U�N���܂ł���̔ǂɂȂ�u�c���芈���v�Ɏ��g��ł��܂��B�V�т�𗬊�����ʂ��āA�w�N���z�����ւ����ɂ��Ă��܂��B�����́A�����̐i�ߕ���������A�Ō�ɋL�O�ʐ^���B��܂����B���������ōl���A��������Ȃ��瓮���p���ƂĂ���ۓI�ł����B
�@�S�N���̍���ł́A�u�厖�Ȃ��Ƃ𗎂Ƃ����ɕ������v�Ƃ����P������A�E�����̐搶���փC���^�r���[�����Ă��܂����B�u�Ȃ��A���w�Z�̐搶�ɂȂ����̂ł����v�u���̎d�������Ă��Ă��ꂵ���Ǝv�������Ƃ͂Ȃ�ł����v���A����ǂ����₪��������p�ӂ���Ă��܂����B�������j���ɃC���^�r���[����܂��B
�T���P�S���i���j �������K�i�T�N���j�E���̂܂Ƃ܂�������悤
�@�T�N���ɂƂ��ẮA���߂Ă̖{�i�I�Ȓ������K�ł��B����̎��K�ł́A�̂��Ђ�������u�߂ȂǁA�G�߂̖���g�����V���v���ʼnh�{�����Ղ�̗����ɒ��킵�܂����B��̎g�����A��̐��A�̈������ȂǁA��ЂƂ̓���J�Ɋw�тȂ���A�O���[�v�ŋ��͂��č�Ƃ�i�߂Ă����܂����B
�@�͂��߂́A�����邨�����������Ă����q���������A�搶��F�B�Ɗm�F�������Ȃ���A���M�̂���\��ɁB�u����Ȃɂ������ʂ�v��،�����K����́uS�搶�ɂ����悤�v�ƌ����Ă��������̂ł����A�����ō�������̂́A�y�����ƐH�ׂĂ��܂����B�����̋Z�p�����łȂ��A���͂��邱�Ƃ̑���A�H�ו��ւ̊��ӁA�h�{�ւ̗����ȂǁA��������̊w�т�����܂����B�u�Ƃł����I�v�Ƃ����q����������������o�Ă���Ƃ����ł��B
�@�Q�N���̉��y�ł́A�u�͂��̂����Łv�i�Q���q�j�Ɓu���ʂ��̂������v�i�R���q�j�̋Ȃ�̂����Ȃ���A�̂�����A�蔏�q�������肵�āA���̈Ⴂ���������w�K�����Ă��܂����B�Q���q�͕��������Ȃ郊�Y���A�R���q�͉��ɑ̂���炵�����Ȃ郊�Y���Ǝq���������C�Â��āA���̂܂Ƃ܂�������Ă��܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�T�N���ɂƂ��ẮA���߂Ă̖{�i�I�Ȓ������K�ł��B����̎��K�ł́A�̂��Ђ�������u�߂ȂǁA�G�߂̖���g�����V���v���ʼnh�{�����Ղ�̗����ɒ��킵�܂����B��̎g�����A��̐��A�̈������ȂǁA��ЂƂ̓���J�Ɋw�тȂ���A�O���[�v�ŋ��͂��č�Ƃ�i�߂Ă����܂����B
�@�͂��߂́A�����邨�����������Ă����q���������A�搶��F�B�Ɗm�F�������Ȃ���A���M�̂���\��ɁB�u����Ȃɂ������ʂ�v��،�����K����́uS�搶�ɂ����悤�v�ƌ����Ă��������̂ł����A�����ō�������̂́A�y�����ƐH�ׂĂ��܂����B�����̋Z�p�����łȂ��A���͂��邱�Ƃ̑���A�H�ו��ւ̊��ӁA�h�{�ւ̗����ȂǁA��������̊w�т�����܂����B�u�Ƃł����I�v�Ƃ����q����������������o�Ă���Ƃ����ł��B
�@�Q�N���̉��y�ł́A�u�͂��̂����Łv�i�Q���q�j�Ɓu���ʂ��̂������v�i�R���q�j�̋Ȃ�̂����Ȃ���A�̂�����A�蔏�q�������肵�āA���̈Ⴂ���������w�K�����Ă��܂����B�Q���q�͕��������Ȃ郊�Y���A�R���q�͉��ɑ̂���炵�����Ȃ郊�Y���Ǝq���������C�Â��āA���̂܂Ƃ܂�������Ă��܂����B
�T���P�R���i�j�@���̂ق�����E���b����E�Z�����K��
�@�u���傤���傪�~�܂��Ă��邩�猩�Ă݂āI�v�ƁA�P�N����M�������Ăт܂����B�ڂ��Â炵�Č��Ă݂�ƁA�����V���`���E���r�I���ɂƂ܂��Ă��܂����B���������߂̃`���E�ł��B�悭�����܂����B�u�ق�Ƃ��ˁB�v��l�ł������̗l�q�����߂Ă��܂����B
�@�P�N���̐����Ȃł́A�u�A�T�K�I�v����Ă��܂��B��܂��������̂ŁA�����̐���肪���ۂɂȂ��Ă��܂��B��������������̂P�N�������������Ă��܂����B�u�����肪�o�Ă��Ă���v�u�܂��肪�o�ĂȂ�����A�߂��Ⴈ��������v�ƒ�����Ă��܂��B���ׂł́A�Q�N�����u�~�j�g�}�g�v�̐��������Ă��܂����B
�@���b����ł́A�T���̐����ڕW�u�b���������肫�����v�ɂ��āAM�搶���S�����Ă��������܂����B�u�����v�̊�������A�ڂƎ��ƐS�Œ����܂��Ƃ��b���������܂����B�b���悭�����ƁA�����u�ł���v�悤�ɂȂ�A�F�B�Ɓu���ǂ��v�ɂȂ�A�������Ƃ��������邱�Ƃ������Ă��������܂����B
�@�P���ԖځA�P�N���ƂU�N���̗���������܂����B�U�N���͐}�H�Łu���C�ɓ���̏ꏊ�v�̊G��`���Ƃ������ƂŁA�Z������I��Ŏʐ^���B��ɗ��܂����B�P�N���͐����ȂŎq�����������Łu�w�Z�T���v�ł��B�q�������̂ЂƂ݂��P���Ă��܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�u���傤���傪�~�܂��Ă��邩�猩�Ă݂āI�v�ƁA�P�N����M�������Ăт܂����B�ڂ��Â炵�Č��Ă݂�ƁA�����V���`���E���r�I���ɂƂ܂��Ă��܂����B���������߂̃`���E�ł��B�悭�����܂����B�u�ق�Ƃ��ˁB�v��l�ł������̗l�q�����߂Ă��܂����B
�@�P�N���̐����Ȃł́A�u�A�T�K�I�v����Ă��܂��B��܂��������̂ŁA�����̐���肪���ۂɂȂ��Ă��܂��B��������������̂P�N�������������Ă��܂����B�u�����肪�o�Ă��Ă���v�u�܂��肪�o�ĂȂ�����A�߂��Ⴈ��������v�ƒ�����Ă��܂��B���ׂł́A�Q�N�����u�~�j�g�}�g�v�̐��������Ă��܂����B
�@���b����ł́A�T���̐����ڕW�u�b���������肫�����v�ɂ��āAM�搶���S�����Ă��������܂����B�u�����v�̊�������A�ڂƎ��ƐS�Œ����܂��Ƃ��b���������܂����B�b���悭�����ƁA�����u�ł���v�悤�ɂȂ�A�F�B�Ɓu���ǂ��v�ɂȂ�A�������Ƃ��������邱�Ƃ������Ă��������܂����B
�@�P���ԖځA�P�N���ƂU�N���̗���������܂����B�U�N���͐}�H�Łu���C�ɓ���̏ꏊ�v�̊G��`���Ƃ������ƂŁA�Z������I��Ŏʐ^���B��ɗ��܂����B�P�N���͐����ȂŎq�����������Łu�w�Z�T���v�ł��B�q�������̂ЂƂ݂��P���Ă��܂����B
�T���P�Q���i���j�@�㕟���������قƂ̘A�g�E�ӂ�ӂ��C��łȂ���
�@���߂ĖѕM������R�N���B�㕟���������قŁu�����T�[�N�������v������Ă���F���܂����}�����A�q�ǂ������ɖѕM�̎w�������Ă��������܂����B�q�ǂ������́A�M�̎�������p���A�����̌`�̐������ȂǁA��ЂƂ��J�ɋ����Ă��������Ȃ���A�^���ȕ\��Ŏ��g��ł��܂����B���i�̎��Ƃł͂Ȃ��Ȃ����킦�Ȃ��u�����������y�����v��u�������������Ƃ���C�����v����ށA�M�d�Ȏ��ԂƂȂ�܂����B�K���{�����e�B�A�̊F���܂��A��l�ЂƂ�ɗD�������������Ă�������p���ƂĂ���ۓI�ŁA�q�ǂ����������S���Ċw�Ԃ��Ƃ��ł����悤�ł��B�����������b�ɂȂ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�R�N���̐}�H�ł��B�傫�ȃr�j�[���܂ɋ�C�����߂āA�ӂ�ӂ킵���S�n�𖡂킢�܂����B�{�[���̂悤�ɓ����Ă݂���A�F�B�̑܂ƂȂ��Ă݂���A�V�ѕ����H�v���܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@���߂ĖѕM������R�N���B�㕟���������قŁu�����T�[�N�������v������Ă���F���܂����}�����A�q�ǂ������ɖѕM�̎w�������Ă��������܂����B�q�ǂ������́A�M�̎�������p���A�����̌`�̐������ȂǁA��ЂƂ��J�ɋ����Ă��������Ȃ���A�^���ȕ\��Ŏ��g��ł��܂����B���i�̎��Ƃł͂Ȃ��Ȃ����킦�Ȃ��u�����������y�����v��u�������������Ƃ���C�����v����ށA�M�d�Ȏ��ԂƂȂ�܂����B�K���{�����e�B�A�̊F���܂��A��l�ЂƂ�ɗD�������������Ă�������p���ƂĂ���ۓI�ŁA�q�ǂ����������S���Ċw�Ԃ��Ƃ��ł����悤�ł��B�����������b�ɂȂ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�R�N���̐}�H�ł��B�傫�ȃr�j�[���܂ɋ�C�����߂āA�ӂ�ӂ킵���S�n�𖡂킢�܂����B�{�[���̂悤�ɓ����Ă݂���A�F�B�̑܂ƂȂ��Ă݂���A�V�ѕ����H�v���܂����B
�T���P�O���i�y�j�ӂ��݂�T�^�f�[�i�w�Z���J�E�����n���P���j
�@ �~�J�̒��A�����p�̒��A�����̕ی�҂̊F�l�ɂ����Z���������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�@�q�������́A�����Ƃ͏����Ⴄ�ْ����̒��ł��A�ꐶ�����Ɋw�K�Ɏ��g�ގp�������Ă���܂����B�P�N���ɂƂ��ẮA���߂Ă̎��ƎQ�ςɁA���x�����������Ă��Ƃ̕������Ă��邩�ǂ����m�F�����Ă��܂����B�u���ɗ��Ă���Ă��邩�ȁv�Ƃ����S�̐�����������悤�ł����B�O���w���҂Ƃ��āA�ӂ��ݖ�s���玕�ȉq���m�̕��X�����ق��A�P�N���A�S�N���Ɏ��Ȏw�������{���Ă��������܂����B�͂Ԃ炵�̑I�ѕ��A�݂͂����̎d�����^�̎��Ǝ��u���V�̖͌^���g�p���Ȃ���A�킩��₷�������Ă��������܂����B�T�N���̉��y�ł́A�O���[�v�ʼn��y�̕\���̍H�v��b�������p���قق��܂����v���܂����B�����̎��Ƃ����Ă���w�N�������A�ی�҂̕��X���ꏏ�ɂȂ�A�ꏏ�ɍl���Ă��������܂����B
�@����̓����ɂ����āA�s�R�ҐN�����������������Ƃ���A�������ł̈��S�m�ۂ���s�����m�F���܂����B���̌�A�ی�҂̊F�l�ɂ��}���ɗ��Ă��������A�����n���P�����s���܂����B�ی�҂̊F�l�ɂ��A�v������ÂȑΉ������Ă��������A�X���[�Y�Ȉ����n�����s���܂����B
�@������A������ɔ����ē���������S�ӎ��̂����߁A�w�Z�A�ƒ낪�A�g���Ďq�������̖������̐��Â���ɓw�߂Ă܂���܂��B�����͂��������܂����ی�҂̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B


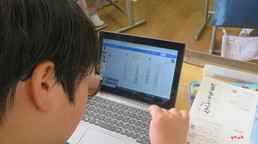





�@ �~�J�̒��A�����p�̒��A�����̕ی�҂̊F�l�ɂ����Z���������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�@�q�������́A�����Ƃ͏����Ⴄ�ْ����̒��ł��A�ꐶ�����Ɋw�K�Ɏ��g�ގp�������Ă���܂����B�P�N���ɂƂ��ẮA���߂Ă̎��ƎQ�ςɁA���x�����������Ă��Ƃ̕������Ă��邩�ǂ����m�F�����Ă��܂����B�u���ɗ��Ă���Ă��邩�ȁv�Ƃ����S�̐�����������悤�ł����B�O���w���҂Ƃ��āA�ӂ��ݖ�s���玕�ȉq���m�̕��X�����ق��A�P�N���A�S�N���Ɏ��Ȏw�������{���Ă��������܂����B�͂Ԃ炵�̑I�ѕ��A�݂͂����̎d�����^�̎��Ǝ��u���V�̖͌^���g�p���Ȃ���A�킩��₷�������Ă��������܂����B�T�N���̉��y�ł́A�O���[�v�ʼn��y�̕\���̍H�v��b�������p���قق��܂����v���܂����B�����̎��Ƃ����Ă���w�N�������A�ی�҂̕��X���ꏏ�ɂȂ�A�ꏏ�ɍl���Ă��������܂����B
�@����̓����ɂ����āA�s�R�ҐN�����������������Ƃ���A�������ł̈��S�m�ۂ���s�����m�F���܂����B���̌�A�ی�҂̊F�l�ɂ��}���ɗ��Ă��������A�����n���P�����s���܂����B�ی�҂̊F�l�ɂ��A�v������ÂȑΉ������Ă��������A�X���[�Y�Ȉ����n�����s���܂����B
�@������A������ɔ����ē���������S�ӎ��̂����߁A�w�Z�A�ƒ낪�A�g���Ďq�������̖������̐��Â���ɓw�߂Ă܂���܂��B�����͂��������܂����ی�҂̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B
�T���X���i���j�������̓��E���낢��G�̋�����E�q�i�̂���
�@�����ψ�������Q�����Ắu�������̓��v�ł��B�v��ψ��̑��ɂ��A��������̎q���������Q�����Ă���܂����B����́A�������ɂ��ӂ�Ă��܂����B
�@4�N���̐}�H�ł��B�u���낢��G�̋�����v�̒P���ł́A�G�̋���X�g���[�Ő����Ĕ������A�X�|���W�Ń|���|���ƒ@������A�y�b�g�{�g���̃L���b�v�ȂǁA�g�߂ȗp��ɊG�̋�����āA�\�����Ă��܂����B�n�[�g�^�₤���܂��̌`�̎���̓��������āA�\���̍H�v�����Ă���q�����܂����B
�@�߂������m�点�ł��B�R�N�P�g�̑��ۂɂ���c�o���̑��ɂ́A�����c�o�������ł��Ă��܂������A���܂ɂ��q�i�����܂�Ă����悤�ł��B�u�Z���搶�I�Ɍ���Ȃ�����I�v�Ǝq������������T���Ă��܂����B�Ȃ�ƁA�R�H�̃q�i�������痎���Ă��܂��A�S���Ȃ��Ă����̂ł��B��ꔭ���͎q�������ł��B�u�������낤�I�v�Ǝq���������̈ĂŁA�������������̈�ً߂��̍̉Ԕ��ɖ��߂܂����B����Ȃ̂ŁA�q���������߂��̂��Ԃ�E��ŁA����炵���`�ɐ����܂����B�݂�Ȃ�3�H�̖������F��܂����B��C��3�H�̃q�i�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����e�c�o���̋C�������v���Ƃ������܂�܂���B�q�������̏��ɂ��ƁA����2�H�̃q�i�����̒��ɂ���悤�ł��B���������痎���邱�ƂȂ��A�����Ɉ���Ăق����ƋF�����ł��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�����ψ�������Q�����Ắu�������̓��v�ł��B�v��ψ��̑��ɂ��A��������̎q���������Q�����Ă���܂����B����́A�������ɂ��ӂ�Ă��܂����B
�@4�N���̐}�H�ł��B�u���낢��G�̋�����v�̒P���ł́A�G�̋���X�g���[�Ő����Ĕ������A�X�|���W�Ń|���|���ƒ@������A�y�b�g�{�g���̃L���b�v�ȂǁA�g�߂ȗp��ɊG�̋�����āA�\�����Ă��܂����B�n�[�g�^�₤���܂��̌`�̎���̓��������āA�\���̍H�v�����Ă���q�����܂����B
�@�߂������m�点�ł��B�R�N�P�g�̑��ۂɂ���c�o���̑��ɂ́A�����c�o�������ł��Ă��܂������A���܂ɂ��q�i�����܂�Ă����悤�ł��B�u�Z���搶�I�Ɍ���Ȃ�����I�v�Ǝq������������T���Ă��܂����B�Ȃ�ƁA�R�H�̃q�i�������痎���Ă��܂��A�S���Ȃ��Ă����̂ł��B��ꔭ���͎q�������ł��B�u�������낤�I�v�Ǝq���������̈ĂŁA�������������̈�ً߂��̍̉Ԕ��ɖ��߂܂����B����Ȃ̂ŁA�q���������߂��̂��Ԃ�E��ŁA����炵���`�ɐ����܂����B�݂�Ȃ�3�H�̖������F��܂����B��C��3�H�̃q�i�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����e�c�o���̋C�������v���Ƃ������܂�܂���B�q�������̏��ɂ��ƁA����2�H�̃q�i�����̒��ɂ���悤�ł��B���������痎���邱�ƂȂ��A�����Ɉ���Ăق����ƋF�����ł��B
�T���W���i�j��ʌ��w�͊w�K�����E�݂���̉ԁE�����̃c�o���E�ψ����
�@���N�A�{���Ŏ��{���Ă��邱�̒����́A�q��������l��l�́u�w�͂̐L�сv�𑪂邱�Ƃ��ł���u���ȂɊւ��钲���v�u�w�K�ɑ���ӗ~��w�K���@�A�ƒ�ł̐����K�����Ɋւ��鎿�⒲���v������܂��B�^�u���b�g�[���������p����CBT�������s���܂����B�����͂U�N�����R���Ԃ����Ď��{���܂����B
�@�ی����O�ɂ���u�݂���v�̖ɉԂ���������炢�Ă��܂��B���k�n�̂���₩�ȍ��肪�L�����Ă��܂��B��N�͉Ԃ̐������Ȃ������̂ŁA���N�͂�������̎����Ȃ邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B
�@�����̃c�o���́A��������Ǝp�������Ă���܂����B�����Ɠ������ɂ��܂��B�q�i�̊�͌����܂��A������������A���ɂ���̂�������܂���B
�@���|����ψ���ł́A�J�������̐��������ꂢ�ɑ|�����Ă��܂����B������|�����Ă���ԁA�͂�ꂽ���̒��ŃJ���������U���ł���悤�ɂ��܂����B�������ꂢ�ɂȂ����u���߂����v�́A���ꂵ�����ȃJ�����ڐ��ł��B






 �@
�@

�@���N�A�{���Ŏ��{���Ă��邱�̒����́A�q��������l��l�́u�w�͂̐L�сv�𑪂邱�Ƃ��ł���u���ȂɊւ��钲���v�u�w�K�ɑ���ӗ~��w�K���@�A�ƒ�ł̐����K�����Ɋւ��鎿�⒲���v������܂��B�^�u���b�g�[���������p����CBT�������s���܂����B�����͂U�N�����R���Ԃ����Ď��{���܂����B
�@�ی����O�ɂ���u�݂���v�̖ɉԂ���������炢�Ă��܂��B���k�n�̂���₩�ȍ��肪�L�����Ă��܂��B��N�͉Ԃ̐������Ȃ������̂ŁA���N�͂�������̎����Ȃ邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B
�@�����̃c�o���́A��������Ǝp�������Ă���܂����B�����Ɠ������ɂ��܂��B�q�i�̊�͌����܂��A������������A���ɂ���̂�������܂���B
�@���|����ψ���ł́A�J�������̐��������ꂢ�ɑ|�����Ă��܂����B������|�����Ă���ԁA�͂�ꂽ���̒��ŃJ���������U���ł���悤�ɂ��܂����B�������ꂢ�ɂȂ����u���߂����v�́A���ꂵ�����ȃJ�����ڐ��ł��B
�T���V���i���j�@�A�x�����̒��ɁE�킽�������̏Z�ލ�ʌ��E���g�͉��������Ă���H
�@�w���O�ɂ͉��Ҋ����炫�n�߂܂����B�����A�w�Z�����c�ł����b�ɂȂ��Ă���n���H���A�u�A�x���́i�������j�ł��Ȃ���������…�v�ƁA�V���߂����痎���t�|�������Ă��������܂����B�u�C�ɂȂ�������Ăˁv�ƁA�������ɂ��ӂ�Ă��܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�S�N���̎Љ�ł��B�u�킽�������̏Z�ލ�ʌ��v���w�K���Ă��܂��B��ʌ��̉w���p�҃����L���O�ł́A��{�w����ԑ��������̂ł����A�u�������ݒn�͉Y�a�Ȃ̂ɁA�Ȃ�ő�{�̕����l���������̂���…�v�Ƃ����^�₪�o�܂����B����Ɓu��{�ɂ͐V��������Ԃ��邩�炶��Ȃ����ȁv�Ƃ����ӌ����o�܂����B�w�K�̒��ŋ^�₪���܂�A�q���������瓚���ɂȂ���Ԃ₫���o�����ƂŁA�S�C�͂��̂��Ƃ�]�����Ă��܂����B�O���Ől���������s�ɂ͐Ԏ��ł��̎s���Z�ň͂�ł��܂��B�����͉w���p�����L���O�ŏo���s����ň݂͂܂����B�������牽���C�Â����Ƃ͂Ȃ����Ɣ���B�q�������̍l���Ŏ��Ƃ��i��ł��܂����B
�@��T�A�w�Z�����c��I���Z���𐴑|���Ă����������Ƃ��ɁAI����쐬�̎��̃����h�Z���B���̒��ɂ́A�܂莆�ł������u������v�������Ă��܂����B������N�C�Y�`���ɂ��āA���̕����ŗ������Ƃ���A�T�N���̎q���������A�����������ď��~���ɏ����Ă��鎆�̃����h�Z�����J���Ă��܂����B�S�[���f���E�B�[�N�O�̘b�ł������A���̓��e���o���Ă��Ă���ă����h�Z���̒��������Ă���܂����B���肪�Ƃ��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@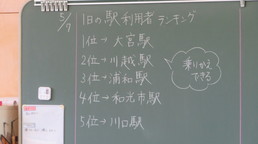
 �@
�@
�@�w���O�ɂ͉��Ҋ����炫�n�߂܂����B�����A�w�Z�����c�ł����b�ɂȂ��Ă���n���H���A�u�A�x���́i�������j�ł��Ȃ���������…�v�ƁA�V���߂����痎���t�|�������Ă��������܂����B�u�C�ɂȂ�������Ăˁv�ƁA�������ɂ��ӂ�Ă��܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�S�N���̎Љ�ł��B�u�킽�������̏Z�ލ�ʌ��v���w�K���Ă��܂��B��ʌ��̉w���p�҃����L���O�ł́A��{�w����ԑ��������̂ł����A�u�������ݒn�͉Y�a�Ȃ̂ɁA�Ȃ�ő�{�̕����l���������̂���…�v�Ƃ����^�₪�o�܂����B����Ɓu��{�ɂ͐V��������Ԃ��邩�炶��Ȃ����ȁv�Ƃ����ӌ����o�܂����B�w�K�̒��ŋ^�₪���܂�A�q���������瓚���ɂȂ���Ԃ₫���o�����ƂŁA�S�C�͂��̂��Ƃ�]�����Ă��܂����B�O���Ől���������s�ɂ͐Ԏ��ł��̎s���Z�ň͂�ł��܂��B�����͉w���p�����L���O�ŏo���s����ň݂͂܂����B�������牽���C�Â����Ƃ͂Ȃ����Ɣ���B�q�������̍l���Ŏ��Ƃ��i��ł��܂����B
�@��T�A�w�Z�����c��I���Z���𐴑|���Ă����������Ƃ��ɁAI����쐬�̎��̃����h�Z���B���̒��ɂ́A�܂莆�ł������u������v�������Ă��܂����B������N�C�Y�`���ɂ��āA���̕����ŗ������Ƃ���A�T�N���̎q���������A�����������ď��~���ɏ����Ă��鎆�̃����h�Z�����J���Ă��܂����B�S�[���f���E�B�[�N�O�̘b�ł������A���̓��e���o���Ă��Ă���ă����h�Z���̒��������Ă���܂����B���肪�Ƃ��B
�T���T���i���j�����̂ڂ�
�@�T�v�ۓ앪�قɂ́A�u���ǂ��̓��v�ɂ��Ȃ�ŁA��������́u�����̂ڂ�v������ɉf���Č��C�ɉj���ł��܂����B�w�Z�^�c���c��ψ���I���A�����Ă������������̂ł��B�{�Z�̎q�����������Ă���Ă��邱�Ƃł��傤�B

�@�T�v�ۓ앪�قɂ́A�u���ǂ��̓��v�ɂ��Ȃ�ŁA��������́u�����̂ڂ�v������ɉf���Č��C�ɉj���ł��܂����B�w�Z�^�c���c��ψ���I���A�����Ă������������̂ł��B�{�Z�̎q�����������Ă���Ă��邱�Ƃł��傤�B

�T���Q���i���j���߂Ẵ^�O���O�r�[�E�ǂ��ǂ��킭�킭�܂�����
�@�^�O���O�r�[�́A���O�r�[�ƈ���ēG�ƂԂ���^�b�N��������܂���B�^�b�N���̑���ɁA���ɂ����u�^�O�v���Ƃ�܂��B�U�߂�Ƃ��̓^�O������Ȃ��悤�ɁA�{�[�����S�[�����C������Γ��_�ɂȂ�܂��B�{�[����������܂ܑ�������A�����Ƀp�X���Ȃ����肵�Ȃ���A���_���߂����čU�߂�Q�[���ł��B�R�N���̓I���G���e�[�����O�Ƃ��āA�u�^�O�Ƃ�S�������v�����܂����B����ƃ^�O�������h���̂ł����A���������̂ł����^�O�����������ꂽ�肵�܂��B�ȉ~�`�̃{�[������≡�A���ɂ���F�B�Ƀp�X�����邱�ƂɊ���邽�߂ɁA�~�`�p�X�Q�[����O��œ�������K�����܂����B�u�^�O�Ƃ�S�������v�u�{�[���̃p�X�v�ɖ����ɂȂ��Ď��g�݂܂����B
�@�Q�N���̐����ȁu�ǂ��ǂ��@�킭�킭�@�܂�����v�ł��B�݂�Ȃ̒��ɂ́A���C�ɓ���̏ꏊ�A�����̂���ꏊ�A�s�v�c�Ɏv���Ă���ꏊ��b�������܂����B�^�u���b�g���g���āA�D���ȏꏊ���Љ�鏀�������Ă��܂����B���͂���̂Ƀ��[�}���ł����ł��Ȃ��̂ŁA�Ђ炪�ȃL�[�{�[�h�ł������ł��܂����B�F�B�ƒT���������ꏊ��b�������܂����B



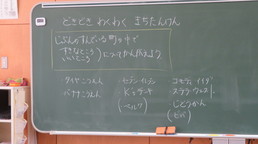

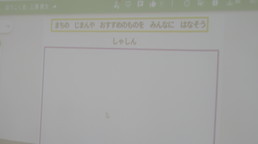
�@�^�O���O�r�[�́A���O�r�[�ƈ���ēG�ƂԂ���^�b�N��������܂���B�^�b�N���̑���ɁA���ɂ����u�^�O�v���Ƃ�܂��B�U�߂�Ƃ��̓^�O������Ȃ��悤�ɁA�{�[�����S�[�����C������Γ��_�ɂȂ�܂��B�{�[����������܂ܑ�������A�����Ƀp�X���Ȃ����肵�Ȃ���A���_���߂����čU�߂�Q�[���ł��B�R�N���̓I���G���e�[�����O�Ƃ��āA�u�^�O�Ƃ�S�������v�����܂����B����ƃ^�O�������h���̂ł����A���������̂ł����^�O�����������ꂽ�肵�܂��B�ȉ~�`�̃{�[������≡�A���ɂ���F�B�Ƀp�X�����邱�ƂɊ���邽�߂ɁA�~�`�p�X�Q�[����O��œ�������K�����܂����B�u�^�O�Ƃ�S�������v�u�{�[���̃p�X�v�ɖ����ɂȂ��Ď��g�݂܂����B
�@�Q�N���̐����ȁu�ǂ��ǂ��@�킭�킭�@�܂�����v�ł��B�݂�Ȃ̒��ɂ́A���C�ɓ���̏ꏊ�A�����̂���ꏊ�A�s�v�c�Ɏv���Ă���ꏊ��b�������܂����B�^�u���b�g���g���āA�D���ȏꏊ���Љ�鏀�������Ă��܂����B���͂���̂Ƀ��[�}���ł����ł��Ȃ��̂ŁA�Ђ炪�ȃL�[�{�[�h�ł������ł��܂����B�F�B�ƒT���������ꏊ��b�������܂����B
�T���P���i�j�����̃c�o���E�����̂ڂ�E�������Ƃ��肻����
�@3�N1�g�̑����猩����c�o���̑��ɂ́A�����Ɠ������ɂ���1�H�̃c�o�������܂��B������������A�������߂Ă���̂�������܂���B���N���c�o���̗l�q��������ۂɂȂ�܂����B
�@���w���ł́A���ǂ��̓��Ɍ����Ắu�����̂ڂ�v�̍�i���������܂����B�F�Â��������ꂢ�ŁA���Ă��邾�����C���o�Ă��܂��B�E���R�̖͗l�������J�ɕ`���Ă���܂��B��C��C�̕\���ڂ��Ⴄ�̂ŁA���ꂼ��̌��������Ă��܂��B
�@4�N���̉��y�u�������Ƃ��肻����v�ł��B���Ճn�[���j�J���l�A�O���[�v�ŗ��K���Ă���̂ł����A�F�B���m�����Ƃ悢���t�ɂȂ邽�߂̃A�h�o�C�X�����Ă���̂��A���炵���ł��B�r���A�̂̃p�[�g�ƌ��Ճn�[���j�J�̃p�[�g�ɕ������̂ŁA���t���₩�ɂȂ�܂��B�y����ʼn��t�ł��܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@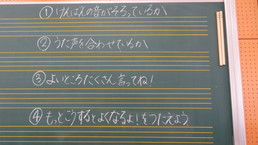
�@3�N1�g�̑����猩����c�o���̑��ɂ́A�����Ɠ������ɂ���1�H�̃c�o�������܂��B������������A�������߂Ă���̂�������܂���B���N���c�o���̗l�q��������ۂɂȂ�܂����B
�@���w���ł́A���ǂ��̓��Ɍ����Ắu�����̂ڂ�v�̍�i���������܂����B�F�Â��������ꂢ�ŁA���Ă��邾�����C���o�Ă��܂��B�E���R�̖͗l�������J�ɕ`���Ă���܂��B��C��C�̕\���ڂ��Ⴄ�̂ŁA���ꂼ��̌��������Ă��܂��B
�@4�N���̉��y�u�������Ƃ��肻����v�ł��B���Ճn�[���j�J���l�A�O���[�v�ŗ��K���Ă���̂ł����A�F�B���m�����Ƃ悢���t�ɂȂ邽�߂̃A�h�o�C�X�����Ă���̂��A���炵���ł��B�r���A�̂̃p�[�g�ƌ��Ճn�[���j�J�̃p�[�g�ɕ������̂ŁA���t���₩�ɂȂ�܂��B�y����ʼn��t�ł��܂����B
�S���R�O���i���j�X�N�[���^�N�g�̊��p�E��̋N�����E�~���~�}�u�K
�@�S�N���̏��ʂ̎��Ƃł́A��ԏ��ɏ������Ǝv����i���X�N�[���^�N�g�ɒ�o���܂����B�X�N�[���^�N�g�A�v���́A�w�K�]�����T�|�[�g����@�\���[�����Ă��܂��B�ʎw������Ɖ��P�ɂȂ��������������Ă��܂��B�����̂߂��āu�_��̕M�g���ɋC�����ď������v�ł��B�߂��Ăɑ��āA�U��Ԃ�ł́u�M��̌����ɋC�����ď��������v�u���̒ʂ蓹�ɋC�����ď��������v�����ȕ]�����܂����B���t�̃^�u���b�g�ɂ́A���X�ƍ�i����o����܂����B
�@�T�N���̑̈�ł��B�V�̗̓e�X�g�Ɍ����āA�����́u��̋N�����v���s���܂����B�y�A�ɂȂ�A������������ĂR�O�b�Ԃɂǂꂭ�炢�̂��N�������Ƃ��ł���̂��A���𐔂��܂����B���K�Ƃ͂����A�q�������͖{�C���o���āA�����ɑ̂��N�����܂����B�u�R�O��v�ƃy�A�̎q��������ƁA�u���`�A���N�Ɠ��������v�Ə������������K����B���N�̋L�^���o���Ă����Ƃ͂������Ǝv���܂����B
�@���ی�̌��C�ł��B�T���Q�O��������{���鐅�j�w�K�Ɍ����āA���E���͐S�x�h���@�𒆐S�Ƃ����~���~�}�u�K��ɎQ�����܂����B�����ԏ��h���̕��X�ɂ��w�������������A�L���̂Ƃ��Ɏ������E�����ǂ̂悤�ȘA���̐��ɂ���̂��A�q�������̖�����邽�߂̐S�x�h���@�̗�����m�F���܂����B�E���̒��ŁA���߂Ă��̌��C�ɎQ��������̂͂��܂���ł������A���N�̌��C�ɂ����Ė������ӎ������������A���h���̕����獂���Z�p�ƒm����`�����A�^���Ɏ��g�݂܂����B
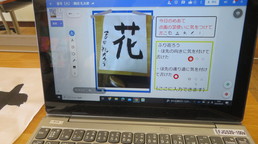 �@
�@
 �@
�@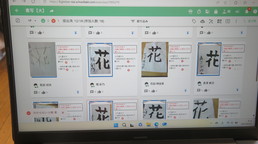
 �@
�@
 �@
�@
�@�S�N���̏��ʂ̎��Ƃł́A��ԏ��ɏ������Ǝv����i���X�N�[���^�N�g�ɒ�o���܂����B�X�N�[���^�N�g�A�v���́A�w�K�]�����T�|�[�g����@�\���[�����Ă��܂��B�ʎw������Ɖ��P�ɂȂ��������������Ă��܂��B�����̂߂��āu�_��̕M�g���ɋC�����ď������v�ł��B�߂��Ăɑ��āA�U��Ԃ�ł́u�M��̌����ɋC�����ď��������v�u���̒ʂ蓹�ɋC�����ď��������v�����ȕ]�����܂����B���t�̃^�u���b�g�ɂ́A���X�ƍ�i����o����܂����B
�@�T�N���̑̈�ł��B�V�̗̓e�X�g�Ɍ����āA�����́u��̋N�����v���s���܂����B�y�A�ɂȂ�A������������ĂR�O�b�Ԃɂǂꂭ�炢�̂��N�������Ƃ��ł���̂��A���𐔂��܂����B���K�Ƃ͂����A�q�������͖{�C���o���āA�����ɑ̂��N�����܂����B�u�R�O��v�ƃy�A�̎q��������ƁA�u���`�A���N�Ɠ��������v�Ə������������K����B���N�̋L�^���o���Ă����Ƃ͂������Ǝv���܂����B
�@���ی�̌��C�ł��B�T���Q�O��������{���鐅�j�w�K�Ɍ����āA���E���͐S�x�h���@�𒆐S�Ƃ����~���~�}�u�K��ɎQ�����܂����B�����ԏ��h���̕��X�ɂ��w�������������A�L���̂Ƃ��Ɏ������E�����ǂ̂悤�ȘA���̐��ɂ���̂��A�q�������̖�����邽�߂̐S�x�h���@�̗�����m�F���܂����B�E���̒��ŁA���߂Ă��̌��C�ɎQ��������̂͂��܂���ł������A���N�̌��C�ɂ����Ė������ӎ������������A���h���̕����獂���Z�p�ƒm����`�����A�^���Ɏ��g�݂܂����B
�S���Q�W���i���j�̈璩��E�͂��߂܂��Ċw�Z
�@���N�x�͂��߂Ă̑̈璩�����܂����B�u�O�ւȂ炦�v�u�C�����v�u�₷�߁v�u�̑����`�ɊJ���v�ȂǁA�W�c�s���̊�{�ɂ��āA�P�N���͂T�C�U�N��������{�ɂ��Ċm�F���܂����B
�@�P�N���̐����Ȃł��B�w�Z�̒����݂�Ȃŕ����Ă߂���A�w�Z�̎{�݂̗l�q��w�Z�������x���Ă���l�����邱�Ƃ𗝉�����w�K�ł��B�S�C�̈����ƂƂ��ɁA�Z�����Ɂu�P�N�P�g�ł��B�v�Ɛ擪�̎q�����������C�悭�����Ă��܂����B�Z�����Ɍf�����Ă���P�N���̎ʐ^�����āA�u�ڂ�������I�v�u�킽���͂ǂ��ɂ���́H�v�Ǝʐ^�ɓB�t���ł����B�Q�g����͗��̍Z���̎ʐ^�����āu���ꂩ�ȁH�v�Ǝ��₳��A�u�O�̍Z���搶�����ł���v�Ɠ�����ƁA�u�ǂ����Ă��Ȃ��Ȃ���������́H�v�u�U�O�܂œ����Ă�߂�ꂽ���A�ق��̊w�Z�ɍs���Ă��܂����Z���搶�����܂��B�v�u�Z���搶�͉��Ȃ́H�v�ƒ����̎��₪��яo���A�S�C�Ǝ��͑�����܂����B�P�N���̌��t�ɂ́A��������܂��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@���N�x�͂��߂Ă̑̈璩�����܂����B�u�O�ւȂ炦�v�u�C�����v�u�₷�߁v�u�̑����`�ɊJ���v�ȂǁA�W�c�s���̊�{�ɂ��āA�P�N���͂T�C�U�N��������{�ɂ��Ċm�F���܂����B
�@�P�N���̐����Ȃł��B�w�Z�̒����݂�Ȃŕ����Ă߂���A�w�Z�̎{�݂̗l�q��w�Z�������x���Ă���l�����邱�Ƃ𗝉�����w�K�ł��B�S�C�̈����ƂƂ��ɁA�Z�����Ɂu�P�N�P�g�ł��B�v�Ɛ擪�̎q�����������C�悭�����Ă��܂����B�Z�����Ɍf�����Ă���P�N���̎ʐ^�����āA�u�ڂ�������I�v�u�킽���͂ǂ��ɂ���́H�v�Ǝʐ^�ɓB�t���ł����B�Q�g����͗��̍Z���̎ʐ^�����āu���ꂩ�ȁH�v�Ǝ��₳��A�u�O�̍Z���搶�����ł���v�Ɠ�����ƁA�u�ǂ����Ă��Ȃ��Ȃ���������́H�v�u�U�O�܂œ����Ă�߂�ꂽ���A�ق��̊w�Z�ɍs���Ă��܂����Z���搶�����܂��B�v�u�Z���搶�͉��Ȃ́H�v�ƒ����̎��₪��яo���A�S�C�Ǝ��͑�����܂����B�P�N���̌��t�ɂ́A��������܂��B
�S���Q�T���i���j����������
�@�T�N���̉ƒ�Ȃł��B�ƒ�Ȏ��ł̊w�K�͏��߂Ăł��B�܂��A�K�X�̌����������āA������ē_����w�K�����܂����B����̎g�����A���A�ЂÂ����ɂ��Ă��w�т܂����B���������O�ɁA�₩��̒��܂�肪�ʂ�Ă��Ȃ����A�m�F���܂����B�₯�ǂȂǁA���S�ɋC�����Ȃ���s���܂����B������킹�āu���������܂��I�v�ƁA�݂�Ȃň��ލg���A�ق������ȂǁA���������ş��ꂽ���́A�ЂƂ�������Ă��������������Ƃł��傤�B
 �@
�@
 �@
�@
�@�T�N���̉ƒ�Ȃł��B�ƒ�Ȏ��ł̊w�K�͏��߂Ăł��B�܂��A�K�X�̌����������āA������ē_����w�K�����܂����B����̎g�����A���A�ЂÂ����ɂ��Ă��w�т܂����B���������O�ɁA�₩��̒��܂�肪�ʂ�Ă��Ȃ����A�m�F���܂����B�₯�ǂȂǁA���S�ɋC�����Ȃ���s���܂����B������킹�āu���������܂��I�v�ƁA�݂�Ȃň��ލg���A�ق������ȂǁA���������ş��ꂽ���́A�ЂƂ�������Ă��������������Ƃł��傤�B
�S���Q�S���i�j�@�t�܂�������E���ԁE�Z�����|�{�����e�B�A�E�}���I���G���e�[�����O
�@�K�i�̂Ƃ���̓��I�ɓ��̉Ԃ��炫�ق����Ă��܂��B���~�����̃c�c�W�̉Ԃ��F�Ƃ�ǂ�ɍ炫�n�߂܂����B���ԏ�ɓ���Ƃ���̍����ɂ́A�u�ɂ��͂珬�v�ƂȂ�悤�A�O�Z��������N����ō���A���Ă�������A�����ɉԂ��炫�n�߂Ă��܂��B���܂����������Ă��������Ă��܂��B
�@�w�Z�����c�ł���n��̕��X���A�����炨�|�������Ă��������Ă��܂��B���j���͑|�����Ȃ����Ȃ̂ŁA�ؗj���ɂ��ꂢ�ɂ��Ă��������̂́A�ƂĂ����肪�����ł��B�q�������̎��ƒ��ɂ��ꂢ�ɂ��Ă��������܂����A�����͎��Ȍ��f���������̂ŁA�q�������͋C�����悭���A�����Ă���܂����B
�@�}���x�������A�P�N���Ɍ����Đ}�����̎g�����ɂ��ăI���G���e�[�����O�����Ă��������܂����B�}�����ł̉߂������A�J�[�h���g�p���Ă̖{�̎���A�Ԃ����������Ă��������܂����B�}�����̓����ɂ́A�S���Ȃ̂ŁA�u�Ƃ������v�Ɋւ���{������������ׂĂ��������Ă��܂����B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@
�@�K�i�̂Ƃ���̓��I�ɓ��̉Ԃ��炫�ق����Ă��܂��B���~�����̃c�c�W�̉Ԃ��F�Ƃ�ǂ�ɍ炫�n�߂܂����B���ԏ�ɓ���Ƃ���̍����ɂ́A�u�ɂ��͂珬�v�ƂȂ�悤�A�O�Z��������N����ō���A���Ă�������A�����ɉԂ��炫�n�߂Ă��܂��B���܂����������Ă��������Ă��܂��B
�@�w�Z�����c�ł���n��̕��X���A�����炨�|�������Ă��������Ă��܂��B���j���͑|�����Ȃ����Ȃ̂ŁA�ؗj���ɂ��ꂢ�ɂ��Ă��������̂́A�ƂĂ����肪�����ł��B�q�������̎��ƒ��ɂ��ꂢ�ɂ��Ă��������܂����A�����͎��Ȍ��f���������̂ŁA�q�������͋C�����悭���A�����Ă���܂����B
�@�}���x�������A�P�N���Ɍ����Đ}�����̎g�����ɂ��ăI���G���e�[�����O�����Ă��������܂����B�}�����ł̉߂������A�J�[�h���g�p���Ă̖{�̎���A�Ԃ����������Ă��������܂����B�}�����̓����ɂ́A�S���Ȃ̂ŁA�u�Ƃ������v�Ɋւ���{������������ׂĂ��������Ă��܂����B

�@
�S���Q�R���i���j�����̃c�o���E���ʁE�����Ă���Ԃ�…
�@�J��ǂ�����Ă��邩�Ǝv������A�c�o���͑��̒��ł����Ɗ������Ă��܂��B�q�i���a�����Ă���A���S�n�̂����悤�Ƀx�b�h������Ă��銴���Ɍ����܂����B
�@�Q�N���̏��ʂł��B�u�������p���A�������������A�������������v�Ə��ʃm�[�g�ɏ�����Ă��܂��B�C�X�Ɋ��Ƃ��Ȃ��̊Ԃ̓O�[���������i�O�[�j�A�ܐ�������Ƃ����ɂ�������i�y�^�j�A�w���͂܂������Ɂi�s���j�u�O�[�s�^�s���v���߂Ċm�F�A�����ĉ��M�̎��������m�F���܂����B�S�������������O�̕������Ă��˂��ɏ����A���̏W���͂͂��炵���������ł��B
�@�U�N���̎Љ�ł��B�����̎q���������������Ă��鎞�Ԃ𗘗p���āA���̑��̎q�������́A�n�}���̒��ɂ���A�Z�Z�������ƒn���������銈�������Ă��܂����B�͂��ߒS�C�������o���܂����B�������܂��̒n����T���̂ł����A�Ȃ��Ȃ�������܂���B�u�������I�v�ƈ�l����ƌ�����ƁA���X�Ɍ����Ă��܂����B���ɁA�q�������������o���܂����B�����Ă��錄�Ԃ̎��Ԃ����������Ă��܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@
�@�J��ǂ�����Ă��邩�Ǝv������A�c�o���͑��̒��ł����Ɗ������Ă��܂��B�q�i���a�����Ă���A���S�n�̂����悤�Ƀx�b�h������Ă��銴���Ɍ����܂����B
�@�Q�N���̏��ʂł��B�u�������p���A�������������A�������������v�Ə��ʃm�[�g�ɏ�����Ă��܂��B�C�X�Ɋ��Ƃ��Ȃ��̊Ԃ̓O�[���������i�O�[�j�A�ܐ�������Ƃ����ɂ�������i�y�^�j�A�w���͂܂������Ɂi�s���j�u�O�[�s�^�s���v���߂Ċm�F�A�����ĉ��M�̎��������m�F���܂����B�S�������������O�̕������Ă��˂��ɏ����A���̏W���͂͂��炵���������ł��B
�@�U�N���̎Љ�ł��B�����̎q���������������Ă��鎞�Ԃ𗘗p���āA���̑��̎q�������́A�n�}���̒��ɂ���A�Z�Z�������ƒn���������銈�������Ă��܂����B�͂��ߒS�C�������o���܂����B�������܂��̒n����T���̂ł����A�Ȃ��Ȃ�������܂���B�u�������I�v�ƈ�l����ƌ�����ƁA���X�Ɍ����Ă��܂����B���ɁA�q�������������o���܂����B�����Ă��錄�Ԃ̎��Ԃ����������Ă��܂����B
�@
�S���Q�Q���i�j���߂Ă̏K���E���߂Ă̋��H
�@�R�N�����珑�ʂ̎��ƂɏK�����n�܂�܂��B�K��������J���ē���̖��O�A�u�����A�g�������w�т܂����B�����́A�������������Ƃ͂��܂���ł������A���߂Ďg�����̂ɋ����ÁX�ł����B�T�����炢�悢�敶���������܂��B
�@�P�N���͍������狋�H�ł��B�h�{���@��M�搶���u���イ���傭���͂��܂��v�̎��Ƃ����܂����B�����̃��j���[�̏Љ�i�܂�p���A�ĕ��̂��܂����|�^�[�W���A�n���o�[�O�A��̃\�e�[�A�����j�ł́A�ǂ�ȐH�ׂ��̂������Ă���̂��A�͂Ăȁi�H�j�{�b�N�X���g���āA�q�������Ƀ{�b�N�X�̒��ɓ����Ă���H�ו����o���Ă��炢�܂����B�܂��A�ǂ̂悤�ɋ��H�Z���^�[�ō���Ă���̂��A�^�P�m�R���т����l�q��Ō��܂����B�R�O�l�łS�O�O�O�l�����̋��H������Ă��������Ă��钲��������B�傫�Ȃ���ɑ�ʂ̏ݖ�������Ɓu�����`���v�Ǝq�������͂т����肵���l�q�ł����B
�@���H�z�V�ł́A�͂��߂ċ��H���ԂɂȂ��Ă���O���[�v�̎q�������́A�y���݂Ȃ���������ْ����Ă��܂������A�S���ɓ����悤�ȗʂŔz�V���邱�Ƃ��ł��܂����B���ԈȊO�̎q�������́A�z�V�܂Ń}�X�N�����Ėق��đ҂��܂��B�z�V���I����Ă���q�͑҂�����Ȃ��悤�Łu�}�X�N�O���Ă����ł����H�v�Ɖ��x���S�C�ɕ����Ă��܂����B�u���������܂��I�v�̂��ƁA�u���������H�v�Ɛq�˂�ƁA�Ƃт�����̏Ί��Ԃ��Ă���܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�R�N�����珑�ʂ̎��ƂɏK�����n�܂�܂��B�K��������J���ē���̖��O�A�u�����A�g�������w�т܂����B�����́A�������������Ƃ͂��܂���ł������A���߂Ďg�����̂ɋ����ÁX�ł����B�T�����炢�悢�敶���������܂��B
�@�P�N���͍������狋�H�ł��B�h�{���@��M�搶���u���イ���傭���͂��܂��v�̎��Ƃ����܂����B�����̃��j���[�̏Љ�i�܂�p���A�ĕ��̂��܂����|�^�[�W���A�n���o�[�O�A��̃\�e�[�A�����j�ł́A�ǂ�ȐH�ׂ��̂������Ă���̂��A�͂Ăȁi�H�j�{�b�N�X���g���āA�q�������Ƀ{�b�N�X�̒��ɓ����Ă���H�ו����o���Ă��炢�܂����B�܂��A�ǂ̂悤�ɋ��H�Z���^�[�ō���Ă���̂��A�^�P�m�R���т����l�q��Ō��܂����B�R�O�l�łS�O�O�O�l�����̋��H������Ă��������Ă��钲��������B�傫�Ȃ���ɑ�ʂ̏ݖ�������Ɓu�����`���v�Ǝq�������͂т����肵���l�q�ł����B
�@���H�z�V�ł́A�͂��߂ċ��H���ԂɂȂ��Ă���O���[�v�̎q�������́A�y���݂Ȃ���������ْ����Ă��܂������A�S���ɓ����悤�ȗʂŔz�V���邱�Ƃ��ł��܂����B���ԈȊO�̎q�������́A�z�V�܂Ń}�X�N�����Ėق��đ҂��܂��B�z�V���I����Ă���q�͑҂�����Ȃ��悤�Łu�}�X�N�O���Ă����ł����H�v�Ɖ��x���S�C�ɕ����Ă��܂����B�u���������܂��I�v�̂��ƁA�u���������H�v�Ɛq�˂�ƁA�Ƃт�����̏Ί��Ԃ��Ă���܂����B
 �@
�@�S���Q�P���i���j�P�N�����}�����E�ӂ��ݖ�s����ψ���K��
�@�U�N���Ǝ�Ȃ��œ��ꂵ���P�N���݂͂�ȏΊ�ł��B�Q�N���u�w�Z�͊y������v�R�N���u�ꏏ�ɗV�ڂ��ˁv�S�N���u���H����������v�T�N���u���w���߂łƂ��v�U�N���u�������Ƃ��͗����Ăˁv�ƁA�e�w�N����P�N���Ɍ����āA���������ȃ��b�Z�[�W������܂����B��������m�������炨���N�C�Y�ł́A�V��̂��ƁA�S�Z�̎q���̐��A���߂����邱�Ƃ��N�C�Y�ɏo�肳��܂����B�����Q�[�����S���ł��܂����B�P�N���́A�u�����Ă���Ƃ��͏����Ăˁv�u���h�ȂP�N���ɂȂ�܂��v�Ƃ͂����茈�ӕ\��������܂����B�݂�Ȃ���傫�Ȕ��肪�����A�Ƃꂭ�������ł����B�v��ψ��̎q�������́A�����͏��߂Đi�s���܂����B�Z�����Ԃ̒��ł̏������撣��܂����B
�@���璷�E����ψ��͂��߂V���̕��X�̊w�Z�{�ݖK�₪����܂����B�V�N�x�n�܂��Ă̎����̗l�q�A�{�݂����邽�߂ł��B�͂��߂ɁA�Z���̊w�Z�o�c���j�̐����A������Ď���A���w�������������܂����B���������������Ď��ƂɎQ�����Ă���l�q�A�{�ݐݔ������Ă��������܂����B�̈�قł́A���O�e�N�m�X�����삵�Ă����������A�u�Z�̂S�ԁv�̐��앨���������育���ɂȂ��Ă��܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�U�N���Ǝ�Ȃ��œ��ꂵ���P�N���݂͂�ȏΊ�ł��B�Q�N���u�w�Z�͊y������v�R�N���u�ꏏ�ɗV�ڂ��ˁv�S�N���u���H����������v�T�N���u���w���߂łƂ��v�U�N���u�������Ƃ��͗����Ăˁv�ƁA�e�w�N����P�N���Ɍ����āA���������ȃ��b�Z�[�W������܂����B��������m�������炨���N�C�Y�ł́A�V��̂��ƁA�S�Z�̎q���̐��A���߂����邱�Ƃ��N�C�Y�ɏo�肳��܂����B�����Q�[�����S���ł��܂����B�P�N���́A�u�����Ă���Ƃ��͏����Ăˁv�u���h�ȂP�N���ɂȂ�܂��v�Ƃ͂����茈�ӕ\��������܂����B�݂�Ȃ���傫�Ȕ��肪�����A�Ƃꂭ�������ł����B�v��ψ��̎q�������́A�����͏��߂Đi�s���܂����B�Z�����Ԃ̒��ł̏������撣��܂����B
�@���璷�E����ψ��͂��߂V���̕��X�̊w�Z�{�ݖK�₪����܂����B�V�N�x�n�܂��Ă̎����̗l�q�A�{�݂����邽�߂ł��B�͂��߂ɁA�Z���̊w�Z�o�c���j�̐����A������Ď���A���w�������������܂����B���������������Ď��ƂɎQ�����Ă���l�q�A�{�ݐݔ������Ă��������܂����B�̈�قł́A���O�e�N�m�X�����삵�Ă����������A�u�Z�̂S�ԁv�̐��앨���������育���ɂȂ��Ă��܂����B
�S���P�W���i���j�P�N���̂���`���E���P��
�@�����A���o�Z����ƂU�N�����P�N���̂���`�������Ă���Ă��܂��B�����h�Z�����J����Ƃ��납��A�����h�Z���̒��̋��ȏ��A�M�����A�����o���ɓ���邱�ƁA�����h�Z�������b�J�[�ɓ���邱�ƁA�P�N�������͈�A�̗��ꂪ�����ԏ��ɂȂ��Ă��܂����B
�@���N�x�A���߂Ă̔��P���ł��B��N���͂��炩���ߖh�Г��Ђ����Ԃ���K�����܂����B�k�x�T���̒n�k���痝�Ȏ�����Ύ����N�������Ƃ����z��ł��B����Ƃ��́A�u�����Ȃ��u�����Ȃ��v�u���ǂ�Ȃ��u�v�u����ׂ�Ȃ��v�u�����Â��Ȃ��v�̓��������Ƃ����u�����������v�����悤�ɂ��܂����B���Ԃ͂T���R�Q�b�B���߂Ăɂ��Ă͑������ł��܂����B�ǂ�����Ύ����N�������̂����A�q�������͕������悭�����Ă��܂����B��������̖�������ԑ�Ȏ��ƁB�Z���A���S��C�̘b���Ō�܂Œ����A�^���Ɏ��g�݂܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�����A���o�Z����ƂU�N�����P�N���̂���`�������Ă���Ă��܂��B�����h�Z�����J����Ƃ��납��A�����h�Z���̒��̋��ȏ��A�M�����A�����o���ɓ���邱�ƁA�����h�Z�������b�J�[�ɓ���邱�ƁA�P�N�������͈�A�̗��ꂪ�����ԏ��ɂȂ��Ă��܂����B
�@���N�x�A���߂Ă̔��P���ł��B��N���͂��炩���ߖh�Г��Ђ����Ԃ���K�����܂����B�k�x�T���̒n�k���痝�Ȏ�����Ύ����N�������Ƃ����z��ł��B����Ƃ��́A�u�����Ȃ��u�����Ȃ��v�u���ǂ�Ȃ��u�v�u����ׂ�Ȃ��v�u�����Â��Ȃ��v�̓��������Ƃ����u�����������v�����悤�ɂ��܂����B���Ԃ͂T���R�Q�b�B���߂Ăɂ��Ă͑������ł��܂����B�ǂ�����Ύ����N�������̂����A�q�������͕������悭�����Ă��܂����B��������̖�������ԑ�Ȏ��ƁB�Z���A���S��C�̘b���Ō�܂Œ����A�^���Ɏ��g�݂܂����B
�S���P�V���i�j�O���ꊈ���E���̌����鉻�E�I���G���e�[�����O�E�ψ����
�@ALT�̐搶�����N�x���ύX�ɂȂ�A�L�����[�搶�̏��߂Ă̎��Ƃł��B�T�N���̊O����ł́A����ɍ��킹�Ȃ��炢�g�̕\�����A�p��ɐe����ł��܂����Bwhat is your name�H�ƃL�����[�搶����q�˂��AMy name is �Z�Z. �ƌ����I��������ƁA���肵��Good job.���g��Thank you.�Ɠ����Ă��܂����B
�@�R�N���̉��y�ł́A�u�䂩���ɂ��邯��v���̂��Ă��܂����B�u�o���f���`��v�̋Ȃ̎R�ł́A���̌����鉻�Ƃ��āA�p���o���[���ŕ\���Ă��܂����B�q���������������悤�ɂ��Ă��܂����B
�@�Q�N���́A�}�����̎g�����̃I���G���e�[�����O������܂����B����̋��ȏ��Ɍf�ڂ���Ă���}�������łɓ����ɏ����Ă��āA�w�K�̈ӗ~�ނ悤�ɍH�v����Ă��܂����B�}�����̖{��T���R�̃~�b�V�����ŁA�q�������͈ꐶ�����Q�[���ɎQ�����Ă��܂����B
�@�T�C�U�N���͏��߂Ă̈ψ���ł��B�T�N���͏����ْ������ʎ����ł����B�ψ����A���ψ�����I�o���܂����B�V���������o�[�ňψ���ɂ�����v�����`���܂����B�q�ǂ������ɂƂ��āA�w�Z���������悭�y�����Ȃ�悤�Ɋw�Z���̎d���S���A�����I�Ɏ��g�ވψ�������A���ꂩ�犈���ɂȂ邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@ALT�̐搶�����N�x���ύX�ɂȂ�A�L�����[�搶�̏��߂Ă̎��Ƃł��B�T�N���̊O����ł́A����ɍ��킹�Ȃ��炢�g�̕\�����A�p��ɐe����ł��܂����Bwhat is your name�H�ƃL�����[�搶����q�˂��AMy name is �Z�Z. �ƌ����I��������ƁA���肵��Good job.���g��Thank you.�Ɠ����Ă��܂����B
�@�R�N���̉��y�ł́A�u�䂩���ɂ��邯��v���̂��Ă��܂����B�u�o���f���`��v�̋Ȃ̎R�ł́A���̌����鉻�Ƃ��āA�p���o���[���ŕ\���Ă��܂����B�q���������������悤�ɂ��Ă��܂����B
�@�Q�N���́A�}�����̎g�����̃I���G���e�[�����O������܂����B����̋��ȏ��Ɍf�ڂ���Ă���}�������łɓ����ɏ����Ă��āA�w�K�̈ӗ~�ނ悤�ɍH�v����Ă��܂����B�}�����̖{��T���R�̃~�b�V�����ŁA�q�������͈ꐶ�����Q�[���ɎQ�����Ă��܂����B
�@�T�C�U�N���͏��߂Ă̈ψ���ł��B�T�N���͏����ْ������ʎ����ł����B�ψ����A���ψ�����I�o���܂����B�V���������o�[�ňψ���ɂ�����v�����`���܂����B�q�ǂ������ɂƂ��āA�w�Z���������悭�y�����Ȃ�悤�Ɋw�Z���̎d���S���A�����I�Ɏ��g�ވψ�������A���ꂩ�犈���ɂȂ邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B
�S���P�U���i���j�w���ڕW���l����E���H�w��
�@�Q�N���ł́A�w�������Ŋw���ڕW���l���Ă��܂����B�w�Z����͊w�K�w���v�̂�w�Z����ڕW�Ɋ�Â��A�q���������t�̎v����肢�荞��Ō��߂���A�w���ɂ�����P�N�Ԃ̖ڕW�ł��B�q���������ǂ�ȃN���X�ɂ������̂��A�^���ɍl���Ă��܂����B�ǂ�ȖڕW�ɂȂ����̂��C�ɂȂ�܂��B
�@�h�{���@��M�搶�́A�ߑO�����H�Z���^�[�ŋ��H������Ă��܂��B�����ɂ͖{�Z�ɗ��āA�e�������܂�苋�H�w�����s���Ă��܂��B�����̃��j���[�́A�₫���A�n�[�g�f�j�b�V���A�n�b�V���|�e�g�A����݃I�����W�A�����ł��B�q���������H�ׂ₷�����j���[�ł��B�u����݃I�����W�̖��͂ǂ����ȁv�u���܂��ł��B�v�u�悩�������B�v�Ɖ�b���Ă��܂����B���łɁA����݃I�����W�������������Ă���q�����܂����BM�搶�́A�q�������̋��H�w����A�����ɋ��H�Z���^�[�ɖ߂�܂��B���H�������ƒ�������Ă��܂��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@
�@�Q�N���ł́A�w�������Ŋw���ڕW���l���Ă��܂����B�w�Z����͊w�K�w���v�̂�w�Z����ڕW�Ɋ�Â��A�q���������t�̎v����肢�荞��Ō��߂���A�w���ɂ�����P�N�Ԃ̖ڕW�ł��B�q���������ǂ�ȃN���X�ɂ������̂��A�^���ɍl���Ă��܂����B�ǂ�ȖڕW�ɂȂ����̂��C�ɂȂ�܂��B
�@�h�{���@��M�搶�́A�ߑO�����H�Z���^�[�ŋ��H������Ă��܂��B�����ɂ͖{�Z�ɗ��āA�e�������܂�苋�H�w�����s���Ă��܂��B�����̃��j���[�́A�₫���A�n�[�g�f�j�b�V���A�n�b�V���|�e�g�A����݃I�����W�A�����ł��B�q���������H�ׂ₷�����j���[�ł��B�u����݃I�����W�̖��͂ǂ����ȁv�u���܂��ł��B�v�u�悩�������B�v�Ɖ�b���Ă��܂����B���łɁA����݃I�����W�������������Ă���q�����܂����BM�搶�́A�q�������̋��H�w����A�����ɋ��H�Z���^�[�ɖ߂�܂��B���H�������ƒ�������Ă��܂��B
�@
�S���P�S���i���j���b����E���R�[�_�[�u�K��
�@��N���ɂƂ��Ă͏��߂Ă̂��b����ł��B���ɐ��ł��܂����B�����͐������w�Z�̂T�P��ڂ̒a�����B�@
�J�Z�L�O���ɍ��킹�āA�{�Z���Ɛ��Ō��U�N���̕ی�҂ł���S����ɁA�����̖{�Z�̗l�q�ɂ��āA���b�����������܂����B
�@�����̘L�����͍��͑��ɂȂ��Ă��āA�����̂�����ꖾ�邢�ł����A�����͑��ł͂Ȃ��ǂ����������ł��B
�Z��ɋ��������Ă��āA���ی�ɗF�B�Ƌ������ɗ��Ă��������ł��B�N���u�͌��݂T�ł��B�N�C�Y�`���ŁA���b��������A�����͂X����܂����B��y�N���u������AS����̓g�����y�b�g��S������Ă����悤�ł��BS����̑��ƃA���o���������Ă��Ă��������܂����B�Ɗԋx�݂ɂ́A�S�N������������Z�����ɗ������A�����̑��ƃA���o�������ɗ��܂����BS����A�M�d�Ȃ��b�����肪�Ƃ��������܂����B
�@�R�N���̉��y�ł��B�R�N������n�܂郊�R�[�_�[�ł����A�{�����R�[�_�[�u�K�����܂����B���̎g�����Ƀ^���M���O�̏d�v���ɂ��ċ����Ă��������܂����B�傫�ȑ������A�����ȑ������ɂ��čl�������A�����炢�̑��̎g���������ׂĂ��ꂢ�ȉ��ł͂Ȃ����ƁA���ꂢ�ȉ����o���Ƃ��߂ɐ�̎g�����ɂ��Ē��J�ɋ����Ă��������܂����B�R�N���͘b�̕����������ł����B���R�[�_�[���F���u�V�v�̉����g���āA���ꂢ�ɏo�����Ƃ��ł��܂����B���ꂩ��A���Ă��ȉ��F�ł��낢��ȋȂ����t���Ăق����ł��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@��N���ɂƂ��Ă͏��߂Ă̂��b����ł��B���ɐ��ł��܂����B�����͐������w�Z�̂T�P��ڂ̒a�����B�@
�J�Z�L�O���ɍ��킹�āA�{�Z���Ɛ��Ō��U�N���̕ی�҂ł���S����ɁA�����̖{�Z�̗l�q�ɂ��āA���b�����������܂����B
�@�����̘L�����͍��͑��ɂȂ��Ă��āA�����̂�����ꖾ�邢�ł����A�����͑��ł͂Ȃ��ǂ����������ł��B
�Z��ɋ��������Ă��āA���ی�ɗF�B�Ƌ������ɗ��Ă��������ł��B�N���u�͌��݂T�ł��B�N�C�Y�`���ŁA���b��������A�����͂X����܂����B��y�N���u������AS����̓g�����y�b�g��S������Ă����悤�ł��BS����̑��ƃA���o���������Ă��Ă��������܂����B�Ɗԋx�݂ɂ́A�S�N������������Z�����ɗ������A�����̑��ƃA���o�������ɗ��܂����BS����A�M�d�Ȃ��b�����肪�Ƃ��������܂����B
�@�R�N���̉��y�ł��B�R�N������n�܂郊�R�[�_�[�ł����A�{�����R�[�_�[�u�K�����܂����B���̎g�����Ƀ^���M���O�̏d�v���ɂ��ċ����Ă��������܂����B�傫�ȑ������A�����ȑ������ɂ��čl�������A�����炢�̑��̎g���������ׂĂ��ꂢ�ȉ��ł͂Ȃ����ƁA���ꂢ�ȉ����o���Ƃ��߂ɐ�̎g�����ɂ��Ē��J�ɋ����Ă��������܂����B�R�N���͘b�̕����������ł����B���R�[�_�[���F���u�V�v�̉����g���āA���ꂢ�ɏo�����Ƃ��ł��܂����B���ꂩ��A���Ă��ȉ��F�ł��낢��ȋȂ����t���Ăق����ł��B
�S���P�R���i���j������̐������w�Z
�@���̏��߂̋Ζ��n�͊�Ύs�ł����B���������s�ł��B����Ύs�ɂ͐������w�Z������܂����B���p�Ŕ����s�ɍs�����A��ɁA�������s���������w�Z�Ɋ��܂����B�{�Z�̃X�N�[���J���[�́u�O���[���v�ł����A���剜�ɏ�����Ă��邳�����s���������w�Z�̕������u�O���[���v�ł��邱�Ƃ������܂����B��������Ă���ɐe�ߊ����킫�܂����B
 �@
�@
�@���̏��߂̋Ζ��n�͊�Ύs�ł����B���������s�ł��B����Ύs�ɂ͐������w�Z������܂����B���p�Ŕ����s�ɍs�����A��ɁA�������s���������w�Z�Ɋ��܂����B�{�Z�̃X�N�[���J���[�́u�O���[���v�ł����A���剜�ɏ�����Ă��邳�����s���������w�Z�̕������u�O���[���v�ł��邱�Ƃ������܂����B��������Ă���ɐe�ߊ����킫�܂����B
 �@
�@
�S���P�P���i���j���Ԓn��w�͒����E�Z��T���E���N�����Ă���܂���
�@��N���ȏ�́A�O�N�Ɋw�K�������e���o�肳�����Ԓn��w�͒����i�Z���j�ɗՂ݂܂����B�W�����čŌ�܂ł�����߂��Ɏ��g�݂܂����B
�@��N�����Z���T�����܂����B�Z��ɂ���V��i�̂ڂ�ڂ��A�Ԃ�A���傤��イ�̂قˁA�W�����O���W���A�Ăڂ����j�A��ԁX�A�������̂����������Ă��܂����B�����ɖ߂��Ă���A���������̂��G�ɕ\���Ă��܂����B�u���傤���ɂ����Ă�ˁB����̓u�����R���ˁv�Ƙb�������Ă���ƁA�u�Z���搶�A���Č��āv�Ƃł����������G�������Ă���āA�������n�܂�܂����B��������Ȃ��Ȃ��o���܂���ł����B�i�j
�@���T��T�ԁA��N�������C�ɓo�Z���Ă���܂����B�ƂĂ����ꂵ���v���Ă��܂��B���ƒ�ł̗�܂��A���x���Ɋ��ӂ��܂��B
�@3�N1�g�̑��ۂɂ���c�o���̑��B���N���c�o��������Ă��܂����B��N�A���������c�o�����߂��Ă����̂ł��傤���B�܂�1�H�ł��B���ꂩ�珙�X�ɑ����āA��N�A���N�̂悤�ɂ܂��q�i�̒a���������邩������܂���B
 �@
�@
 �@
�@
�@
�@��N���ȏ�́A�O�N�Ɋw�K�������e���o�肳�����Ԓn��w�͒����i�Z���j�ɗՂ݂܂����B�W�����čŌ�܂ł�����߂��Ɏ��g�݂܂����B
�@��N�����Z���T�����܂����B�Z��ɂ���V��i�̂ڂ�ڂ��A�Ԃ�A���傤��イ�̂قˁA�W�����O���W���A�Ăڂ����j�A��ԁX�A�������̂����������Ă��܂����B�����ɖ߂��Ă���A���������̂��G�ɕ\���Ă��܂����B�u���傤���ɂ����Ă�ˁB����̓u�����R���ˁv�Ƙb�������Ă���ƁA�u�Z���搶�A���Č��āv�Ƃł����������G�������Ă���āA�������n�܂�܂����B��������Ȃ��Ȃ��o���܂���ł����B�i�j
�@���T��T�ԁA��N�������C�ɓo�Z���Ă���܂����B�ƂĂ����ꂵ���v���Ă��܂��B���ƒ�ł̗�܂��A���x���Ɋ��ӂ��܂��B
�@3�N1�g�̑��ۂɂ���c�o���̑��B���N���c�o��������Ă��܂����B��N�A���������c�o�����߂��Ă����̂ł��傤���B�܂�1�H�ł��B���ꂩ�珙�X�ɑ����āA��N�A���N�̂悤�ɂ܂��q�i�̒a���������邩������܂���B
�@
�S���P�O���i�j�������̓��E�P�N���̉��Z
�@�����P�O���́APTA�̕��X���o�Z�w���Ƃ��Đ���܂ŗ��Ă��������܂��B����ɍ��킹�āA��䒆�w�Z��Ŗ����P�O�����u�������̓��v�Ƃ��āA�q���������o�Z���鎞�Ԃɍ��킹�āA�n��̕��X������芈�������Ă��������Ă��܂��B
�@�����́A�����ψ��̕��X������O�ɂ��炵�Ă��������A�u�������^���v�ɎQ�����Ă��������܂����B�v��ψ��A��\�ψ��ȊO�̎q���������Q�����Ă���܂����B�݂�ȂŌ��C�ɂ����������킵�A�������́u�������v�̃V�����[������܂����B�P�N�����������������ł��܂����B�u���炵����g�ł��ˁv�ƁA�V���������E���́A�����A�ی�ҁA�n��A���E������̂ƂȂ��Ă������^�������Ă���l�q���ق߂Ă���܂����B
�@�P�N���̉��Z�ɂ́A���}�����Ԃ̂��Ƃ̕��X�����炵�Ă��������܂����B�q�������͂��Ƃ̕��X�̊�����Ĉ��S���Ă���悤�ł����B���Z�ǂł̏��߂Ẳ��Z�ł��B�ی�҂̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�����P�O���́APTA�̕��X���o�Z�w���Ƃ��Đ���܂ŗ��Ă��������܂��B����ɍ��킹�āA��䒆�w�Z��Ŗ����P�O�����u�������̓��v�Ƃ��āA�q���������o�Z���鎞�Ԃɍ��킹�āA�n��̕��X������芈�������Ă��������Ă��܂��B
�@�����́A�����ψ��̕��X������O�ɂ��炵�Ă��������A�u�������^���v�ɎQ�����Ă��������܂����B�v��ψ��A��\�ψ��ȊO�̎q���������Q�����Ă���܂����B�݂�ȂŌ��C�ɂ����������킵�A�������́u�������v�̃V�����[������܂����B�P�N�����������������ł��܂����B�u���炵����g�ł��ˁv�ƁA�V���������E���́A�����A�ی�ҁA�n��A���E������̂ƂȂ��Ă������^�������Ă���l�q���ق߂Ă���܂����B
�@�P�N���̉��Z�ɂ́A���}�����Ԃ̂��Ƃ̕��X�����炵�Ă��������܂����B�q�������͂��Ƃ̕��X�̊�����Ĉ��S���Ă���悤�ł����B���Z�ǂł̏��߂Ẳ��Z�ł��B�ی�҂̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂��B
�S���X���i���j�o�Z�̗l�q�E�w�������E��ĉ��Z�E����̈��A
�@���J�̍����ƂĂ����ꂢ�Ȓ��A���߂ēo�Z�ǂœo�Z�����P�N���B�ǒ�����Ɏ��������Ă���ǂ�����܂����B�܂��A���������U��Ԃ�Ȃ���A�P�N���̗l�q�����Ă���ǒ������܂����B�����ł͂U�N�����P�N���̂����b�����Ă���Ă��܂����B
�@����̓��w���Ŏʐ^�B�e�Ŏg�p�����}�H���̈֎q�A�ی�ҁA�P�N���̈֎q���T�C�U�N�����ЂÂ������Ă���܂����B�������@�q�ŁA���������ƕЂÂ��������Ƃ����ԂɏI���܂����B�����������w�N�ł��B
�@�R�N���́u���[�����������v�u�ȁ[�ɂ��������v�̃Q�[���A�S�N���͊w�N�Łu�ҏb����ɂ�������v�Q�[���̊w�������Ő���オ���Ă��܂����B�V�����w���Ŋy�������Ȑ����������܂��B�T�N���́u�ψ�����v�̒S�������߂Ă��܂����B�w�Z�̂��߂̎d�����n�܂�܂��B
�@�ߌ�A�Z�̂S�Ԃ̉̎���̈�قɐݒu���Ă����������n��̊�Ɓu���O�e�N�m�X�v�̑�юВ��l�ɁA�ӂ��ݖ�s����ψ���璷�l�Ƌ��畔���l�ƂƂ��ɁA�ӂ��ݖ�s���l����̂��������璷�l���炨�n���܂����B����ɑ����āA�{�Z�����߂Ă������쐬���A���n�������Ă��������܂����B�u���O�e�N�m�X�v����̍H��������q�������Ă����������Ƃ��ł��܂����B�R�N�O�ɕS�t����ݒu���Ă�����������A�T�O���N�L�O�i�Ńo���_�i�̒n�}�ւ̂����͂����Ă�����������ƁA���̉������Ă��������ƍl���Ă��܂��B����͋���ے��Ɉʒu�t���āA�n��A�g�̊ϓ_����Z�O�w�K�ōH�ꌩ�w�������Ă��������悤�ɁA�v������ĂĂ��܂��B����Ƃ���낵�����肢���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@���J�̍����ƂĂ����ꂢ�Ȓ��A���߂ēo�Z�ǂœo�Z�����P�N���B�ǒ�����Ɏ��������Ă���ǂ�����܂����B�܂��A���������U��Ԃ�Ȃ���A�P�N���̗l�q�����Ă���ǒ������܂����B�����ł͂U�N�����P�N���̂����b�����Ă���Ă��܂����B
�@����̓��w���Ŏʐ^�B�e�Ŏg�p�����}�H���̈֎q�A�ی�ҁA�P�N���̈֎q���T�C�U�N�����ЂÂ������Ă���܂����B�������@�q�ŁA���������ƕЂÂ��������Ƃ����ԂɏI���܂����B�����������w�N�ł��B
�@�R�N���́u���[�����������v�u�ȁ[�ɂ��������v�̃Q�[���A�S�N���͊w�N�Łu�ҏb����ɂ�������v�Q�[���̊w�������Ő���オ���Ă��܂����B�V�����w���Ŋy�������Ȑ����������܂��B�T�N���́u�ψ�����v�̒S�������߂Ă��܂����B�w�Z�̂��߂̎d�����n�܂�܂��B
�@�ߌ�A�Z�̂S�Ԃ̉̎���̈�قɐݒu���Ă����������n��̊�Ɓu���O�e�N�m�X�v�̑�юВ��l�ɁA�ӂ��ݖ�s����ψ���璷�l�Ƌ��畔���l�ƂƂ��ɁA�ӂ��ݖ�s���l����̂��������璷�l���炨�n���܂����B����ɑ����āA�{�Z�����߂Ă������쐬���A���n�������Ă��������܂����B�u���O�e�N�m�X�v����̍H��������q�������Ă����������Ƃ��ł��܂����B�R�N�O�ɕS�t����ݒu���Ă�����������A�T�O���N�L�O�i�Ńo���_�i�̒n�}�ւ̂����͂����Ă�����������ƁA���̉������Ă��������ƍl���Ă��܂��B����͋���ے��Ɉʒu�t���āA�n��A�g�̊ϓ_����Z�O�w�K�ōH�ꌩ�w�������Ă��������悤�ɁA�v������ĂĂ��܂��B����Ƃ���낵�����肢���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�S���W���i�j�n�Ǝ��E���w��
�@�i���E���w���߂łƂ��������܂��B
�@���J�̍��A�Ԓd�̍̉ԁA�r�I�������q���������o�}���܂����B�q�������͑҂�����Ȃ��l�q�ŁA������葁���o�Z���܂����B���~���ɒ���o����Ă���N���X�ւ��̖���Ɋ������グ�Ă���q�����܂����B
�@�n�Ǝ��ł́A�V�����搶�����{�Z�͔����̐E��������ւ��܂����B��������̐搶�����q�������̑O�ɕ��т܂����B�ǂ̐搶�������̃N���X�ɂȂ�̂��A���N���N�h�L�h�L���`���܂��B�V�����搶������́A�u�ڂ����Ă������v���ł��鐼�����̎q�������̂��Ƃ��ق߂Ă���܂����B�U�N����������\�̂��ƂŁA�u�v��ψ��Ƃ��Ă݂�Ȃ̑O�Řb���@�������̂ŁA���ƒ��̔��\���撣�肽���B�����w�K�ł͂T�O��e�X�g�����ō��i�ł���悤�ɂ������B�v�ƌ��ӂ��q�ׁA�傫�Ȕ�������炢�܂����B���������ł��B�S�C���\�ł͎q����������傫�Ȕ���Ɗ�����������A�q���������V�����S�C�����������ł����B
�@�w���J���ł́A�S�C�̘b���悭�����Ă��܂����B�q�������̊��҂��`���܂��B
�@�������������͋C�̒��ŁA�V��N�������w���܂����B�u�Z���搶�`�I�v�ƁA�Z��̂���V��N�������̂��Ƃ��o���Ă��āA�������������Ă���܂����B������҂�ْ����Ă���l�q�ł������A�b���Ō�܂ł������蒮�����Ƃ̂ł����P�N���ł����B��������n�܂�w�Z�����Ɉ������������Ă�����悤�ɂ������ł��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�i���E���w���߂łƂ��������܂��B
�@���J�̍��A�Ԓd�̍̉ԁA�r�I�������q���������o�}���܂����B�q�������͑҂�����Ȃ��l�q�ŁA������葁���o�Z���܂����B���~���ɒ���o����Ă���N���X�ւ��̖���Ɋ������グ�Ă���q�����܂����B
�@�n�Ǝ��ł́A�V�����搶�����{�Z�͔����̐E��������ւ��܂����B��������̐搶�����q�������̑O�ɕ��т܂����B�ǂ̐搶�������̃N���X�ɂȂ�̂��A���N���N�h�L�h�L���`���܂��B�V�����搶������́A�u�ڂ����Ă������v���ł��鐼�����̎q�������̂��Ƃ��ق߂Ă���܂����B�U�N����������\�̂��ƂŁA�u�v��ψ��Ƃ��Ă݂�Ȃ̑O�Řb���@�������̂ŁA���ƒ��̔��\���撣�肽���B�����w�K�ł͂T�O��e�X�g�����ō��i�ł���悤�ɂ������B�v�ƌ��ӂ��q�ׁA�傫�Ȕ�������炢�܂����B���������ł��B�S�C���\�ł͎q����������傫�Ȕ���Ɗ�����������A�q���������V�����S�C�����������ł����B
�@�w���J���ł́A�S�C�̘b���悭�����Ă��܂����B�q�������̊��҂��`���܂��B
�@�������������͋C�̒��ŁA�V��N�������w���܂����B�u�Z���搶�`�I�v�ƁA�Z��̂���V��N�������̂��Ƃ��o���Ă��āA�������������Ă���܂����B������҂�ْ����Ă���l�q�ł������A�b���Ō�܂ł������蒮�����Ƃ̂ł����P�N���ł����B��������n�܂�w�Z�����Ɉ������������Ă�����悤�ɂ������ł��B
4���V���i���j�n�Ǝ��E���w������
�@�i���E���w����q��������z�����Ȃ���A���E���S���ŁA���w�����A�����A���A���b�J�[�̃e�[�v�\��A���ʔ��A�L���A�g�C������|���A�ו������܂����B�c�t���A�ۈ牀�̏j�����f���A�V�Q�N��������Ă��ꂽ�t�炵���f��������������\��܂����B���w����P�N���̂��߂ɁA�w�Z�^�c���c��ψ��̂m�����Z����A�n��L���̂Ƃ���Ɂu�������ւ悤�����v�Ƃ����{�Z�L�����N�^�[�́u�ɂ�����ӂ���v�̌f�������Ă�������A�w�Z�����c�̕��X���A�u�n�Ǝ��Ɠ��w��������ˁB�v�Ɛ���܂������ꂢ�ɂ��Ă��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B�E�����q�������̏o��Ƀ��N���N�h�L�h�L���Ă��܂��B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
�@�i���E���w����q��������z�����Ȃ���A���E���S���ŁA���w�����A�����A���A���b�J�[�̃e�[�v�\��A���ʔ��A�L���A�g�C������|���A�ו������܂����B�c�t���A�ۈ牀�̏j�����f���A�V�Q�N��������Ă��ꂽ�t�炵���f��������������\��܂����B���w����P�N���̂��߂ɁA�w�Z�^�c���c��ψ��̂m�����Z����A�n��L���̂Ƃ���Ɂu�������ւ悤�����v�Ƃ����{�Z�L�����N�^�[�́u�ɂ�����ӂ���v�̌f�������Ă�������A�w�Z�����c�̕��X���A�u�n�Ǝ��Ɠ��w��������ˁB�v�Ɛ���܂������ꂢ�ɂ��Ă��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B�E�����q�������̏o��Ƀ��N���N�h�L�h�L���Ă��܂��B
�S���Q���i���j���ی㎙���N���u�ւ�������
�@�V�N�x�ɂȂ�܂����̂ŁA�V���������搶�ƂƂ��ɕ��ی㎙���N���u�ւ������ɂ��������܂����B�V�P�N���̎q���������u����ɂ��́`�I�v�ƌ��C�����ς��̂������ł��B�u�V���������搶���v�Ǝq�������������������Ă��Ă���܂����B�u�S�N���̒S�C�̐搶�͒N�ł����H�v�ƋC�ɂȂ��Ă��������Ȃ��悤�ł��B�u�S���W�������y���݂ɂˁ�v�ƌ����܂����B�V�����搶���q���������y���݂ɂ��Ă��܂��B
 �@
�@
�@�V�N�x�ɂȂ�܂����̂ŁA�V���������搶�ƂƂ��ɕ��ی㎙���N���u�ւ������ɂ��������܂����B�V�P�N���̎q���������u����ɂ��́`�I�v�ƌ��C�����ς��̂������ł��B�u�V���������搶���v�Ǝq�������������������Ă��Ă���܂����B�u�S�N���̒S�C�̐搶�͒N�ł����H�v�ƋC�ɂȂ��Ă��������Ȃ��悤�ł��B�u�S���W�������y���݂ɂˁ�v�ƌ����܂����B�V�����搶���q���������y���݂ɂ��Ă��܂��B
�S���P���i�j���C
�@�ߘa�V�N�x���X�^�[�g�ł��B
���N�x���u�ɂ��͂炫�炫����L�v���p�����܂��B�w�Z�̗l�q���M���Ă����܂��̂ŁA��낵�����肢���܂��B
�@�V�������E�������C���܂����B�����̋��E��������ւ��ɂȂ�A�������ɐV�������������A�t���b�V���Ȋ�Ԃꂪ���낢�܂����B�E�����炠�������Ȋ��}�̔��肪�����܂����B
�@�ӂ��ݖ�s����ψ����Â̒��C���ł��B�s�����ׂĂ̍Z���A�V�C�]�C�Z���@�����A�s�O���璅�C�������@�͏o�Ȃ��܂����B�u�w�����ϗ��ς������Ďq�������̋���ɂ�����悤�Ɂx�w�v���̋��t�Ƃ��Ċw�ё����鋳�t�ł����Ăق����x�v�ƒ��q���璷�l���͋�������܂����B�����s���l���炢�����������}�̌��t�̍Ō�Ɂu�ӂ��ݖ�s�̎q����������낵�����肢���܂��v�Ƃ����t�����������܂����B��Ȏq�ǂ�������a����A���悢�����ɐ��������邽�߂ɑS�͂Ŏ��g�ތ��ӂ�V���ɂ��܂����B


�@�ߘa�V�N�x���X�^�[�g�ł��B
���N�x���u�ɂ��͂炫�炫����L�v���p�����܂��B�w�Z�̗l�q���M���Ă����܂��̂ŁA��낵�����肢���܂��B
�@�V�������E�������C���܂����B�����̋��E��������ւ��ɂȂ�A�������ɐV�������������A�t���b�V���Ȋ�Ԃꂪ���낢�܂����B�E�����炠�������Ȋ��}�̔��肪�����܂����B
�@�ӂ��ݖ�s����ψ����Â̒��C���ł��B�s�����ׂĂ̍Z���A�V�C�]�C�Z���@�����A�s�O���璅�C�������@�͏o�Ȃ��܂����B�u�w�����ϗ��ς������Ďq�������̋���ɂ�����悤�Ɂx�w�v���̋��t�Ƃ��Ċw�ё����鋳�t�ł����Ăق����x�v�ƒ��q���璷�l���͋�������܂����B�����s���l���炢�����������}�̌��t�̍Ō�Ɂu�ӂ��ݖ�s�̎q����������낵�����肢���܂��v�Ƃ����t�����������܂����B��Ȏq�ǂ�������a����A���悢�����ɐ��������邽�߂ɑS�͂Ŏ��g�ތ��ӂ�V���ɂ��܂����B
000